AZ-3-3
エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説(その3)
「『資本論』探求」で欠落しているものと不破哲三氏の誤った主張(その3)
「『資本論』第三部を読む」を検証する。(1/3)

このページのPDFファイルはこちら。
大笑いした仰々しいタイトルの文章
私は、最近、不破さんの本を読むと、そのデタラメさに怒りのほうが多いのですが、「『資本論』第三部を読む」を読んで、大笑いしてしまった箇所があるので、順番は逆になりますが、その話から書かせていただきます。
それは、この本の最後に収められた、「『マルクスと日本』──探究の旅は終着点を迎えた──」という仰々しいタイトルの文章のなかみです。
不破さんの「推測」
内容を紹介すると、概ね次のようにまります。
不破さんは、1981年に『前衛』に「マルクスと日本」という論文を掲載し、「マルクスの知識の広さ」の「源泉が、幕末に日本に駐在したイギリスの初代公使オールコックの著作『大君の都──幕末日本滞在記』ではないか」、と「推論」したとのです。
その根拠として、マルクスは『資本論』第一部で、中世ヨーロッパの封建制を述べている箇所の注で、「日本は、その土地所有の純封建的な組織とその発達した小農民経営とによって、たいていはブルジョア的偏見にとらわれているわれわれのすべての歴史書よりもはるかに忠実なヨーロッパ中世の姿を示している。」(マルクス・エンゲルスの原注。(大月版『資本論』② P938 注192)と述べているが、「オールコックの回想記には、」その根拠となる必要な「すべての材料が提供されている」からだと言うのです。
その後、2013年に出た天野光則氏の論文に、マルクスの抜粋ノートにはオールコックの『大君の都』を読んだ記録がないとの記述があったが、不破さんは、2015年の時点で、抜粋ノートにあったマローン報告からの抜粋は、「比較的短い期間の観察の記録で、しかも、かんじんの、ヨーロッパの中世との比較論がどこにもない」ので、「私の推測には根拠がある」と、いまでも考えているとのことでした。
不破さんの「推測」は「無知」に基づくものだった
私は常々不破さんの「推測」には気をつけろ、不破さんの言うことは原典にあたって確かめてくださいといっていますが、同様な気持ちを持っている方が少なからずいるようです。「最近」(2017年6-7月頃か?)『経済』編集部に、小田さんという方から天野論文で紹介された日本関係の文献四冊を調べた論文が寄せられ、「その中に『ヨーロッパ中世との比較』論がある」ことが分かってそうです。その内容を不破さんは、「このことは、幕末の日本社会が『ヨーロッパの中世像』を示しているという認識が、オールコックだけのものではなく、この時代に来日したヨーロッパからの多くの訪問者に共通するものであったことを、しめしていると思います。」とまとめています。
恐れ入ります。2015年の時点では、ノートに抜粋のあったマローンの文章は、「比較的短い期間の観察の記録で、しかも、かんじんの、ヨーロッパの中世との比較論がどこにもない」から「私の推測には根拠がある」と言ったが、それは、「幕末の日本社会が『ヨーロッパの中世像』を示しているという認識が、オールコックだけのものではなく、この時代に来日したヨーロッパからの多くの訪問者に共通するものであったことを」知らなかったからだというのです。「推測の根拠」の裏付けは、「この時代に来日したヨーロッパからの多くの訪問者に共通する」認識についての「無知」だったというのです。不破さんは、「この時代に来日したヨーロッパからの多くの訪問者に共通する」認識など知らずに、「マルクスの知識の広さ」の「源泉」が、不破さんのようにたまたま読んだ一冊の本(オールコックの『大君の都』)による「狭い」知識であると「推論」(思い込み)したというのです。不破さんは、マルクスを自分と同程度の「狭い」知識の人間と見ているようですが、それは、あまりにもお粗末で、あまりにもマルクスに失礼なのではないでしょうか。
私が、クスクスと〝大笑い〟した理由
そして私が、図書館の読書室で、クスクスと〝大笑い〟したのは、「探究の旅の終着を確認する」という見出しの中の文章です。
どうでも良いようなことに「執着」して、洛陽の紙価をますます低めている不破さんの「終着」宣言ほど秀逸なものはありません。これを読んで、クスクスと〝大笑い〟しない人は、そう多くはないでしょう。
不破さんは言います。
「……幕末の日本の統治体制のうちにヨーロッパの『中世像』をとらえるという見方が、オールコックに特有のものではなく、ペリー艦隊の訪問から日本の開国、そして諸外国からの相次ぐ訪問という過程で、訪問者たちの多かれ少なかれ共通の認識として形成されて来たものであることが、明らかになったと思います。 そうなると、『資本論』でのマルクスの日本論の典拠を、オールコック『大君の都』に限定する理由はなくなります。 そして、自分が読んだ日本関係の書物九冊の名(マローン報告を含めて)をノートに書き留めたマルクスが、オールコック『大君の都』だけをその例外、つまり読んでも名を書き残さなかったとする理由はないわけですから、マルクスの日本論の典拠にオールコックを挙げた一九八一年の私の推論がなりたたないことは、最終的に実証されたと言ってよいでしょう。」、と。
「『マルクスと日本』──探究の旅は終着点を迎えた──」という仰々しいタイトルでの不破さんの話術にごまかされてはなりません。クスクスと〝大笑い〟出来なくなってしまいます。「訪問者たちの多かれ少なかれ共通の認識として形成されて来たものであることが、明らかになった」のは2017年ではありません。1981年に不破さんが貧しい「知識」にもとづいて「推測」(?)したときから「明らか」だったのです。だから、「『資本論』でのマルクスの日本論の典拠を、オールコック『大君の都』に限定する理由」など、1981年からなかったのです。それなのにわけの分からないもっともらしいことを言って、「探究の旅は終着点を迎えた」などと言われたら、誰でも、クスクスと〝大笑い〟して、やっぱり、不破さんは「不破さん」だと、納得する以外ないでしょう。
ただ救いは、マルクスが書き留めたノートに「オールコック」の名がなかったことです。もしも、「オールコック」の名があったなら、貧しい「知識」にもとづく不破さんの「推測」が勝利宣言を持って「探究の旅は終着点を迎えた」こと、請け合いです。
1981年に明らかなことを2017年まで「探究」し続ける〝裸の王様〟
こんなに、クスクスと〝大笑い〟させる不破さんは、自分が「共産党」内の〝裸の王様〟であることに気づかず、訳の分からない蘊蓄を披露して「長旅を終結」させます。
マルクスが書き留めたノートに「オールコック」の名がなかったことを指摘し、異を唱えた天野氏への逆恨みかどうかは分かりませんが、不破さんは、天野氏が「マルクスの日本知識の主要な源泉」としたというマローンの報告書とは別の『日本と中国』という旅行記を取り上げて、「私たちがびっくりするような日本の封建制度美化論で」、「他の訪問者の比較論とはあまりにも違う内容です」と、天野氏を当てこすっています。
そして不破さんは、言わなければ良いのに、ヨーロッパの専制君主の傍若無人の振る舞いを述べたマローンについて、「マローンの目には、中世ヨーロッパの政治社会は、このようなものとして映っていたのでしょう。そこには、ヨーロッパの中世というよりも、ドイツ自身の旧時代にたいするマーロンの独特の認識があったのかもしれません。」と言います。マローンの「私たちがびっくりするような日本の封建制度美化論」の話をしていると思ったら、ヨーロッパの専制君主の傍若無人の振る舞いとは「ヨーロッパの中世というよりも、ドイツ自身の旧時代にたいするマローンの独特の認識」によるものだという、不破さんのヨーロッパの封建制度美化論に変わってしまいました。
続けて、不破さんは、「この論考」に出てきたマローン以外の「旅行記」の筆者5人の名前を挙げ、これらの人たちがイギリス人とアメリカ人であることを述べ、「いずれも、中世と言えばイギリスの王朝をまず思い浮かべるアングロサクソン系の人たちでした。そこから、『ヨーロッパの中世像』への認識のこれだけ大きな違いが出ているのかも知れません。」と言って、マローンの「ヨーロッパの中世」の認識との違いを言います。
論点は流転します。「ヨーロッパの中世というよりも、ドイツ自身の旧時代にたいするマローンの独特の認識」を問題にしていたのが、ドイツとイギリスの「ヨーロッパの中世像」への認識の違いに変わってしまいます。
不破さんは、ドイツ人とアングロサクソン系の人たちとの「『ヨーロッパの中世像』への認識のこれだけ大きな違い」と言いますが、「これだけ大きな違い」なるものについては、私たちに、何も教えてくれません。
「これだけ大きな違い」なるものとは、何なのか。
アングロサクソン系の人たちの代表として出された5人のうちオールコックを除く4人の著作の紹介の中には、ドイツ人のマローンの『日本と中国』に出てくるような「ヨーロッパの専制君主」の具体的な振る舞いについての記述などありませんから、その点での「これだけ大きな違い」なるものは見当たりません。そして、アングロサクソン系の最後の人物、不破さんの推奨するオールコックは、「生産物のうち、余分なものがあれば、すべて大名とその家臣によって吸い取られてしまう」ことや、日本の「土下座の習慣など、大君の高官や大名にたいする一般大衆の屈辱的な関係」など、日本のなかに、「ヨーロッパの遠い昔の時代の封建的・専制的状態と社会秩序が完全な力をもって再現されているのを発見する」と述べるとともに、「これはある点では」イタリアのロンバルディア公国やフランスのメロヴィンガ王朝や昔のドイツで、特定の家から王を選んだころの状態を思わせるものがあり、サクソン時代やプランタジネット朝初期のイギリスの豪族と大体同じように支配権を享受しているように思われると言っています。このように、不破さんの言う「中世と言えばイギリスの王朝をまず思い浮かべるアングロサクソン系の人たち」の一人のオールコックは、「ヨーロッパの遠い昔の時代の封建的・専制的状態と社会秩序」を「イギリスの王朝」に限定などしていないだけではなく、ドイツ人のマローンの『日本と中国』に出てくる「ヨーロッパの専制君主」の「押収し、掠奪し、法外な税金を課し、取り立てる」という具体的な振る舞いと同一の認識、共通認識をもっていました。
それでは、「これだけ大きな違い」なるものとは、いったい、何なのか。
マローンの『日本と中国』は、日本には「十分に熟慮された、法制化された政治的な制度」があるが、「ヨーロッパの専制君主」にはないと述べているので、「法制化」好きの不破さんなので、「法制化」の有無ということなのでしょうか。
いずれにしても、このように読者に理解できないことを言ったあと、「そんなことも頭に思い浮かべながら、一九八一年以来、たどってきたマルクスの『日本知識』の源泉探究の長旅を終結させたいと思います。(『経済』二〇一七年一〇月号)」と、「共産党」内の〝裸の王様〟である不破さんらしく、読者を「愚民」扱いしての「論理」の進め方は、いかにも、この本の最後を締めるにふさわしい文章といえるでしょう。
二〇世紀後半から二一世紀に生きる私たちは、『資本論』だけでなく、「ヨーロッパの中世」を記した文献によって、「ヨーロッパの中世」の専制君主の統治が、多少のバリュエーションはあっても、その実態は、「押収し、掠奪し、法外な税金を課し、取り立てる」、マローンの描いた「ヨーロッパの専制君主」の統治そのものであり、それは、「押収し、掠奪し、法外な税金を課し、取り立てる」日本の封建時代の統治と変わらぬものであることを知っています。そして、不破さんほどの読書力のある人ならば、たまたま読んだ本の内容とマルクスの見解とに共通点があるからといって、マルクスの「剽窃」(源泉を明らかにしないこと)だなどと大胆に「推測」をして自慢などせずに、1981年時点で、マルクスが『資本論』を執筆した当時の文献に当たり、当時日本はヨーロッパでどのように見られていたのかを調べることは、それほど難しいことではなかったはずです。
不破さんは、付け焼き刃がはげたのを必死に取り繕おうとして、ますます信用を失う「論建て」で自らの偉大さを示そうとして、失敗してしまいました。この、自らの偉大さを示そうとした、どうでもいいような「推測」の顛末は、不破さんの人間性と不破さんの「研究」の質を見事に示してくれました。
私たちは、エセ「マルクス主義」者の誤った『資本論』解説から科学的社会主義の革命思想を守り、現代の世界を支配しているグローバル資本を民主的にコントロールして各国人民が等しく文明の利益を享受できる新世界をつくるために、共産主義者を装って害毒を流し続ける不破さんと、大変な時間の浪費ではあるが、しばし、付き合わなければなりません。
※『資本論』に出てくる日本関係の文章で、ここに引用したもの以外の、私がメモした文章を参考に掲載しておきます。『資本論』で、是非、確かめて下さい。
26-1 日本の封建制の崩壊の必然性について
「ヨーロッパによって強制された外国貿易が日本で現物地代から貨幣地代への転化を伴うならば、日本の模範的な農業もそれでおしまいである。この農業の窮屈な経済的存立条件は解消するであろう。」(大月版『資本論』① P183)
26-2 日本でも生活条件の循環はもっと清潔に行われている
「この分割借地は家から遠くにあって、家には便所がない。一家は自分の借地まで行って排泄するか、または、汚い話だがここでは実際に行われているように、戸だなの引き出しに排泄物を入れておくかしなければならない。引き出しがいっぱいになれば、それを抜いて、中身の必要なところにあけるのである。日本でも生活条件の循環はもっと清潔に行われている。」ドクター・ハンターの『公衆衛生。第七次報告書。1864年』から農村労働者の小屋の調査内容を「簡単に要点を述べ」たもの。(大月版『資本論』②P901)
なお、私のメモとは、ホームページ「5温故知新」→「1マルクス・エンゲルスの大事な発見」の各子ページのことで、上記の文章は「I日本関係」に収納されています。各子ページはジャンル別に整理されていますので、是非、活用して下さい。

不破さんらしい第三部の解説のはじまり
不破さんの「『資本論』第三部を読む」は、「(1)第三部の研究対象は何か──『日常の意識』のなかの世界に近づく」というタイトルの文章で始まっています。
これまで見てきたように、第三部の解説のむすびは、不破さんらしい、不破さんにふさわしい内容となりましたが、さすがは不破さん、第三部の解説のはじまりも、実に、不破さんらしいものとなっています。
『資本論』第三部の解説のはじめ、導入部分であるならば、そして『資本論』を「歴史的に読む」と言っているのであればなおさら、第三部は、マルクスのどんな仕上がり状態の草稿をエンゲルスがどのように編集したのかを、その経緯の説明も含めて書かれているエンゲルスの「序文」等を参照して、その解説をはじめるのが、一般的、常識的な解説の仕方でしょう。
しかし、不破さんは違います。
不破さんは、まず、マルクスが「第三部」を資本主義的生産の「総過程の諸姿容」といっているのにエンゲルスが「資本主義的生産の総過程」と変えてしまったのは、「第三部全体の趣旨を誤解させることで、残念な訂正だったと思います」と言って、エンゲルスが「第三部」のタイトルを「資本主義的生産の総過程」としたことが「第三部全体の趣旨を誤解させる」ことでもあるかのように、「巧み」な話術によって、読者に印象づけます。「序文」を読んでいただければ分かるとおり、『資本論』第三部の編集た大変な苦労をしたエンゲルスは、不破さんの「巧み」な話術によって、「第三部全体の趣旨を誤解させる」修正主義者の地位に落としめられてしまいます。
そして、つぎに、「本文に入る前に、のべておきたいことがあります。」と言って、不破さんが発見(創作)した『資本論』の「歴史的」読み方に、なんとなく誘導するために「第三部草稿」が「未完稿の形のままで残された」という特徴をあげ、その理由として、「著作の諸部分を互い違いに仕上げている」というマルクス自身の言葉を引用しています。
ちょっとわき道に(1)
ちょっとわき道にそれますが、「著作の諸部分を互い違いに仕上げている」ということに関して、不破さんが「第二部を読む」でおこなったマルクスに対する侮辱を思い出していただきたいと思います。(なおこのページでは、不破さんの論述がこれまでの自身の「主張」や「推測」と異なるが、本題の進行に直接関係のない場合、必要に応じて、「ちょっとわき道に」としてコメントさせていただきます。)
不破さんは、「『資本論』第二部を読む」で、マルクスが第一部草案を書き終えたあと、1864年の夏頃から、「第3部」を第2章(草稿の「章」は『資本論』では「篇」のことです。)→第1章→第3章の順に書き、その後、1865年の前半に「第2部 資本の流通過程」の草案を書きはじめたことについて、その理由を、マルクスの三つの無能のせいにしていました。
私は、ホームページ「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」の冒頭の「不破さんらしい『第二部』の成立過程のスケッチ」で、なぜ「第1部」の執筆のあと「第2部」ではなく「第3部」を書いたのかということについて、MEGA「解題」でその理由について、「第1部」第6章のあと「第3部」を書ことによって、「本質と直接的な現象との、問題を孕んだ関連を矛盾なく説明すること、運動法則それ自体を暴くばかりでなく、同じくこの法則の貫徹メカニズムを証明することにも努めていたことに帰せられるべきものであった」(大谷禎之介『マルクスの利子生み資本論』2 P389-390)と述べられていることを紹介し、不破さんの言うマルクスの「三つの無能」説が不破さんの認識能力の無さとデタラメな「推測」によるものであることを詳しく説明しました。※詳しくは、ホームページ「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」を、是非、参照して下さい。
不破さんは、「第二部を読む」では、「第3部」を第2章→第1章→第3章の順に書き、その後、1865年の前半に「第2部 資本の流通過程」の草案を書きはじめたことについて、マルクスの三つの無能の「問題」を理由にしていましたが、マルクスが意識的に「著作の諸部分を互い違いに仕上げている」ということを不破さんも十分に知っているということを、ここで、明らかにしてしまいました。不破さんという人は、根っからのペテン師なのでしょうか。
さて、話を戻します。
不破さんは、不破さんが創作した『資本論』の「歴史的」読み方に、なんとなく誘導するために『資本論』「第三部草稿」が「未完稿の形のままで残された」という特徴をあげたあと、マルクスのエンゲルスへの手紙で「第三篇」について、「第一篇」、「第二篇」が内容をかなり詳しく紹介しているのにたいし簡潔に述べられている点をあげて、「このことは、第三篇について、マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいたことを示すものですが、その意味は、第三篇を読むところで説明することにします。」と、不破さん得意の「推測」が、力余って、「断定」となり、その理由は「第三篇を読むところで説明する」と思わせぶりに言うことによって、不破さん「創作」の「『資本論』の歴史的読み方」へ読者を誘導しようとします。
不破さんは、マルクスのエンゲルスへの手紙で「第三篇」が簡潔に述べられている点を口実に、「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」と「断定」し「真実」であるかのように思わせ、その理由は「第三篇を読むところで説明する」といいます。デマを「真実」であるかのように言って世論を誘導する手法は、「トンキン湾事件」を持ち出すまでもなく陰謀家の常套手段ですが、読者が「第三篇を読むところ」まで、不破さんの「断定」が「真実」であるかのように思い込まされたのでは、不破さんの思うつぼになってしまいますので、より詳しい説明は「第三篇を読む」ところに譲ることにして、ここでは、マルクスの『資本論』の編集の軌跡から、「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」ことなどどこにもみあたらないことを見てみましょう。
マルクスは、1864年から1865年にかけて「第三篇」を執筆したあと、1865年の前半に「第二部」の草案を書き、その後『資本論』第三部の「第四篇」以降の草案を執筆したといわれています。そして、第三部の「第四篇」以降の草案を執筆したあと、「第二部」については1881年の第8稿まで執筆を続け『資本論』の執筆を打ち切りました。しかし、この間に、マルクスが「第三篇」の「内容を大きく変えるつもり」だなどと言った記録など聞いたこともなければ、「第三篇」の内容を変えたこともありません。不破さんの言っていることが、不破さんの「創作」であることは、「第三篇を読む」ところで明らかになります。ご期待下さい。
ちょっとわき道に(2)
マルクスのエンゲルスへの手紙で「第一篇」、「第二篇」が内容をかなり詳しく紹介しているのにたいし、「第三篇」が簡潔に述べられているという点に関し、ここでまた、ちょっとわき道にそれさせていただきます。
不破さんは『前衛』の2014年1月号で、エンゲルスが『空想から科学へ』の中で「剰余価値の搾取を抜きにした資本主義論を展開した」(P102)というデマを言い、さすがにまずいと思ったのか、あるいは最初に大ウソをつく陰謀家の常套手段なのかよく分かりませんが、「第三章の資本主義論には、剰余価値のことが一言も出てこない」(P104)と訂正します。そして、エンゲルスのこの誤り──不破さんのデマ──の原因として「これには歴史的制約もあったと思います」と述べ、エンゲルスが『資本論』の第二部、第三部について「ごく簡単な筋書きを手紙で知らされた以外は、マルクスが死ぬまで草稿を目にすることはありませんでした」と言っていました。それが今度は、「第二部、第三部の内容を説明したさいに」「第三部の第一篇、第二篇については、草稿に執筆した内容をかなり詳しく紹介して」いると『前衛』(2014年1月号)とは違うことを言い、第三篇が「ごく簡潔」に書かれていることをもって、「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」のではないかなどという不破さんの「推測」の「論拠」になってしまいます。ホームページ「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」の中で、「不破さんと、『ああいえば、上祐』」というタイトルの文章を書きましたが、ほんとうに、「ああいえば、上祐」です。
不破さんは、『前衛』の2014年1月号では、エンゲルスが『空想から科学へ』の中で「剰余価値の搾取を抜きにした資本主義論を展開した」というデマの「根拠」に、エンゲルスは『資本論』の第二部、第三部について「ごく簡単な筋書きを手紙で知らされた」だけだったとウソを言い、『『資本論』探究 全三部を歴史的に読む下』では、「第三部の第一篇、第二篇については、草稿に執筆した内容をかなり詳しく紹介して」いるのに、第三篇の「利潤率の傾向的低下の法則」に関しては、すでに「第一部で展開されたことからも、明らかだ」として「ごく簡潔に」述べられていることをもって、マルクスが『資本論』の「内容を大きく変えるつもりでいた」という、自分に都合のいい「推測」の「根拠」としてしまいます。不破さんは、マルクスとエンゲルスの思想の状況を、手紙に書かれた内容からではなく手紙の長さで、自分の考えに都合がいいように「推測」し、自分の「推測」に合わせて手紙の長さも「調整」してしまいます。
大体において、『空想から科学へ』の中で「剰余価値の搾取を抜きにした資本主義論を展開した」などというのは真っ赤なウソですが、マルクスがエンゲルスに、利潤率の傾向的低下の法則について「第一部で展開されたことからも、明らかだ」として「第三篇」の内容を簡潔に報告したことが、「剰余価値の搾取を抜きにした資本主義論」にどのように結びつくのか、不破さんにお聞きしたい。
なお、前掲の『前衛』の文章はさらに続いて、そのために、「第三部になると、一段と編集が難しくなって、七,八年かかりました」とエンゲルスの能力のなさをやゆしたあと、『空想から科学へ』について、「ですから、経済学に関して言うと、エンゲルスの思い違いという部分があっても不思議でないのです」と結論づけています。まったく、言いたい放題ですが、『『資本論』探究 全三部を歴史的に読む下』とつなぎ合わせて読むと、不破さんが如何に〝矛盾〟していることを言っているかが明らかになります。
不破さんは、エンゲルスがマルクスから手紙で『資本論』の第二部、第三部についての「ごく簡単な筋書き」を知らされただけだったから「経済学に関して言うと、エンゲルスの思い違いという部分があっても不思議でない」と言いました。しかし、「ごく簡潔に」書かれていたのは「第三篇」でした。そして、『『資本論』探究 全三部を歴史的に読む下』の「『資本論』第三部を読む」では、不破さんは、「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味をまったく理解できず、「第三篇」(「第三篇」は「第一三章」から「第一五章」までの三つの「章」で構成されています。)につて、「第一三章」は「マルクスの最大の経済学的発見を記録した輝かしい章」だと茶化し、「第一五章」は「以後の草稿で取り消した章」とデマを言い、「第一四章」は「第一五章が取り消されたために不要になった章」だとして切り捨てています。だから、不破さんの立場からいえば、マルクスのエンゲルスへの手紙で「第三篇」が「ごく簡潔」に書かれていることは、エンゲルスが「経済学に関して」「思い違い」を少なくすることができたということになります。それなのになぜエンゲルスは「経済学に関して」「思い違い」をしても「不思議でない」のか不思議でならない。不破さんのその場しのぎの「推測」と「断定」がどうにも解決できない〝矛盾〟を生んでしまいました。※『前衛』2014年1月号での不破さんのエンゲルスへの中傷の詳し説明は、ホームページ4-14「☆科学的社会主義の旗を掲げて共に闘ったマルクスとエンゲルスが、経済(社会の土台)についての共通認識を持っていなかったという不破さんの無責任な推論」を、是非、参照して下さい。
このように、不破さんは、第三部の解説の「はじめに」にあたる部分で、『資本論』第三部を編集した功労者のエンゲルスを「第三部全体の趣旨を誤解させる」修正主義者として紹介し、自ら創作した「『資本論』の「歴史的」読み方」へのプロローグとしています。
なんとも、不破さんらしいやり方です。
第三部はどのように編集されたか、エンゲルスの声を聞いてみよう
第三部の解説の「はじめに」にあたる部分の不破さんのこのような異常な書き出しの内容の真偽を明らかにするまえに、第三部はどのように編集されたのか、エンゲルスの声を聞いてみましょう。
エンゲルスは、まずはじめに、第三部の編集が約一〇年を要した難産であった理由を述べています。理由は、二つあって、一つはエンゲルス個人に関わることで、もう一つは第三部の草稿の完成度によるものでしたが、ここでは、「第三部の解説」という観点から、エンゲルス個人に関わる問題についてはごく簡単に触れるにとどめて、第三部の草稿の完成度に関わるエンゲルスの編集上の対応について、より詳しく見てみたいと思います。
エンゲルスは、第三部の編集に約10年を要した理由として、「まず第一に、そして最もひどく私を妨げたのは、ずっと前からの視力の衰えで、そのために私の執筆労働時間は何年ものあいだ最小限度に制限されていたし、今でもただ例外的に人工光線のもとでペンをとることを許されているという有様である」と「エンゲルス個人に関わる」理由を挙げています。「そのうえに、」『資本論』第一部の英語版やマルクスと自分の旧著の翻訳や国際労働運動の成長にともなう「ますますふくれあがってくる仕事が私ひとりの肩にかか」り、「私の理論的な仕事のために好ましい程度をはるかに超えて私の助力が頻繁に求められ」るなど、「断ることのできないほかの仕事があった。それらは新たな研究なしにはできないことも多かった。」助力が必要な「政党間の交渉は冬はたいてい書面で行われるが、夏はおもに面談で行われることになってい」たため、『資本論』のような、「私にとっては、中断を許さない仕事は冬のあいだに、ことに一年の最初の3か月のあいだにやってしまうよりほかはなくなってきた。」そして、「人間も七〇歳を超えれば」、「困難な理論的な仕事の場合に中断を克服することは、もはや以前のようにたやすく急速にはできない。だから、ある冬の仕事が完全に最後まで仕上げられてしまわなかったかぎり、その仕事は次の冬に大部分はまた初めからやりなおさなければならなかった。そして、最も困難な第五篇では特にそういうことが起きたのである。」
エンゲルスは、「エンゲルス個人に関わる」理由を、概ねこのように、挙げています。そして、もう一つの理由である「第三部の草稿の完成度」について、エンゲルスは「第三部のためには、たった一つの、しかも欠けたところのまったく多い最初の草稿があっただけだった」と述べています。
そしてこれらの「草稿」と、どのように格闘し、編集をなし遂げたのか、その概要は以下のとおりです。第三部を読み進めるとき、常に、頭の片隅において、読み進めて下さい。
◇「私の仕事は、手稿の全部を、私にとってさえしばしば判読に骨の折れるような原文から読みやすい写しに書き取らせることから始まったが、これだけでもかなりの時間がかかった。」
◇「第一篇のためには主要原稿は大きな制限を加えなければ使えないものだった。」
第一章は、原稿の「もっとあとではじめて、しかもことのついでに、取り扱われ」たものをまとめたものである。「第二章は主要原稿から取ってある。」第三章は、70年代に作った「剰余価値率と利潤率との関係が数式で説明してある」ノートを友人のサミュエル・ムアが要約したものと、「ときおり主要原稿を利用しながら」仕上げた。「第四章は表題があるだけだった。」「私は自分でそれを書き上げた」。「第五章以下では」、主要原稿に、「ここでもまた非常にたくさんの入れ替えや補足が必要になった」。
これに続く三つの篇については、文章上の校正は別として、ほとんどまったく元の原稿によることができた。
◇「おもな困難は第五篇にあった」。
「ちょうどここでマルクスは書き上げのさいちゅうに前に述べたような重い病気の一つに襲われたのだった。だから、ここにはできあがった草案がないのであり、これから中身を入れるはずだった筋書きさえもなくてただ仕上げの書きかけがあるだけであって、この書きかけも一度ならず覚え書きや注意書きや抜き書きの形での材料やの乱雑な堆積に終わっているのである。」
「私がまず試みたのは、」「すきまを埋めることや暗示されているだけの断片を仕上げることによってこの篇を完全なものにし、この篇が著者の与えようと意図したすべてのものを少なくともおおよそは提供するようにすることだった。これを私は少なくとも三度はやってみたが、しかしそのつど失敗した。そして、そのためにむだにした時間こそは、遅延の主要な原因の一つなのである。」「一八九三年の春この篇のためのおもな仕事をすませたのである。」
「第五篇」の第二一章から第二九章までは、若干の手入れが必要だった。
「ところが、第三〇章からはほんとうの困難が始まった。ここからは、引用文から成っている材料を正しい順序に置くことだけではなく、絶えず挿入文や脱線などに中断されながらまた別の箇所でしばしばまったく付随的に続けられている思想の進行を正しい順序に置くことも必要だった。こうして第三〇章は入れ替えや削除によってできあがり、この削除されたもののためには別の箇所で使いみちが見いだされた。」
「第三一章は再びかなりよくまとめて書き上げてあった。」
次に、「『混乱』という表題をつけた長い一篇が続き」、それを「批判的に風刺的に取り扱おうと」「いろいろやってみたあげくに、この章を組み立てることは不可能だということをさとった。」
「その次には、私が第三二章で取り入れたものがかなりよく整理されて続いてい」た。
「『混乱』からあとの、そしてすでにそれ以前の箇所で取り入れられなかったかぎりでの、すべてのこれらの材料から、私は第三三~三五章をまとめ上げた。」
「『資本主義以前』(第三六章)は完全に書き上げてあった。」
◇「第六篇 超過利潤の地代への転化」の編集について。
「地代に関する篇(第六篇、第三七章~第四七章──青山)は、ずっと完全に書き上げられていたとはいえ、けっしてよく整理されてはいなかった」。「いちばん手がかかったのは、差額地代Ⅱのところの表であり、また、第四三章ではそこで取り扱われるべき差額地代Ⅱの第三の場合が全然検討されていないということを発見したことだった。」
◇「最後に第七篇は完全に書き上げられてはいたが、ただ最初の草案でしかなく、印刷のできるものにするためには、まずその果てしなくもつれあったいくつもの章句を分解しなければならなかった。」
第七篇の「最後の章ははじめのほうがあるだけである。ここでは、地代、利潤、労賃という三つの大きな収入形態に対応する発展した資本主義社会の三つの大きな階級──土地所有者、資本家、賃金労働者──と、それらの存在とともに必然的に与えられている階級闘争とが、資本主義時代の事実上現存する結果として示されるはずだった。このような最後の総括をマルクスは印刷直前の最後の改訂のために保留しておくのが常だったが、その場合には最新の歴史的な諸事件がいつもまちがいなくきまって彼の理論的展開の例証を最も望ましい現実性において提供したのである。」
これが、エンゲルスが『資本論』第三部の編集に約一〇年を要した理由です。

不破さんが、エンゲルスの序文を皆さんに伝えたくなかった理由
不破さんは、エンゲルスが『資本論』第三部の編集に約一〇年を要したのは、「経済学に関して言うと、エンゲルスの思い違いという部分があっても不思議でないのです」と言い、そのために、「第三部になると、一段と編集が難しくなって、七,八年かか」ったと言います。エンゲルスが『資本論』第三部の編集に約一〇年を要したのは、エンゲルスの経済学に対する知識のなさの賜物のようにいう不破さんにとって、上記の「序文」にあるようなエンゲルスの苦闘など、皆さんに伝えたくなかったのかもしれません。
そして、不破さんには、エンゲルスの序文のなかの「『資本論』第三部の編集に約一〇年を要した理由」で、もう一つ、皆さんに伝えたくなかった訳があります。
私は、不破さんが「第二部」の解説の最後で、不破さん自らが創作した「恐慌の運動論」にとりつかれて、狭隘な「最後の章」しかイメージできず、「第二部」の「最後の章」が、「体系的な恐慌論を展開した」ものになるという「推測」をしたことに対し、その推論を退けて、「恐慌論」そのものの本格的展開は、「恐慌」という資本主義的生産の総過程の具体的諸形態の一つの論究であり、「第三部」に属するものと考えることを述べました。
そのとき、私は、マルクスが、エンゲルスあての1868年の手紙で、『資本論』は、「資本の一般的本性」を究明し、「三つの階級の、すなわち資本家、土地所有者および賃労働者の経済的な諸関連を暴」き、「資本主義的生産様式の『解体』を、ブルジョア社会の克服にまでいたるべき階級闘争として論じるつもり」であるといい、マルクスは、1878年11月には第2巻(第2部と第3部)の刊行が1879年の末には可能だと考えていたが、1879年に、「『現在のイギリスの産業恐慌がその頂点に達する以前には』第2巻を刊行しない、と言明し」、1880年には、「『ちょうどいましがた、若干の経済現象が新しい発展段階にはいった』ところであり、これらの現象が、新たな仕上げを要求していたのである」と述べていることも紹介しました。そして、マルクスにとって、1880年に「若干の経済現象が新しい発展段階にはいった」ことは、「理論的内容と内的構造とは主要な点においてすでに与えられて」いるが「もともとはあらゆる研究がもっている……荒削りの形態」である「草稿」を仕上げる絶好の好機が到来したと思ったのではないかとも言いました。
エンゲルスの、第七篇についての、「最後の章ははじめのほうがあるだけである。ここでは、地代、利潤、労賃という三つの大きな収入形態に対応する発展した資本主義社会の三つの大きな階級──土地所有者、資本家、賃金労働者──と、それらの存在とともに必然的に与えられている階級闘争とが、資本主義時代の事実上現存する結果として示されるはずだった。このような最後の総括をマルクスは印刷直前の最後の改訂のために保留しておくのが常だったが、その場合には最新の歴史的な諸事件がいつもまちがいなくきまって彼の理論的展開の例証を最も望ましい現実性において提供したのである。」との序文の文章は、不破さんの「推論」を退け、私の考えと一致するものです。
これが、不破さんが、エンゲルスの序文のなかの、第三部の編集に約一〇年を要した経緯にかかわる文章について、皆さんに伝えたくなかった、もう一つ、理由だと思います。
序文の中の、不破さんにとって耳の痛い言葉の三つの代表例
序文は、エンゲルスが『資本論』第三部の編集に約一〇年を要した理由の説明にに続いて、「第三部」への導入の文章になります。第三部の第三篇までを学ぶ上で大変重要な問題が提起されていますので、エンゲルスが言っていることで理解できないこと等があったらメモを取って、第三部の学習への備えにして下さい。そして、第三部の学習が終わったら、もう一度、序文を読み返してみましょう。
なお、この「第三部」への導入の一連の文章の中にも、不破さんにとって耳の痛い、聞きたくない言葉がいくつも出てきます。そのうちの三つの代表例を紹介します。
①物事の捉え方
「諸物やそれらの相互関係が固定したものとしてではなく可変的なものとしてとらえられるところでは、それらの思想的模写である諸概念もやはり変化や変形を受けるものだということ、それらは硬直した定義のなかにはめこまれるのではなく、それらの歴史的または論理的な形成過程のなかで展開されるのだということ、これはまったく自明なことである。」(『資本論』大月版④P19)
不破さんは、敵を攻撃するときには、上記のような弁証法的な見方、科学的な見方を完全に捨て去ります。不破さんは、マルクス・エンゲルス・レーニンを歴史の中で見ることを拒否します。
私たちが運動を進めるうえで大切なことは、今をしっかり読むことです。今をしっかり読むとは、第一に、現在の矛盾の集中点をしっかりつかむこと、運動の環をしっかりとつかむこと、そして第二に、その現れと予想される結果を国民に曝露することです。そして、その時々の「矛盾の集中点」がマルクス・エンゲルスの時代には「恐慌」であり、レーニンの時代には「帝国主義と帝国主義戦争」でした。資本主義の矛盾のその時代々々の必然的で典型的な現れを国民に知らせることはマルクス・レーニン主義者にとって最も重要なことです。
しかし、不破さんとその仲間たちは、その時々の資本の行動と国家の行動を見て、その時々の科学的社会主義の党の政策を判断することができません。
だから、19世紀後半に生きたマルクスとエンゲルスが「恐慌が政治的変革の最も強力な槓杆」だというと、マルクスは「恐慌=革命」説に立っていたと言ってマルクスに濡れ衣を着せます。そして、19世紀末から20世紀前半に活躍したレーニンが当時の帝国主義段階を「死滅しつつある資本主義」だというと、「それらの発言からからもうほぼ百年たちましたからね」とレーニンを嘲笑し、揶揄します。
そのくせ、20世紀から21世紀にかけて活動している不破さんたちは、「利潤率の傾向的低下の法則」の持つ重要な意義を忘れ去り、マルクスの「基本的矛盾」から「利潤第一主義」を抽出して、それ(利潤第一主義)を克服するために、「労賃が増加すれば経済はよくなる」と言って、マルクスのいう「健全で『単純な』(!)常識の騎士たち」(『資本論』第2巻 大月版 P505~506)のレベルに成り下がり、資本主義の大問題な点は「利潤第一主義」だとして、「利潤第一主義」からくる重大な弊害はすべて資本主義の「桎梏」だと言い、「地球温暖化」も「原発」も「恐慌」も資本主義の「桎梏」の現れだなどと訳の分からないことを言って、味噌も糞も一緒にして、国民の科学的・階級的認識を退化させようとしています。
その結果、「危機的な世界」の変革については「どういう形態で起こるかの予測はできません」としゃじを投げてしまいます。確かに、占い師ではないから「予測」はできない。しかし私たちは科学的社会主義を会得した人間集団だ。問題が何かをつかむ能力を持ち、問題解決の方法を知っている。しかし不破さんは科学的・弁証法的な認識能力を持ち合わせていないから現代の「危機的な世界」の変革については〝しゃじを投げ〟、マルクス・エンゲルス・レーニンに対しては悪罵を投げつける。こんな寝ぼけたことを言っているようでは、100年たっても革命は起きない。※不破さんが、マルクスは「恐慌=革命」説に立っていたという暴論に関してはホームページ4-19「☆不破さんは、マルクスが1865年に革命観・資本主義観の大転換をしたという、レーニンも気づかなかった大発見を、21世紀になっておこない、マルクスの経済学をだいなしにしてしまった。」を、レーニンの「帝国主義論」を揶揄し、「それらの発言からからもうほぼ百年たちましたからね」とレーニンを嘲笑したことに関しては、ホームページ4-13「☆レーニンの資本主義観、社会主義経済建設の取り組み、革命論への、反共三文文筆家のような歪曲と嘲笑、これでもコミュニストか」を、「地球温暖化」も「原発」も「恐慌」も資本主義の「桎梏」の現れだなどと、味噌も糞も一緒にしてしまうことに関しては、ホームページ4-3「☆「桎梏」についての不破さんの仰天思想」を参照して下さい。
②史的唯物論
「マルクスによって1845年になされた」「どこでもいつでも政治的な状態や事件はそれに対応する経済状態によって説明されるという発見」(大月版『資本論』④ P23-24)*1845年になされた発見成果は『哲学の貧困』(1847年)で示された──青山。
不破さんは、このことを忘れ、グローバル資本の行動を見ようともせず、党員を「生活向上」と「平和」だけを訴える「健全で『単純な』(!)常識の騎士たち」にしようとしています。
③科学的社会主義者の基本精神
「科学的な問題に携わろうとする人は、なによりもまず、自分が利用しようとする書物をその著者が書いたとおりに読むことを、またことに、そこに書いてないことを読み込まないようにすることを、学ばなければならないのである。」(『資本論』大月版④P30)
このエンゲルスの言葉は、科学的社会主義者のモラルであり、基本精神を表しています。お互いにこのような精神を持ってコミュニケーションをとらなければ会話は成り立たないし、理論的な進展もありません。しかし、不破さんの他者の書物にたいする接し方は、攻撃しようとするものについての「推測」と「歪曲」で成り立っています。今回の「『資本論』探究」のなかの不破さんの誤りのほとんど全てが「推測」と「歪曲」に基づくものです。その代表例が、「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」で指摘した下記の文章で、確かにマルクスはお手上げのように見えます。(お手上げかどうか、PDFの41ページを参照して、確かめて下さい。)
「しかし、マルクスは、そこまで(拡大再生産の継続が不可能だということ──青山)話を進めず、第一年度の表式に、あれこれの問題を見つけだして、議論の空転をはじめました。……(青山の略)が大問題だとして、きりきり舞いするのです。これは、率直に言って、問題のないところに無理に問題をつくり出すといった式の話でしたが、この時点では、それが解決のつかない重大問題に見えたのでした。
マルクスはそこからぬけだそうとして、あれこれの奇策や邪道にまで考えをめぐらせたようで、その様子はあちこちにちりばめられた溜息まじりの言葉からもうかがわれます。
『しかし待て!ここにはなにかちょっとした儲け口はないか?』、『突然、仮定をすり替えてはならない』、資本主義的機構に固着している『汚点』を『理論的諸困難をかたづけるための逃げ道として利用してはならない』
マルクスは、ついに、考察の途中で筆を投げたようで、第三回目の挑戦は、『Ⅱの資本家たちの一部のあいだにおける追加貨幣資本の形成が、他の一部の明確な貨幣喪失と結びつく……』と書いたところで、ぷつんと途切れています。こういうことも、マルクスの草稿では、珍しいことでした。」
これが、不破さんが『資本論』の中の文章の一部を借用して、驚くべき創作を行った文章です。私は、「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」で、「これはもう、エセ「マルクス主義」者などという範疇を遙かに超えて、ペテン師、詐欺師とでもいうべきものです」と書きました。この不破さんの文章を読んで、マルクスの無能さが分かれば不破さんの文筆力は「最高」ということになります。
エンゲルスは、二〇世紀から二一世紀にかけて、不破哲三氏という「科学的社会主義」を語るペテン師が現れるのを見越していたようです。万一不破さんが悔い改めるというのであれば、この言葉を額縁にして一番目のつくところに掲げることを推奨します。そして、当然であるが、私たちはこの言葉に則って、切磋琢磨して、科学的社会主義の思想を発展させなければなりません。
私が「不破さんの誤り」を指摘する原動力の一つは、不破さんのデタラメな「推測」とマルクス・エンゲルス・レーニンの思想の「歪曲」への怒りです。だから、皆さんは、時々耳障りな文章に出会うことがあるかもしれませんが、あいつ「怒ってるな」と高いところから見下ろして、笑って許して下さい。何だか、最後が私の懺悔の言葉になってしまいました。恥ずかしい。
さてそれでは、第三部の解説の「はじめに」にあたる部分で、『資本論』第三部を編集した功労者のエンゲルスを「第三部全体の趣旨を誤解させる」修正主義者として紹介し、自らの主張に読者を導こうとする、なんとも、不破さんらしいやり方について、検証して行きましょう。
『資本論』の読者は、第三部全体の趣旨を誤解させられたか
不破さんは、マルクスが「第三部」を資本主義的生産の「総過程の諸姿容」といっているのにエンゲルスが「資本主義的生産の総過程」と変えてしまったのは、「第三部全体の趣旨を誤解させることで、残念な訂正だったと思います」と言います。
しかし、『資本論』の第三部を読んだ人で、第三部のタイトルが「資本主義的生産の総過程」となっていることによって、「第三部全体の趣旨」を「誤解」した人がいたでしょうか。いるとすれば、それは、もう少しあとでよく分かりますが、「第三部全体の趣旨」を最初から「誤解」している不破さんくらいなものでしょう。
私たちは、著作の内容を読んでその著作の中に書いてあることを理解します。不破さんのこの主張を読んで不破さんに賛同する人がいるとすれば、その人は、まだ『資本論』を読んでいない人です。不破さんの主張は、不破さんの解説だけを読んでいる人にそう思わせるだけのものです。もしも「資本主義的生産の総過程」というタイトルがふさわしくないのであれば、「内容」と「タイトル」が一致せず「残念な訂正だった」だけで十分です。「タイトル」で「内容」を変えることはできません。それなのに、エンゲルスが、いかにも、「第三部全体の趣旨」を変えてしまい、『資本論』の読者に「誤解」を与えているかのように言うのは、『資本論』を読んだ人にとって事実ではありません。
そもそも、「第三部」でマルクスとエンゲルスは何を言い、何を言おうとしたのか、一緒に見てみましょう。
『資本論』第三部は何を言い、何を言おうとしたのか
先ほども見たように、私は、「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」で、「第1部」の執筆のあと「第2部」ではなく「第3部」を書いた理由について、MEGA「解題」には、「第1部」第6章のあと「第3部」を書ことによって、「本質と直接的な現象との、問題を孕んだ関連を矛盾なく説明すること、運動法則それ自体を暴くばかりでなく、同じくこの法則の貫徹メカニズムを証明することにも努めていたことに帰せられるべきものであった」と述べられていることを紹介しました。
私は、同じく「エセ『マルクス主義』者の『資本論』解説(その2)」で、『資本論』の全体の構成について、大雑把に、①「第一部 資本の生産過程」は、「価値」、「資本」、「剰余価値とその生産」、「資本の蓄積過程」等資本主義における「資本」の「生産過程」の資本主義独自の「特徴」・「要素」、富の源泉とその生産過程の解明という資本主義の「本質」を、つまり、「資本の生産過程」論究し、②「第二部 資本の流通過程」は、その「資本の生産過程」が作用する資本主義の「軀体」の「構造」を論究して、資本主義的生産様式の成立条件等を明らかにし、③「第三部 資本主義的生産の総過程」は、「第一部」の資本主義独自の富を生み出す過程、つまり「資本の生産過程」で、生み出された富が「第二部」の「資本の流通過程」という「軀体」──それは、「市場」、「商業」、「信用」等、資本の運動法則が円滑に進行するための「機能」・「器官」が備わった「軀体」──を通って「資本主義的生産の総過程」を通じて富が分配されるメカニズムを説明し、あわせて、「三つの階級の、すなわち資本家、土地所有者および賃労働者の経済的な諸関連を暴」き、「資本主義的生産様式の『解体』を、ブルジョア社会の克服にまでいたるべき階級闘争として論じるつもり」であった、ことを述べました。
このように、「第三部」は、「資本の生産過程」で創られた富が「資本の流通過程」を通じ、「資本主義的生産の総過程」で「諸姿容」をとって分配されメカニズムを明らかにし、そこでの階級闘争を呈示することによって、資本主義社会を土台から解明した『資本論』にふさわしい完結篇となるべき地位が与えられていたと思われます。
先ほど、私は、マルクスがエンゲルスあての手紙で、『資本論』が、「資本の一般的本性」を究明し、「三つの階級の、すなわち資本家、土地所有者および賃労働者の経済的な諸関連を暴」き、「資本主義的生産様式の『解体』を、ブルジョア社会の克服にまでいたるべき階級闘争として論じるつもり」であるといい、エンゲルスが、たぶんマルクスのこの言葉を念頭において、「序文」で第七篇について、「最後の章ははじめのほうがあるだけである。ここでは、地代、利潤、労賃という三つの大きな収入形態に対応する発展した資本主義社会の三つの大きな階級──土地所有者、資本家、賃金労働者──と、それらの存在とともに必然的に与えられている階級闘争とが、資本主義時代の事実上現存する結果として示されるはずだった。」と述べていることを紹介しましたが、私の「推論」はマルクスとエンゲルスのこれらの言葉に依拠しています。
このように、私は、「第三部」は、資本主義的生産の総過程における富の分配と階級闘争の篇であると捉えています。なお、「資本主義的生産の総過程」とは何か、という詳しい説明は、もう少しお待ち下さい。

不破さんは、主題は「総資本の諸姿容」だという
不破さんは、マルクスは第一巻初版への「序言」で「この著書の第二巻は資本の流通過程(第二部)と総過程の諸姿容(第三部)とを取り扱い」と述べており、第三部の冒頭の文章では、資本主義的生産の「総過程について『一般的反省』をおこなうことは、第三部の課題ではないとの断り書きまで書きそえています」と言います。
そして、不破さんは、「第三部で研究するのは、私たちがこれまで第一部、第二部で研究してきた世界とは、次元の違う世界なのです」と言い、これまで研究してきたのは「資本主義社会の本質的、内面的な世界」で、「これから研究するのは、『社会の表面』に現れる世界」だと言い、「これまで見てきた世界の最大の特徴は、それが、商品が価値どおりに交換され、流通する世界だということでした」が「第三部で研究される『生産当事者たちの日常の意識』に近づいてゆく世界では、そこがどう変わるのか。それは、これからの研究のお楽しみに残しておくことにしましょう。
そしてマルクスは、こういう意味で、第三部の内容の核心を示すものとして、『諸姿容』の語を押し出したのでした。」と、言います。
「青い字」で表示した、「それが」と「そこが」と「こういう意味で」という肝心なところの意味がよく分かりませんが、「こういう意味で」といういうのは、「これから研究するのは、『社会の表面』に現れる世界」を研究するという意味で、ということを不破さんは言いたかったんだろうと思います。
これらを踏まえて、不破さんは、第三部の主題は「総資本の諸姿容」だと言います。
「資本主義的生産の総過程」とは
マルクスが第一巻初版への「序言」で述べている資本主義的生産の「総過程の諸姿容」という言葉のなかの「資本主義的生産の総過程」とはどんな意味なのでしょうか。それを探るために、ちょっと長くなりますが、第三部の冒頭の文章を全文抜粋してみましょう。不破さんが一部抜粋した文章は非常に理解しづらい訳なので、その部分を含め「大月版」を抜粋します。
「第一部では、それ自体として見られた資本主義的生産過程が直接的生産過程として示している諸現象が研究されたのであって、この直接的生産過程ではそれにとって外的な諸事情からの二次的な影響はすべてまだ無視されていたのである。しかし、このような直接的生産過程で資本の生涯は終わるのではない。それは現実の世界では流通過程によって補われるのであって、この流通過程は第二部の研究対象だった。第二部では、ことに第三篇で、社会的再生産過程の媒介としての流通過程の考察にさいして、資本主義的生産過程を全体として見ればそれは生産過程と流通過程との統一だということが明らかになった。この第三部で行われることは、この統一について一般的な反省を試みることではありえない。【そこでなされなければならないのは、むしろ、全体として見た資本の運動過程から出てくる具体的な諸形態を見いだして叙述することである。現実に運動している諸資本は具体的な諸形態で相対しているのであって、この具体的な形態にとっては直接的生産過程にある資本の姿も流通過程にある資本の姿もただ特殊な諸契機として現れるにすぎないのである。だから、われわれがこの第三部で展開するような資本のいろいろな姿は、社会の表面でいろいろな資本の相互作用としての競争のなかに現われ生産当事者自身の日常の意識に現れるときの資本の形態に、一歩ごとに近づいて行くのである。】」なお、不破さんが一部抜粋した文章とは、上記の文章の【】内の文章のことです。そして、「この色」で表示した文字は、本文中では傍点をふって表記されています。
上記の文章を読み、不破さんの言っていることと比べてみて下さい。
不破さんは、第三部の冒頭の文章で、資本主義的生産の「総過程について『一般的反省』をおこなうことは、第三部の課題ではないとの断り書きまで書きそえています」と言っていますが、それは、まったくの読み間違えか、曲解です。
まず、ここでマルクスが「第三部」について言っているのは、「第三部で行われることは」、資本主義的生産過程が生産過程と流通過程との統一だということについの「一般的な反省を試みることではありえない」といってるのであって、「資本主義的生産の総過程」について述べているのではありません。マルクスが「資本主義的生産の総過程」について述べているのは、これに続く、不破さんが抜粋した文章の冒頭にある「そこでなされなければならないのは、むしろ、全体として見た資本の運動過程から出てくる具体的な諸形態を見いだして叙述することである。」という文章のなかでです。つまり、マルクスがこで言っている「全体として見た資本の運動過程」とは、「資本主義的生産の総過程」のことです。だから、「生産過程」と「流通過程」と「全体として見た資本の運動過程」に傍点がふってあり、だから、エンゲルスも「第三部」のタイトルを「資本主義的生産の総過程」とし、『資本論』のタイトルが「第一部 資本の生産過程」、「第二部 資本の流通過程」、「第三部 資本主義的生産の総過程」となっているのです。
そして、すでに、ホームページ「エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説②「『資本論』第二部を読む」を検証する。」(当該ページのPDFの4ページ参照)で紹介し、このページの後半の〈『資本論』の成立過程の概略〉の〈項〉(PDFの40ページを参照)でも紹介している「マルクスが1858~1862年頃からあたためていた「経済学批判」の構成プラン」の中の『資本論』の守備範囲に該当する部分の執筆プランが「資本の生産過程」、「資本の流通過程」及び「両過程の統一 または資本と利潤 利子」となっていることからも、「第一部」を「資本の生産過程」、「第二部」を「資本の流通過程」とし、「第三部」を「両過程の統一」、つまり、「資本主義的生産の総過程」というタイトルにすることは、妥当なことであると思われます。
そして、マルクスは『資本論』の「第三部」を、「諸姿容」だけでなく、つまり、「三つの階級の、すなわち資本家、土地所有者および賃労働者の経済的な諸関連を暴」くだけでなく、「資本主義的生産様式の『解体』を、ブルジョア社会の克服にまでいたるべき階級闘争として論じる」ことを思い描いていたのです。
「抜粋」でマルクスが述べていること
不破さんは、『資本論』から「抜粋」した【】内の文章から、「第三部」で「これから研究するのは、『社会の表面』に現れる世界」で、「常識的な社会の見方そのものだ」とマルクスがいっていると言います。確かに「第三部」の研究対象は「『社会の表面』に現れる世界」です。しかし、残念ながら、不破さんの頭にはそれだけしかないから、マルクスが標題を「総過程の諸姿容」としているのに、「『社会の表面』に現れる世界」しか視野に入れることができず、「主題は『総資本の諸姿容』」だという「資本主義的生産の総過程」抜きの間抜けなテーマになってしまうのでしょう。
もう一度、不破さんが「抜粋」した【】内の文章を、必要な補足をして、見てみましょう。
【「第三部」で論究されなければならないのは、「全体として見た資本の運動過程から出てくる具体的な諸形態を見いだして(科学的に──青山補筆)叙述すること」である。「現実に運動している諸資本は具体的な諸形態」として存在するのだから、「この具体的な形態(をとる資本=「現実に運動している諸資本」──青山補筆)にとっては直接的生産過程にある資本の姿も流通過程にある資本の姿も」ただ、資本が現実に運動するうえでの「特殊な諸契機として現れるにすぎないのである。だから、われわれがこの第三部で展開する(剰余価値の利潤への、商品資本の商品取引資本への、貨幣資本の貨幣取引資本への転化等の──青山補筆)ような資本のいろいろな姿は、社会の表面でいろいろな資本の相互作用としての競争(それは各個の資本家に資本主義的生産様式の内在的な諸法則を外的な強制法則として押しつけ、資本家に自分の資本を維持するために絶えずそれを拡大することを強制するところの競争──青山補筆)のなかに現われ(るときの資本の形態に、つまり──青山補筆)生産当事者自身の日常の意識に現れるときの資本の形態に、一歩ごとに近づいて行くのである。」】
ここでマルクスが言っているのは、「これから研究するのは、『社会の表面』に現れる世界」で、「『社会の表面』に現れる世界」は「常識的な社会の見方そのものだ」などという分かりきったことを小難しい言葉を使っていっているのではありません。
マルクスは、まず、「第三部」での論究のテーマは、全体として見た資本の運動過程から出てくる具体的な諸形態を見いだして科学的に叙述することだと言います。そして、この「具体的な諸形態」は、社会の表面での資本の相互作用としての競争によって「直接的生産過程にある資本の姿も流通過程にある資本の姿も」覆い隠された「資本の形態」であり、生産当事者自身の日常の意識に現れるときの資本の形態である、ということを言っています。そして、その「競争」こそが、各個の資本家に資本主義的生産様式の内在的な諸法則を外的な強制法則として押しつけ、資本家に自分の資本を維持するために絶えずそれを拡大することを強制するものであることを忘れてはなりません。
このようにマルクスは、「『社会の表面』に現れる世界」は「常識的な社会の見方そのものだ」などという分かりきったことを小難しい言葉を使っていっているのではなく、資本主義的生産様式における「資本主義的生産の総過程」=「全体として見た資本の運動過程」の仕組みを説明しているのです。
もっとも、資本主義的生産様式の社会の「競争」の意味も分からず、エンゲルスは「競争が悪の根源だという結論を引き出した」などというトンチンカンな暴言を平然という不破さんですから、この程度の解説しかできないのはやむを得ないことなのでしょう。
なお、不破さんに、「競争」にはいろんな意味があり、そんな限定は認めないなどとだだをこねられては困るのですが、ここでマルクスが述べている「競争のなかに現われるときの資本の形態」というフレーズの中の「競争」とは、「補筆」で示したように「産業上(生産活動上)の競いあいではなくて商業上の競いあい」のことで、「競争のなかに現われるときの資本の形態」とは、その競争が各個の資本家に「資本主義的生産様式の内在的な諸法則」を「外的な強制法則」として押しつけるときの「資本の形態」のことです。
※不破さんの、エンゲルスは「競争が悪の根源だという結論を引き出した」と言う暴言の詳しい説明は、ホームページ4-10「☆不破さんの、エンゲルスは『競争が悪の根源だという結論を引き出した』、『剰余価値の搾取を抜きにした資本主義論を展開した』と言う暴言」を、是非、参照して下さい。
〈参考〉「競争は各個の資本家に資本主義的生産様式の内在的な諸法則を外的な強制法則として押しつける」
「資本家は、ただ人格化された資本であるかぎりでのみ、一つの歴史的な価値とあの歴史的な存在権…をもっているのである。……価値増殖の狂信者として、彼は容赦なく人類に生産のための生産を強制し、したがってまた社会的生産諸力の発展を強制し、そしてまた、各個人の十分な自由な発展を根本原理とするより高い社会形態の唯一の現実に基礎となりうる物質的生産条件の創造を強制する。……このようなものとして、彼は貨幣蓄蔵者と同様に絶対的な致富欲をもっている。だが、貨幣蓄蔵者の場合に個人的な熱中として現れるものは、資本家の場合には社会的機構の作用なのであって、この機構のなかでは彼は一つの動輪でしかないのである。……そして、競争は各個の資本家に資本主義的生産様式の内在的な諸法則を外的な強制法則として押しつける。競争は資本家に自分の資本を維持するために絶えずそれを拡大することを強制するのであり、また彼はただ累進的な蓄積によってのみそれを拡大することができるのである。」(大月版『資本論』② P771-772 )。(上記の文章は、ホームページ「温故知新」→「1マルクス・エンゲルスの大事な発見」→「D、資本主義社会Ⅱ」の「14、競争と競いあい」14-4にあります。)
これらを踏まえ、『資本論』第三部のテーマについて
これまで見てきたように、不破さんの、「第三部で研究するのは、私たちがこれまで第一部、第二部で研究してきた世界とは、次元の違う世界なのです」と言う主張、これまで研究してきたのは「資本主義社会の本質的、内面的な世界」で、「これから研究するのは、『社会の表面』に現れる世界」だと言い、だからマルクスは「第三部の内容の核心を示すものとして、『諸姿容』の語を押し出したのでした」のであり、第三部の主題は「総資本の諸姿容」だと言いう主張は、正しくありませんでした。
不破さんは、『資本論』を勘違いしており、「第三部」の研究対象は分かっていたが、内容の核心(主題)が何かは分かっていなかった。
マルクスが草稿を書き、エンゲルスが編集した『資本論』は、「第一部」では、「生産過程」が研究されて、資本の源泉、富の源泉とその生産過程が解明され、「第二部」では、「流通過程」が研究されて、生産過程でつくられた富(資本)の実現の条件と資本主義的生産様式が成立する条件等が明らかにされ、「第三部」では、「全体として見た資本の運動過程」が研究されて、富が分配されるメカニズムが明らかにされます。
マルクスは、第三部の冒頭の文章でそのこと(『資本論』全体の構想)を述べ、「第三部」で行われることは、「全体として見た資本の運動過程から出てくる具体的な諸形態を見いだして(科学的に──青山補筆)叙述すること」だ、と明確に述べています。
『資本論』の「第三部」の「内容の核心」、「主題」は、「『社会の表面』に現れる世界」での資本主義的生産の「総過程の諸姿容」を究明し、「本質と直接的な現象との、問題を孕んだ関連を矛盾なく説明すること、運動法則それ自体を暴くばかりでなく、同じくこの法則の貫徹メカニズムを証明すること」であり、「資本主義的生産の総過程」を通じて富が分配されるメカニズムを明らかにして、資本主義を余すところなく暴露することです。単に、「『社会の表面』に現れる世界」での「総資本の諸姿容」を見たままに述べることではありません。
不破さんは、「マルクスの目」を持つことを自任し、『前衛』2015年5月号では、〝社会変革の主体的条件を探究する〟と言いながら、日本の経済と社会を根本から壊している「産業の空洞化」には目もくれず、資本主義的生産様式のもとでの「社会的バリケード」の必要性と「賃金が上がれば経済はよくなる」という「健全で「単純な」(!)常識の騎士たち」の見地を唱えるだけで、日本の危機の原因から党員の目を逸らせ、「この危機的な世界で、社会変革が、現実に、いつどこで、どういう形態で起こるかの予測はできません」と、自ら「社会変革の客観的条件」などまったく探究できないことを、胸をはって、告白しています。
そんな不破さんだから、現代のグローバル資本の「資本主義的生産の総過程」の諸姿容を正しく見ることができず、「総資本」の「諸姿容」がつくり出した「非正規雇用」や「内部留保」などの「現象」の断面しか見ることができません。だから、「社会的バリケード」を築けば労働者は守られ、「賃金が上がれば経済はよくなる」と思い込んでいる。そんな不破さんだからこそ、『資本論』第三部を科学的社会主義の観点から読むことができず、マルクスが「第三部」を資本主義的生産の「総過程の諸姿容」といっているのにエンゲルスが「資本主義的生産の総過程」と変えてしまったのは、「第三部全体の趣旨を誤解させることで、残念な訂正だったと思います」などと、冒頭からエンゲルスを誹謗・中傷する始末です。マルクスもとんでもない人に見込まれたもので、「『恐慌=革命』説」の濡れ衣といい、災難としか言いようがない。
ちょっと先回りして、もう少し「第三部」の内容を見てみましょう
不破さんの「『資本論』第三部を読む」が、エンゲルスが「第三部全体の趣旨を誤解させる」ことになったという異例の展開で始まったので、ちょっと先廻りすることになりますが、「第三部全体の趣旨」とは何か、「第三部」はどのような「場」なのかをマルクスが私たちにはっきりと示そうとした、資本主義社会の常識である「三位一体的定式」について、述べられているところを見てみましょう。
〈魔法にかけられ転倒され逆立ちした世界、古典派ブルジョア経済学の功績と限界、俗流経済学と経済的三位一体と支配的諸階級の階級的利益〉
「資本─利潤、またはより適切には資本─利子、土地─地代、労働─労賃では、すなわち価値および富一般の諸成分とその諸源泉との関係としてのこの経済的三位一体では、資本主義的生産様式の神秘化、社会的諸関係の物化、物質的生産諸関係とその歴史的社会的規定性との直接的合生が完成されている。それは魔法にかけられ転倒され逆立ちした世界であって、そこではムッシュー・ル・カピタルとマダム・ラ・テル〔資本氏と土地夫人〕が社会的な登場人物として、また同時に直接にはただの物として、怪しい振舞をするのである。このようなまちがった外観と偽瞞、このような、富のいろいろな社会的要素の相互間の独立化と骨化、このような、物の人格化と生産関係の物化、このような日常生活の宗教、およそこのようなものを解消させたということは、古典派経済学の大きな功績である。というのは、古典派経済学は、利子を利潤の一部分に還元し、地代を平均利潤を超える超過分に還元して、この両方が剰余価値で落ち合うようにしているからであり、また、流通過程を諸形態の単なる変態として示し、そして最後に直接的生産過程で商品の価値と剰余価値とを労働に還元しているからである。それにもかかわらず、古典派経済学の代弁者たちの最良のものでさえも、ブルジョア的立場からはやむをえないことながら、自分たちが批判的に解消させた外観の世界にやはりまだ多かれ少なかれとらわれており、したがって、みな多かれ少なかれ不徹底や中途はんぱや解決できない矛盾におちいっている。これにたいして、他方では、現実の生産当事者たちがこの資本─利子、土地─地代、労働─労賃という疎外された不合理な形態ではまったくわが家にいるような心安さをおぼえるのも、やはり当然のことである。なぜならば、まさにこれこそは、彼らがそのなかで動きまわっており毎日かかわりあっている外観の姿なのだからである。したがってまた、同様に当然なこととして、俗流経済学、すなわち、現実の生産当事者たちの日常観念の教師的な多かれ少なかれ教義的な翻訳以外のなにものでもなくて、これらの観念のうちにいくらか条理のありそうな秩序をもちこんでくる俗流経済学は、まさにこの、いっさいの内的関連の消し去られている三位一体のうちに、自分の浅はかな尊大さの自然的な、いっさいの疑惑を越えた基礎を見いだすのである。この定式は同時に支配的諸階級の利益にも一致している。なぜならば、それは支配的諸階級の収入源泉の自然必然性と永遠の正当化理由とを宣言してそれを一つの教条にまで高めるものだからである。
生産関係の物化の叙述や生産関係の独立化の叙述では、われわれは、……立ち入らない。なぜ立ち入らないかといえば、競争の現実の運動はわれわれの計画の範囲外にあるものであって、われわれはただ資本主義的生産様式の内的編制を、いわばその理想的平均において、示しさえすればよいのだからである。
以前のいろいろな社会形態では、この経済的神秘化は、ただ、おもに貨幣と利子生み資本とに関連してはいってくるだけである。それは次のような場合には当然排除されている。第一には、使用価値のための、直接的自己需要のための、生産が優勢な場合である。第二には、古代や中世でのように奴隷制や農奴制が社会的生産の広い基礎をなしている場合である。この場合には生産者にたいする生産条件の支配は、支配・隷属関係によって隠されていて、この支配・隷属関係が生産過程の直接的発条として現れており、目に見えている。自然発生的な共産主義が行われている原始的共同体のなかでは、また古代の都市共同体のなかでさえも、その諸条件を含めてのこの共同体そのものが生産の基礎として現われ、また共同体の再生産が生産の最終目的として現われる。中世の同職組合制度にあってさえも、資本も労働も無拘束なものとしては現われないで、それらの相互の関係は、組合制度やそれと関連する諸関係やまたこの諸関係に対応する職業上の義務や親方資格などの諸観念によって規定されたものとして現われる。資本主義的生産様式においてはじめて(ここで原稿は中断している。)」〈『資本論』第3巻 第2分冊、大月版⑤ P1063F8-1065B1〉
中断した原稿の内容について、青山は要旨次のようなものであろうと推測しています。①資本主義的生産様式においてはじめて経済的三位一体が完成したこと。②資本主義的生産様式においてはじめて資本も労働も社会から無拘束なものとして現われたこと。③その結果、資本主義的生産様式は(資本主義)社会そのものを掘り崩す矛盾を抱えていること。 そして、青山は、グローバル資本主義のもとで、「資本も労働も社会から無拘束なものとして」完全に解き放たれ、産業の空洞化によって、日本社会そのものが存亡の危機に直面していることを強く意識するものです。しかし、不破さんの主張の息の根を止めるためにも、ここで原稿が中断されているのが残念でしかたありません。(上記の文章は、ホームページ「温故知新」→「1マルクス・エンゲルスの大事な発見」→「C、資本主義社会Ⅰ」の「9、資本主義社会での事物の認識」の「9-4 」にあります。)
「第三部」は、「総過程の諸姿容」として、このように「魔法にかけられ転倒され逆立ちした世界」の、真の姿を余すところなく暴露する「場」として設定されました。不破さんは、ほんとうに、科学的社会主義の思想の持ち主であるならば、そのことを「第三部」の解説の「はじめに」の部分で、はっきりと言うべきなのです。しかし、不破さんの口からでた言葉は、「第三部で研究するのは、私たちがこれまで第一部、第二部で研究してきた世界とは、次元の違う世界なのです」という、「第三部」の意義をまったく理解していない言葉だけでした。
これでは、科学的社会主義を学ぼうと思って不破さんの本を買った人たちが、あまりにも可哀想でなりません。

先入見を植えつける
つぎに、不破さんは、「本文に入る前に、のべておきたいことがあります。」と言って、「第三部草稿」が「未完稿の形のままで残された」という特徴を述べたあと、マルクスのエンゲルスへの手紙で、「第一篇」と「第二篇」とが内容をかなり詳しく紹介しているのにたいし、「第三篇」の内容が簡潔である点をあげて、「このことは、第三篇について、マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいたことを示すものですが、その意味は、第三篇を読むところで説明することにします」と言います。
わざわざ「本文に入る前に、のべておきたいこと」と言い、「『第三篇』の内容が簡潔である」ということから不破さん得意の「推測」をして、「力」余って「断定」までした上で、「その意味は、第三篇を読むところで説明することにします」と言うのです。先入見を植えつけるだけの、「第三篇を読むところ」でのお楽しみという、なんとも不破さんらしい、不破さんが創作した『資本論』の「歴史的」読み方へのプロローグの文章です。
不破さんに先入見を植えつけられないために、不破さんが「第三篇を読むところで」した「その意味」の説明を前もって行うと、「『第三篇』の内容が簡潔である」ということから「推測」したということ以外の「意味」などないという、実にばかばかしい内容です。
私たちは、次のページ、〈『第三篇』の意味をまったく理解できない不破さん〉の〈項〉で、その「実にばかばかしい内容」を知ることになるが、不破さんがこの「推測」に使った「『第三篇』の内容が簡潔である」という事実が、これまでの不破さんの言動と「矛盾」することになるということは、すでに〈ちょっとわき道に(2)〉(PDFの7ページ参照)のところで見たとおりです。
以上が、不破さんの「第三部」の「はじめに」の部分、「(1)第三部の研究対象は何か──『日常の意識』のなかの世界に近づく」という「節」で、不破さんが、第三部の内容をまったく理解していないことを示したことについての検証です。
「(2)一般的利潤率と市場価格」について
「(2)一般的利潤率と市場価格」という「節」については、めずらしく、歪曲等がなく、安心して読んでいただけます。
「第三篇」の意味をまったく理解できない不破さん
不破さんの「私だけの勝手な結論」ではない驚きの理由
つぎの「(3)利潤率の傾向的低下の問題をめぐって」という「節」も、ますます、不破さんらしさが全面的に出ているところです。
不破さんは、第三篇について、最初の「第一三章」は、「マルクスの最大の経済学的発見を記録した輝かしい章」、最後の「第一五章」は、ここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」、中間の「第一四章」は、「第一五章の準備のため」の章で、「不要になった章」、だと言います。マルクスとエンゲルスがこの言葉を聞いたら、草葉の陰で頭を抱えてしまうことでしょう。
そして、「これは、私だけの勝手な結論ではありません」と言います。
不破さんは、このページの冒頭で見たとおり、マルクスの日本についての知識の広さの源泉を、たまたま自分が読んだ、オールコックの著書という「狭い知識」に求め、大恥をかいてしまいましたが、今度は十分に調べて、MEGA編集者たちの大部分も不破さんと同じ見解なので、自信をもって、「私だけの勝手な結論ではありません」と断言したのかなと思い、世界の科学的社会主義の「古典」の研究者たちに失望しかけましたが、不破さんの続きの文章を読んで安心しました。
不破さんは、「はじめに」の部分で、マルクスのエンゲルスへの手紙で、「第一篇」、「第二篇」が内容をかなり詳しく紹介しているのにたいし、「第三篇」が簡潔である点をあげて、「このことは、第三篇について、マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいたことを示すものですが、その意味は、第三篇を読むところで説明することにします」と述べていました。しかし、不破さんの「第三篇を読む」ところを読んでみると、上記のように「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」という不破さんの「推測」が、「勝手な結論」でない理由らしきものとして、不破さんが挙げたのは、またしても同じ手紙の同じ理由でした。鳩に豆鉄砲というか、唖然とするしかありません。
不破さんらしさを味わってもらうために抜粋します。
「そこ(手紙のこと──青山)では、第三部について、第一篇、第二篇は全体の内容を説明していましたが、第三篇だけは、第一章(第一三章の誤植──青山)部分、つまりこれまで誰も発見できなかった利潤率の傾向的低下の法則を解明した自分の『勝利』を宣伝しただけで、そのあとの部分については、一言も語らなかったのです。
この篇は、そういう意味で、篇の構成そのものが、大きな理論的転換の前夜の所産という様相を帯びていました。」
つまり、「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」という不破さんの「推測」が、「勝手な結論」でない理由は、マルクスが「利潤率の傾向的低下の法則を解明した自分の『勝利』を宣伝しただけ」で「そのあとの部分については、一言も語らなかった」だからだと言うのです。恐れ入りました。なお、不破さんが「一言も語らなかった」というのは真っ赤なウソです。『資本論』は「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味の重要性をしっかりと解明し、その機能の影響のもとでの産業循環の姿を解明しています。
マルクスが無二の友であるエンゲルスに出した真摯な私信の内容を、「自分の『勝利』を宣伝した」などと言うのも、自己顕示欲の強い不破さんならではの表現で、〝さすがは不破さん〟と思いますが、ここで分かったことが、二つあります。
一つは、不破さんは、「はじめに」の部分の文章で「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいたことを示すものです」と言って、読者に「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」かのように刷り込んで、「内容を大きく変える」「その意味」の「説明」を「第三篇を読むところでする」と読者に思い込ませたが、不破さんの「説明」は、「その内容を大きく変える」「その意味」の「説明」などではなく、「この篇は、そういう意味で、篇の構成そのものが、大きな理論的転換の前夜の所産という様相を帯びていました」という、「その内容を大きく変えるつもり」=「大きな理論的転換の前夜の所産という様相」という同義反復をすることによって、読者を催眠状態にして、刷り込んだ自分の考えに引き込むためのテクニックだったのです。確かに、「その意味」と「そういう意味」という「ワード」は似ていますが、読者は「とんち教室」に来ているのではありません。
もう一つ分かったことは、不破さんの「勝手な結論」でない、とんでもない、理由です。これまで見てきたように、その根拠となるものはマルクスとエンゲルスの手紙以外にありません。私は先に、不破さんが「第三篇について、マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいたことを示すものです」と断定したとき、「不破さん得意の「推測」から、「力」余って「断定」までした」と述べましたが、ここにきて、この表現が間違いであることに気づきました。不破さんは、最初から、「断定」していたんです。だから、不破さんの「結論」を支持するのはMEGA編集者たちなどである必要はありません。「マルクス自身がその内容を大きく変えるつもりでいた」のですから、不破さんの「結論」を支持するのは「マルクス」だと言うわけです。だから、不破さんの「勝手な結論」でない根拠となるものは、マルクスとエンゲルスの手紙で十分だというのでしょう。
もう、不破さんの「理屈」にかなう者は不破さん以外いません。参りました。白旗です。

「第一三章」の解説のはずが、反共文筆家なみのマルクスの歪曲
「第一三章」のテーマ:「この法則そのもの」に触れない不破さん
つぎに、不破さんは、「まず第一三章です。」として、第一三章の「解説」に移ります。
不破さんは、マルクスが「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味を説明している、「一般的利潤率の累進的な低下の傾向は、労働の社会的生産力の累進的発展を表わす、資本主義的生産様式に特有な表現にほかならない」(茶色の文字は『資本論』では傍点で表記されている──青山)とい文章を抜粋して、「この簡単なことが、これまでなぜわからなかったのか。」と言って「これまでの経済学」が「この法則を発見する」ことができなかった理由を『資本論』に則って説明します。しかし、ここは、まだ、「この簡単なことが、これまでなぜわからなかったのか」などと言って、その理由を説明する場ではありません。不破さんは、もっと大事な、「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味を、きちんと、説明しなければならない場面なのです。だからマルクスは、読者にその意味を理解してもらうために、不破さんが「抜粋」した文章に続けて、「それは、資本主義的生産様式が進展するうちに剰余価値の一般的平均率は低下する一般的利潤率に表されざるをえないということを、資本主義的生産様式の本質から一つの自明な必然性として示しているのである。」(大月版④P267)と、事実をねじ曲げて「自分の『勝利』を宣伝」する不破さんとは違って、「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味を、しっかりと、述べています。つまり、資本主義的生産様式のもとで、労働の社会的生産力が累進的に発展すればするほど、一般的利潤率の累進的な低下が起こるという、資本主義的生産様式のもつ内的な矛盾を明らかにしたのが、「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味なのです。ここが肝心な点なのです。この法則のもつこの矛盾を「軸」にして資本主義的生産様式を見ていくのが、「第一五章」です。
そして、これから始まる不破さんのマルクス批判の展開を踏まえて、先回りして言うと、「第一五章」の「肝(きも)」、マルクスが『資本論』の第三篇を通じて読者に理解してもらいたかったことは、「利潤率の傾向的低下の法則」の発見によって、「資本主義的生産様式は生産力の発展に関して富の生産そのものとはなんの関係もない制限を見いだ」し、「この特有な制限は、資本主義的生産様式の被制限性とその単に歴史的な一時的な性格とを証明するのである。それはまた、資本主義的生産様式が富の生産のための絶対的な生産様式ではなくて、むしろある段階では富のそれ以上の発展と衝突するようになるということを証明するのである。」(同上P304)ということです。
この「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味を理解できず、不破さんは、「第一五章」に、勝手に、「『恐慌の必然性』の証明」というターゲットを創作して、それを「マルクスが第一五章で自ら課した課題」ででもあるかにようにげっち上げ、「失敗した」(P37)と、マルクスを誹謗します。
みなさんは、是非、この肝心な点を忘れず、このページを読み進んで下さい。
アダム・スミス以来の全経済学者が発見できないことを発見したことを自慢するためにマルクスは『資本論』の第三篇を書いたのでもないし、「自分の『勝利』を宣伝」するために無二の友であるエンゲルスに手紙を書いたのではありません。不破さんは、自分の尺度でマルクスやエンゲルスやレーニンを測ってはなりません。彼らは、そんな卑しい精神など持ち合わせていないのですから。
「まず第一三章です。」という書き出しではじまった不破さんの「第一三章」の「解説」は、「スミスもリカードゥも、剰余価値を利潤と区別してとらえること」(「剰余価値の発見」──青山)ができなかったから「この簡単なことが、これまで」わからなかったという、身も蓋もない終わりかたをして、不破さんの「主題」である、マルクスへの誹謗がはじまります。
「第一三章」の解説のはずが、反共文筆家なみのマルクスの歪曲
不破さんは、「第一三章」の解説のはずの「項」で、「第一三章」の解説はそっちのけで、いきなり、マルクスを誹謗し科学的社会主義の思想の価値を低めるめに、自ら創作した「恐慌=革命」説の根拠となる、「利潤率の傾向的低下の法則」→「恐慌」→「資本の強力的な転覆」という、不破さん得意の「三段飛び論法」を、マルクスの1857年以来の『経済学批判』の草稿を「拠りどころ」として展開しまいます。そして、「三段飛び論法」の「刷り込み」だけならまだしも、『経済学批判』のための荒削りの草案である『61-63年草稿』を持ち出して、反共文筆家なみのマルクスの歪曲をおこないます。
不破さんは、マルクスが『57-58年草稿』以来、「利潤率の低下の法則が資本主義的生産様式の危機を引き起こす根源をなす」という見解を持っており、「この法則が、恐慌という破局とその反復」をもたらし、「そしてそれが『最後には、資本の強力的な転覆』をもたらすことを断言した」と言います。そして、不破さんは、マルクスが『資本論』の「第一五章」でこの「三段飛び論法」を証明しようとして「失敗」したと言います。不破さんは、そう言うのであれば、少なくとも、マルクスが「第一五章」でこの「三段飛び論法」を提起したことを示さなければなりません。しかし、後で見るように、不破さんが「第一五章」の解説で、「マルクスが第一五章で自らに課した課題は、第一三章で証明した利潤率の傾向的低下が資本主義的生産様式を必然的没落に導くことの証明でした。」(P35)と架空の「課題」を課した「第一五章」の中で述べられていることは、「証明」などする必要のない〝事実〟とその延長線上にある〝展望〟を記した文章でした。
だから、不破さんが自分の主張を「刷り込む」ためには、場違いだろうが、この「第一三章」で「三段飛び論法」を披露する以外、手は、なかったのです。
まずはじめに、不破さんの「三段飛び論法」がいかにマルクスを歪曲しているか、具体的に見てみましょう。
不破さんは、マルクスが「利潤率の低下の法則が資本主義的生産様式の危機を引き起こす根源をなす」という見解を持っていたと言い、「この法則が、恐慌という破局とその反復」をもたらすと、マルクスが、あたかも、「利潤率の低下の法則」が「根源」としてストレートに「利潤率の低下の法則」=「恐慌という破局とその反復」という図式を描いていたかのように言い、マルクスの考えを歪曲します。このようにマルクスの考えを歪曲し、短絡的な図式による攻撃で「利潤率の傾向的低下の法則」を葬り去り、資本主義的生産様式の真の姿を見えなくして、「資本」のもつ限界とその資本の蓄積によって発展する「資本主義的生産様式」の社会の限界を見えなくする反科学的社会主義攻撃=「反共」攻撃を、前「共産党」の委員長の不破さんが率先して行っていることをマルクスが知ったら、さぞがっかりすることでしょう。なぜなら、マルクスは、『資本論』の「第一三章」、「第一四章」、「第一五章」は「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味・意義を余すところなく説明し、不破さんのような短絡的な思考を排して、二一世紀に生きる思想を、私たちに提供してくれているからです。「不破さんだけの勝手な結論」を信じる前に、是非、「第一三章」、「第一四章」、「第一五章」をしっかり読んで下さい。
マルクスは、「利潤率の低下の法則」が「根源」としてストレートに「利潤率の低下の法則」=「恐慌という破局とその反復」という図式など描いていません。マルクスが指摘しているのは、そして真の科学的社会主義の思想が明らかにしたのは、①「利潤率の傾向的低下の法則」が資本主義的生産様式の社会の限界を明らかにしたこと、②資本の唯一の動機は「資本蓄積」であるが「利潤率の傾向的低下の法則」がその阻害要因となり、資本はその障害を克服するために「利潤量」を増やすための生産拡大と「利潤率の低下」を防ぐための様々な手を尽くすが、それが「過剰生産や投機や恐慌を促進し、過剰人口と同時に現れる過剰資本を促進」(大月版P304)し、資本の過多により「利潤率の低下が利潤量によって埋め合わされない」状況が産業循環の熱狂の真っただ中で起こること。その影響をはじめに受け、最も強く受ける「より小さな分散した諸資本の大群はわれ先に冒険(それは、?利潤率の低下を一層の量の拡大で補おうとし?その結果、泥沼の安売り合戦がはじまり?遂には、資金ショートを原価以下の販売で補おうとする冒険──青山補筆)への道へ駆り立てられる。このために恐慌へと追い込まれる。」(P34、読みにくいので原文中にあった〔〕をはずしました。)。その結果、恐慌により資本の減価が行われ、資本の過多は一時的に解消されるが、より高い生産性のもとでの新たな「資本主義的生産様式の社会の危機」と「資本主義的生産様式の社会の克服の条件」の形成がはじまる、という当時の産業循環の姿を明らかにしたことの二点です。
そして、マルクスとエンゲルスは、当時の政治経済情勢の下で、「恐慌が政治的変革の最も強力な槓杆のひとつである」と考え、革命のために心血を注ぎましたが、「恐慌」だけが「最後には、資本の強力的な転覆」をもたらすと「断言した」ことなどありませんでした。
さて次に、『61-63年草稿』を持ち出しての不破さんの反共文筆家なみのマルクスの歪曲について見てみましょう。
不破さんは、『61-63年草稿』の「より小さな分散した諸資本の大群はわれ先に冒険〔の道へ駆り立てられる〕。このために恐慌〔へと追い込まれる〕。」という文章を持ち出して、「この論によると、恐慌の原因は、もっぱら『より小さな分散した諸資本』の冒険的な行動にあって、資本主義経済の主力をなす大資本とは無関係であり、資本主義的生産様式の運命を小資本が握っているということになります。」と、勝手に、「この論」なるデタラメな濡れぎぬをマルクスにきせておいて、続けて「おそらくマルクス自身も、これを恐慌問題の本格的解決だとする確信はなかった、と思います。」(P34-35)などと、一人相撲を取ります。なお。不破さんは、『前衛』の2015年1月号でも、マルクスが「経済恐慌やバブル現象まで、すべて小資本の冒険がなせる業で、大資本には責任がない」と述べていると言っています。
しかし、マルクスが指摘し、真の科学的社会主義の思想が明らかにしたのは、前述のとおり、②で概略示した内容であり、小資本は「経済恐慌」の渦に真っ先に巻き込まれるということです。
そしてここでも不破さんのご都合主義がみごとに発揮されます。不破さんは、33ページでは、マルクスが「利潤率の低下の法則が資本主義的生産様式の危機を引き起こす根源」でこの法則が恐慌をもたらすといっていたと言ったと思ったら、今度は、34ページでは、「恐慌の原因」は、もっぱら「小資本の冒険がなせる業」だとマルクスがいっていると言うのです。このように、文章の流れの中で臨機応変に言うことが変わるのが不破さんの「論理展開」の大きな特徴ですが、マルクスの文章を継ぎ接ぎして自分の誤った「推論」を押し通そうとする不破さんの「論理展開」は、エンゲルスが序文で述べている、「科学的な問題に携わろうとする人は、なによりもまず、自分が利用しようとする書物をその著者が書いたとおりに読むことを、またことに、そこに書いてないことを読み込まないようにすることを、学ばなければならないのである」という科学的社会主義者の基本精神を逸脱した、失格者の「論理展開」です。
不破さんは自分で誤った「問題」を創作し、間違った結論を引き出しておいて、それをこともあろうに、「おそらくマルクス自身も、これを恐慌問題の本格的解決だとする確信はなかった、と思います」などと言ってのけるのです。もう、呆れるばかりです。
※なお、私が、①マルクスとエンゲルスは、「恐慌」だけが「最後には、資本の強力的な転覆」をもたらすと「断言した」ことなどありませんと述べた点と②マルクスは「恐慌の原因」がもっぱら「小資本の冒険がなせる業」だと言っていると不破さんが言っている点についての詳しい説明は、ホームページ4-19「☆不破さんは、マルクスが1865年に革命観・資本主義観の大転換をしたという、レーニンも気づかなかった大発見を、21世紀になっておこない、マルクスの経済学をだいなしにしてしまった。」を、是非、参照して下さい。
不破さんは、ここから一足飛びに「第一五章」の歪曲に移りますが、「第一五章」の内容を正しく理解するためにも、『資本論』の「第三篇」全体をつかむためにも重要であり、その内容は「第一五章」に直結するものなので、不破さんがほとんど触れなかった「第一三章」とまったく触れていない「第一四章」の内容で、留意しておきたい点について、ごく簡単に触れてみたいと思います。
「第一三章」で述べている、もう一つの重要な点
「利潤率の傾向的低下の法則」発見の意義──資本主義的生産様式のもとで、労働の社会的生産力が累進的に発展すればするほど、一般的利潤率の累進的な低下が起こるという、資本主義的生産様式のもつ内的な矛盾を明らかにしたこと──についてはすでに触れたので、「第一三章」で、関連して述べられている、もう一つの重要な点について、ごく簡単に触れてみたいと思います。
マルクスは、「利潤率の進行的低下にもかかわらず」、利潤の絶対量を増大させることができ、ただそれができるだけではなく、「資本主義的生産の基礎の上ではそうならなければならないのである。」(同上P273)として、資本主義的生産様式のもとでは「利潤率の進行的低下」を補うために一層の生産拡大が必要であることを述べています。
この指摘は、70年代以降の日本経済の姿を見るうえで大変大切なものです。
日本は、70年代以降、「利潤率の進行的低下」を補い一層の資本蓄積を図るために海外への資本輸出・直接投資を官民一体となって推進し、その結果、「産業の空洞化」が進み、「資本主義的生産・蓄積の発展の歩みは、労働過程の規模とともにその広がりがますます大きくなることを必然にし、またそれに対応して各個の経営のための資本前貸が増大することを必然にする。それゆえ、諸資本の集積の増大は、資本主義的生産・蓄積の物質的条件の一つでもあれば、またこの生産・蓄積そのものによって生産された結果の一つでもある。」(同上P275)という、資本主義的生産様式がもつ「健全」な姿さえ失われてしまいました。
「産業の空洞化」によって、「絶対的に増大した可変資本を、より高度な構成すなわち不変資本のより以上の相対的増加のもとで充用するためには、総資本が構成の高度化に比例して増大するだけではなく、それよりももっと急速に増大しなければならない。その結果として、資本主義的生産様式が発展すればするほど、同じ労働力を使用するためにもますます大きな、そして増大する労働力を使用するためにはなおさら大きな資本量が必要になるということになる。」(同上P280)という資本主義的生産様式がもつ「健全」な姿が維持できなくなり、労働力「需給」が資本優位になった結果、不安定雇用が急速に拡大していったのです。
このように、私たちが『資本論』を読む場合、日本と世界の〝いま〟を常に頭に入れて考えることが大切です。
そして資本は、「利潤率の傾向的低下の法則」との不断のたたかいを、常に、強いられているのです。不破さんは、その意味をしっかりつかみ、現代を熟考すべきです。
「第一四章」は、現代に多くのことを語りかけている
「第一四章 反対に作用する諸原因」は、まず最初に、なぜ「利潤率の傾向的低下の法則」と呼ぶかについて、「この一般的法則に単に一つの傾向でしかないという性格を与えている」から、「一般的利潤率の低下を傾向的低下と呼んできたのである。」(大月版P291)と述べ、以下で、資本の「利潤率の傾向的低下の法則」との不断のたたかいの「方法」を示し、私たち労働者階級への「低賃金」と「労働強化」とが、資本が「利潤率の傾向的低下の法則」を緩和するための主要な手段であることを明らかにします。
このように、「第一四章」は、「低賃金」と「労働強化」なしには「利潤率の低下」は進み、資本はその存在価値をますます低くしていくということ、「資本」と「労働者階級の低賃金と労働強化」とはメタルの裏表であることを示していますが、この「章」を、「利潤率の傾向的低下が資本主義的生産様式を必然的没落に導くことの証明」を「課題」とした「第一五章の準備のために必要」な「章」で「不要になった章と位置づけることができます」などと言う不破さんの「勝手な結論(決めつけ──青山)」とは、まったく違う内容のものです。
「第一四章」は、「利潤率の低下」に反対に作用する諸原因として①「労働日の延長と労働の強化」とによる「労働の搾取度の増強」②「労働力の価値以下への労賃の引下げ」③「不変資本の諸要素の低廉化」④「相対的過剰人口」の存在。日本では「産業の空洞化」により、「相対的過剰人口」が形成され、臨時工とサービス業への労働力のシフトが強制された。⑤「貿易」による安い商品の輸入。⑥「株式資本の増加」を挙げています。
そしてマルクスは、「利潤率の傾向的低下は、剰余価値率つまり労働の搾取度の傾向的上昇と結びついているのである。それゆえ、利潤率の低下は労賃率の上昇から起きると説明することは、例外的にはそういうこともあるにしても、このうえもなくばかげたことである。」(大月版P301)と述べていますが、数年前に「洛陽の紙価を高めた」トマ・ピケティの『21世紀の資本論』の資本収益率(r)>経済成長率(g)は、「剰余価値率つまり労働の搾取度の傾向的上昇」を実証した、マルクスの正しさを証明するものでした。この事実は、資本家階級との思想闘争をするうえで重要です。
「第一四章」で触れられなかったことと、「現代の資本と世界市場」
なお、ここで触れられなかったことのひとつに不変資本の稼働時間の延長の問題があります。不変資本をフル稼働させて24時間稼働させ、労働者を8時間の3交代にした場合、「利潤率の低下」は防げませんが利潤量は3倍となります。そして、不変資本の稼働期間が約1/3に短縮されることにより、同等の性能のより安価な製造装置の導入か同一価格のより生産性の高い不変資本の導入が可能となります。これも、「利潤率の低下」に反対に作用する諸原因の一つと言えるでしょう。
また、「貿易」に関しては、当時と現代とでは「国家」と「資本」との関係が大きく変化しているので、「現代の資本と世界市場」について、簡単に触れてみたいと思います。
マルクスは「貿易と世界市場」について、つぎのように述べています。
「貿易の拡大も、資本主義的生産様式の幼年期にはその基礎だったとはいえ、それが進むにつれて、この生産様式の内的必然性によって、すなわち不断に拡大される市場へのこの生産様式の欲求によって、この生産様式自身の産物になったのである。」(大月版P298)
このようにして発展してきた「世界市場」は、資本主義的発展の伸びしろがますます小さくなる先進資本主義諸国と資本主義的発展の大きな伸びしろをもった新興諸国とを生み出します。「利潤率の傾向的低下の法則」との不断のたたかいを強いられている資本は、先進資本主義諸国から生産条件の劣っている新興諸国へのグローバル展開への道を、「新自由主義思想」とともに、本格的に歩み始めます。グローバル資本は母国の産業を空洞化することによって、一面では、自らを育てた出身国を棄てざるをえません。しかし同時に、技術が遅れた国々での先行者利得を固定化して収奪を続けるためにも、自らを守るためにも、自らを育てた出身国等の先進資本主義国に頼らざるをえません。そんな中で、日米欧の先進資本主義諸国はグローバル資本に有利な経済ルールを世界に押しつけることを共通目標として協調関係を保ってきました。そんな中で、「産業の空洞化」の被害者である白人労働者層の支持をうけて2017年1月20日登場した米国トランプ政権は、「アメリカファースト」を掲げ、「産業の空洞化」を推進してきた米国企業には目をつむり、貿易の不均衡の解消による雇用増での「白人労働者層の支持」の維持と先進資本主義諸国への米国のより多くの経済的利益の要求と米国の経済優位を脅かしかねない中国の技術開発の抑制と「グローバル資本に有利な経済ルール」の再構築をめざして、世界に圧力をかけ続けてています。
これが、今日の「貿易と世界市場」についての、現代のグローバル資本とそれを支える諸国家の最新の動向です。不破さんの「共産党」は、なぜ、トランプが大統領に当選できたのかを知るべきです。
このように、「第一四章 反対に作用する諸原因」は、現代に多くのことを語りかけており、不破さんのように「不要になった章と位置づけることができます」などと言うことはできません。

不破さんは、自分が理解できないものを「理論上の錯覚」と言う
不破さんは、「第一五章 この法則の内的な諸矛盾の展開」のテーマを、「マルクスが第一五章で自らに課した課題は、第一三章で証明した利潤率の傾向的低下が資本主義的生産様式を必然的没落に導くことの証明でした。」と言い、続けて、「そのカギは、それが恐慌の必然性の根拠となることの立証にありました。」(P35)と述べて、「立証すべき命題」なる文章を第一五章から抜粋します。なお、すでに述べたとおり、「第一三章」のテーマは「利潤率の傾向的低下」を証明することなどではありません。
私は、〈「第一三章」の解説のはずが、反共文筆家なみのマルクスの歪曲〉という〈項〉で、不破さんが、マルクスは「利潤率の低下の法則が資本主義的生産様式の危機を引き起こす根源をなす」という見解を持っており、「この法則が、恐慌という破局とその反復」をもたらし、「そしてそれが『最後には、資本の強力的な転覆』をもたらすことを断言した」と言って、自ら創作した「恐慌=革命」説の根拠となる、「利潤率の傾向的低下の法則」→「恐慌」→「資本の強力的な転覆」という、不破さん得意の「三段飛び論法」を展開したとき、不破さんが「第一五章」の解説でマルクスが「立証すべき命題」として示したという第一五章の文章は、「立証」などを目的としていない、〝事実〟とその延長線上の〝展望=当然の帰結〟を述べた文章であることを指摘しました。
そして私は、〈「第一三章」のテーマ:「この法則そのもの」に触れない不破さん〉という〈項〉で、資本主義的生産様式のもとで、労働の社会的生産力が累進的に発展すればするほど、一般的利潤率の累進的な低下が起こるという、「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ矛盾を「軸」にして資本主義的生産様式を見ていくのが、「第一五章」であることを述べました。
不破さんが、マルクスが「立証すべき命題」としていたとして抜粋した文章は、つぎのとおりですが、その前後の文章を合わせて読むと、「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味をよく現す文章となっています。
不破さんが抜粋したのは、「(他方、──青山補筆)総資本の増殖率すなわち利潤率が資本主義的生産の刺激であるかぎりでは(資本の増殖は資本主義的生産の唯一の目的なのだから)、利潤率の低下は新たな独立資本の形成を緩慢にし、したがって資本主義的生産過程の発展を脅かすものとして現われる。それは過剰生産や投機や恐慌を促進し、過剰人口と同時に現れる過剰資本を促進する」(大月版P304)という文章で、私が補筆した「他方、」は、前に書かれている文章を受けてのものです。
この「他方、」以下の文章の前には、「利潤率の低下と加速的蓄積とは、両方とも生産力の発展を表しているかぎりでは、同じ過程の別々の表現でしかない」こと、そして、「利潤率の低下はまた、小資本家たちからの収奪によって、また最後に残った直接生産者たちからもまだなにか取り上げるものがあればそれを取り上げることによって、資本の蓄積と集中とを促進する」(同上P303-304)ことが述べられており、続けて、「他方、」として、前掲の不破さんが抜粋した文章がつづきます。
そして、前掲の不破さんが抜粋した文章に続くのが、〈「第一三章」のテーマ「この法則そのもの」に触れない不破さん〉で、「第一五章」の「肝(きも)」、マルクスが『資本論』の第三篇を通じて読者に理解してもらいたかったこととして紹介した、「利潤率の傾向的低下の法則」の発見によって、「資本主義的生産様式は生産力の発展に関して富の生産そのものとはなんの関係もない制限を見いだ」し、「この特有な制限は、資本主義的生産様式の被制限性とその単に歴史的な一時的な性格とを証明するのである。それはまた、資本主義的生産様式が富の生産のための絶対的な生産様式ではなくて、むしろある段階では富のそれ以上の発展と衝突するようになるということを証明するのである。」(同上P304)という文章です。
私は、〈「第一三章」の解説のはずが、反共文筆家なみのマルクスの歪曲〉の〈項〉の中で、マルクスは、「利潤率の低下の法則」がストレートに「根源」となって、「利潤率の低下の法則」=「恐慌という破局とその反復」という図式など描いていないことを述べ、マルクスが明らかにしたのは、①「利潤率の傾向的低下の法則」が資本主義的生産様式の社会の限界を明らかにしたこと、②資本の唯一の動機は「資本蓄積」であるが「利潤率の傾向的低下の法則」がその阻害要因となり、資本はその障害を克服するために「利潤量」を増やすための生産拡大と「利潤率の低下」を防ぐための様々な手を尽くすが、それが「過剰生産や投機や恐慌を促進し、過剰人口と同時に現れる過剰資本を促進」し、資本の過多により「利潤率の低下が利潤量によって埋め合わされない」状況が産業循環の熱狂の真っただ中で起こること。その影響をはじめに受け、最も強く受ける「より小さな分散した諸資本の大群はわれ先に冒険(それは、?利潤率の低下を一層の量の拡大で補おうとし?その結果、泥沼の安売り合戦がはじまり?遂には、資金ショートを原価以下の販売で補おうとする冒険への道へ駆り立てられること。このために恐慌へと追い込まれることを明らかにし。その結果、恐慌により資本の減価が行われ、資本の過多は一時的に解消されるが、より高い生産性のもとでの新たな「資本主義的生産様式の社会の危機」と「資本主義的生産様式の社会の克服の条件」の形成がはじまる、という当時の産業循環の姿を解明したことの二点であることを述べました。
この「不破さんが抜粋した文章」を挟んでの一連の文章は、続けて読めばわかるとおり、「利潤率の傾向的低下の法則」がもたらす〝事実〟とその延長線上の〝展望=当然の帰結〟を述べ、「利潤率の傾向的低下の法則」が資本主義的生産様式の社会の限界を明らかにしたことを述べたもので、不破さんの言うような「立証すべき命題」を提起したものなどではありません。
不破さんは、このような「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味をまったく理解できず、「第一五章」に、勝手に、「『恐慌の必然性』の証明」というテーマつけて、それを「マルクスが第一五章で自ら課した課題」ででもあるかにようにげっち上げ、「『恐慌の必然性』の証明」をしていないから「失敗した」(P37)と言って、マルクスを誹謗するのです。
そして、不破さんは、自分が理解できないものを「理論上の錯覚」などと言うのですから、困ったものです。不破さんは、大月版「第一五章」のP304、P324、P325に出てくるリカードらの「利潤率の低下」にたいする恐怖、不安について、マルクスが「実は、なにかもっと深いものが根底にあるのであるが、彼(リカードのこと──青山)はそれを予感するだけである」述べていることについて、次のような、とんでもない解説をします。
「しかし、リカードゥらが利潤率低下現象のうちに見た不安は、根底にある『もっと深いもの』の予感ではなく、理論上の錯覚でした。
マルクス自身も、さまざまな角度からの探究をくりかえしたものの、納得のゆく解答を得ることができず、決定的な結論を得ないまま、この章を閉じざるを得なかったのでした。」などといい、「恐慌現象を利潤率低下の法則に結びつけることには失敗した」と言います。
ペテン師としての不破さんの、面目躍如というところでしょうか。
不破さんは、「リカードゥらが利潤率低下現象のうちに見た不安は、」「理論上の錯覚で」、「根底にある『もっと深いもの』」などないといって、リカードゥらが「理論上の錯覚」をしているかのように言いますが、ご覧のとおり、「実は、なにかもっと深いものが根底にある」と言っているのはマルクスです。だから、「なにかもっと深いものが根底にある」というのが「理論上の錯覚」だというのなら、ただ「理論上の錯覚」などといって誹謗・中傷するのでなく、マルクスが言っている、「資本主義的生産の制限、その相対性、すなわち、それがけっして絶対的な生産様式ではなくただ物質的生産条件のある局限された発展期に対応する一つの歴史的な生産様式でしかない」(大月版P325)という唯物史観のどこに「理論上の錯覚」があるのか、明らかにすべきなのです。ヤクザが因縁をつけるようなやり方は、絶対に、やめるべきです。
そして、不破さんは、「マルクス自身も、さまざまな角度からの探究をくりかえしたものの、納得のゆく解答を得ることができず、決定的な結論を得ないまま、この章を閉じざるを得なかったのでした」と言いますが、マルクスは、「第一五章」に「『恐慌の必然性』の証明」というテーマつけて、それを「マルクスが第一五章で自ら課した課題」になどしていません。だから、そのために「さまざまな角度からの探究をくりかえした」りなどするわけがありません。「第一五章」に、勝手に、「『恐慌の必然性』の証明」というテーマつけて、それを「マルクスが第一五章で自ら課した課題」だなどと言っているのは、不破さんだけです。そもそも、マルクスの「第一五章」でのテーマは、「利潤率の傾向的低下の法則」の「内的な諸矛盾の展開」を述べることです。不破さんは、「『恐慌の必然性』の証明」という架空のターゲットを、勝手に、設定して、マルクスがそのターゲットを撃ち落とさなかったといって非難するのです。このホームページを読み進んでいただければわかりますが、「自ら課した課題」について、「さまざまな角度からの探究をくりかえしたものの、納得のゆく解答を得ることができず、決定的な結論を得ないまま、」「不本意な結果におわ」ってしまったのは、不破さんの方です。
不破さんは、第三篇の解説の冒頭で、「第一五章」について、ここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」だと言いましたが、「第一五章」の解説のなかで、不破さんは、どこが「展開した理論の主要部分」であり、それがどのように誤っており、「以後の草稿で」どのように「取り消した」のか、一言も「解説」してくれません。このような根拠を示さない誹謗・中傷は許されるものではありません。
マルクスが「利潤率の傾向的低下の法則」→「恐慌」→「資本の強力的な転覆」という単純な図式を考えていたという、不破さんの「推測」を善意に捉えるとすれば、不破さんは、産業循環の諸要因を含む資本主義的生産様式の社会の全運動などお構いなしに、恐慌の原因は架空の需要にあるという「恐慌の運動論」を二一世紀になって発見したという「頭脳」の持ち主ですから、やむを得ないことと観念すべきことで、私のように憤慨すべきことではないのかもしれません。
厚顔無恥、『資本論』を読んでいない人に白を黒と思わせる
「第一五章」について、ここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」だといい、「利潤率の傾向的低下の法則」による「『恐慌の必然性』の証明」のための章だと言う不破さんは、「第一五章」の第一節と第二節の中の二つの文章(大月版P307とP313-314)をあげて、「どちらも利潤率の傾向的低下とは問題意識を異にする」、「いまでも、『恐慌の根拠』についてのマルクスの定式として、非常に重視されているものです。」と言います。
この不破さんの言い分は、形式的にも矛盾しています。この二つの文章が「いまでも、『恐慌の根拠』についてのマルクスの定式として、非常に重視されているもの」だとすれば、それは、「第一五章」で「展開した理論の主要部分」ではないのか。そしてそれは、取り消されるべきものではないのか。不破さんはどのようにつじつまを合わせようというのでしょうか。
そしてこの不破さんの言い分は、内容的に誤っています。不破さんは、これら二つの文章が「どちらも利潤率の傾向的低下とは問題意識を異にする」と言いますが、「どちらも利潤率の傾向的低下の法則」の「内的な諸矛盾の展開」のなかで、「利潤率の傾向的低下」のもとでの資本主義的生産様式の矛盾を明らかにしたもので、具体的にこれら二つの文章をみれば、「問題意識を異にする」などと、逆立ちしても、言えません。そもそも「第一の文章」は、不破さんが、マルクスが「立証すべき命題」としていたと偽って抜粋した文章の後半部分をより詳しく述べた文章の一部です。だから、不破さんの「主張」は根本的に間違っており、「捏造」とさえいえるものです。「解説は抜きにして」などと言わずに、不破さんは真摯な気持ち、真摯な態度で「解説」すべきです。それが、『資本論』解説者の義務です。
「解説は抜きにして」不破さんが挙げた「第一の文章」は、不払労働を自分のものにする直接的生産過程──それは、「利潤率の低下に表される過程の発展につれて、このようにして生産される剰余価値の量は巨大なものにふくれ上がる」(大月版P306)──について述べ、そのように生産された総生産物はすべて売れなければならないが、まったく売れない場合等があることを述べた文章につづく文章として書かれたものです。
その概略は、以下のとおりです。
前の文章を引き継いで、マルクスは、前述の直接的生産過程における「搾取の条件」は「ただ社会の生産力によって制限されているだけ」だが、「搾取の実現の条件」は①「敵対的な分配関係を基礎とする消費力によって規定される」(社会の大衆の消費が最低限に引き下げられる)ことと、②資本の「蓄積への欲求によって、」「制限されている」ことを述べ、「これこそは資本主義的生産にとっての法則」だと言います。そして「この法則」は、利潤率の傾向的低下のもとで、「生産方法そのものの不断の革命、つねにこれと結びついている既存資本の減価、一般的な競争戦」による利潤率の傾向的低下への反作用や「ただ存続するだけの手段として生産を改良し生産規模を拡大することの必要」等のなかで貫かれていく。だから、「市場は絶えず拡大されなければならない」。その結果、市場はますます「生産者たち(主として労働者階級のこと──青山)からは独立な自然法則の姿をとるようになり、ますます制御できないものになる」。このように、「内的な矛盾が生産の外的な場面の拡大によって解決を求めるのである」が、このように「生産力が発展すればするほど、ますますそれは消費関係が立脚する狭い基礎と矛盾してくる。」
ここまでが、不破さんが抜粋した「第一の文章」です。これらの文章と連続する次の文章を合わせたものが、不破さんが、マルクスが「立証すべき命題」としていたと偽って抜粋した文章の後半部分である、「それは、過剰生産、投機、恐慌、過剰人口と並存する過剰資本を促進する。」という言葉の内容をより詳しく述べた文章となるのです。
マルクスは、不破さんが抜粋した「第一の文章」に続けて、「このような矛盾に満ちた基礎の上では、資本の過剰が人口過剰の増大と結びついているということは、けっして矛盾ではないのである。なぜならば、この両方をいっしょにすれば、生産される剰余価値の量は増大するであろうとはいえ、まさにそれとともに、この剰余価値が生産される諸条件とそれが実現される諸条件とのあいだの矛盾は増大するのだからである。」という文章を書いています。
これらの文章は、「利潤率の低下に表される過程の発展につれて、このようにして生産される剰余価値の量は巨大なものにふくれ上がる」その過程と「搾取の実現の条件」とを述べ、「市場は絶えず拡大されなければならない」こと、その中で「資本の過剰が人口過剰の増大と結びついて」発展し、「過剰生産や投機や恐慌を促進」することを、不破さんが、マルクスが「立証すべき命題」としていたと偽って抜粋した文章より詳しく述べたものです。
若干、不破さんの謬論からそれますが、「利潤率の傾向的低下の法則」と切っても切れない関係にある「資本の過剰」という言葉が出てきたので、簡単に説明します。
まず、先ほど私が補足した文章に、「資本の過剰が人口過剰の増大と結びついているということは、けっして矛盾ではない」というフレーズがありますが、このことをより詳しく述べた文章が少し先にありますので、紹介します。
「資本の過剰生産というのは、資本として機能できる、すなわち与えられた搾取度での労働の搾取に充用できる生産手段──労働手段および生活手段──の過剰生産以外のなにものでもない。与えられた搾取度でというのは、この搾取度が一定の点より下に下がるということは、資本主義的生産過程の攪乱や停滞、恐慌や資本の破壊をひき起こすからである。このような資本の過剰生産が多少とも大きな相対的過剰人口を伴うということは、けっして矛盾ではない。」(大月版P320-321) これに続く文章も、是非、お読み下さい。
そして、「資本の過多」という言葉の意味について、マルクスは「いわゆる資本の過多(プレトラ──青山)は、つねに根本的には、利潤率の低下が利潤の量によって償われない資本──そして新たに形成される資本の若枝はつねにこれである──の過多に、または、このようなそれ自身で独自の行動をする能力のない資本を大きな事業部門の指導者たちに信用の形で用だてる過多に、関連している。」(大月版P314-315)と述べていますが、「いわゆる資本のプレトラ」とは、「利潤率の低下が利潤量によって埋め合わされない資本のプレトラ」と理解しておいて下さい。
これらも頭に入れて、不破さんが抜粋した「第二の文章」を見てみましょう。ただし、不破さんが抜粋した文章は、「訳」が非常に分かりにくいので、大月版の『資本論』の「訳文」に沿って見ることにします。
なお、不破さんが抜粋した「第二の文章」の前には、「利潤率が低下すると同時に諸資本の量は増大し、またこれに伴って既存資本の減価が進み、この減価は利潤率の低下を妨げて資本価値の蓄積に促進的な刺激を与える。」(大月版P312)という「利潤率の低下と既存資本の減価の影響」についての記述がありますが、「資本主義的生産の真の制限は、資本そのものである」というときの「資本」とはこのような特質をもつ「資本のプレトラ」を内包した「資本」であることをしっかり頭に入れて読んで下さい。そうしないと、「第二の文章」の意味をより深く捉えることができません。
不破さんが、ここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」だと言う「第一五章」で、マルクスが述べていることを聞いてみよう。
「資本主義的生産の真の制限は、(利潤率の傾向的低下のもとで、「資本のプレトラ」の脅威にさらされている──青山補筆)資本そのものである。」つまり、「生産はただ資本のための生産」であり、生産手段は「社会のために生産過程を絶えず拡大形成していくための」手段ではないということである。「生産者大衆の収奪と貧困化とにもとづく資本価値の維持と増殖とはただこのような(=「生産はただ資本のための生産」という──青山)制限のなかでのみ運動することができるのであるが、ここような(=「生産はただ資本のための生産」という──青山)制限は、資本が自分の目的のために充用せざるをえない生産方法」──それは、「労働の社会的生産力の無条件的発展に向かって突進する生産方法」であるが──と「絶えず矛盾することになる。手段──社会的生産力の無条件的発展──は、既存資本の増殖という制限された目的とは絶えず衝突せざるをえない。それだから、(利潤率の傾向的低下のもとで、「資本のプレトラ」の脅威にさらされている──青山補筆)資本主義的生産様式が、物質的生産力を発展させこれに対応する世界市場をつくりだすための歴史的手段だとすれば、それはまた同時に、このようなその歴史的任務とこれに対応する(利潤率の傾向的低下のもとで、「資本のプレトラ」の脅威にさらされている──青山補筆)社会的生産関係(=「資本主義的生産関係」のこと──青山)とのあいだの恒常的矛盾なのである。」
まさにこの文章は、「第一五章 この法則の内的な諸矛盾の展開」のなかの、「利潤率の傾向的低下の法則」の「内的な諸矛盾の展開」のなかで述べられているのです。
このように、不破さんが「いまでも、『恐慌の根拠』についてのマルクスの定式として、非常に重視されているも」として「第一五章」の第一節と第二節の中から抜粋した「二つの文章」は、「どちらも利潤率の傾向的低下とは問題意識を異にする」ものなどではなく、「利潤率の傾向的低下の法則」の「内的な諸矛盾の展開」の構成部分をなすものです。白を黒という、こういうのを「厚顔無恥」というのでしょうか。
なお、私は、不破さんが「不要になった章と位置づけ」た「第一四章」で、マルクスが「貿易と世界市場」について、「貿易の拡大も、資本主義的生産様式の幼年期にはその基礎だったとはいえ、それが進むにつれて、この生産様式の内的必然性によって、すなわち不断に拡大される市場へのこの生産様式の欲求によって、この生産様式自身の産物になったのである。」(大月版P298)と述べていることを紹介し、その現代的意義を申し上げましたので、ここでは、現在の日本とグローバル資本の関係については触れませんが、是非もう一度、この機会に考えて下さい。また、不破さんが、ここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」だと言うこの章には、もう一カ所「貿易と世界市場」について述べているところがあります。それは、「資本が外国に送られるとすれば、それは、資本が国内では絶対に使えないからではない。それは、資本が外国ではより高い利潤率で使えるからである。」(大月版P321)という文章です。この文章も合わせて、この機会に考えて下さい。
これまで、不破さんの「第一五章」の印象操作への反論の中で、「第一五章」の内容についてかなり触れてまいりましたが、この章が、不破さんに「取り消した章」などと言われているので、あらためて、「第一五章」の中の重要な文章について見てみたいと思います。

「第一五章」を「取り消し」たら、『資本論』は『資本論』ではなくなってしまう
少々長いですが①から⑧まであります。
①繰り返しになりますが、この章の一番重要な点は、〈「第一三章」のテーマ「この法則そのもの」に触れない不破さん〉で、「第一五章」の「肝(きも)」、マルクスが『資本論』の第三篇を通じて読者に理解してもらいたかったこととして紹介した、「利潤率の傾向的低下の法則」の発見によって、「資本主義的生産様式は生産力の発展に関して富の生産そのものとはなんの関係もない制限を見いだ」し、「この特有な制限は、資本主義的生産様式の被制限性とその単に歴史的な一時的な性格とを証明するのである。それはまた、資本主義的生産様式が富の生産のための絶対的な生産様式ではなくて、むしろある段階では富のそれ以上の発展と衝突するようになるということを証明するのである。」(同上P304)という文章です。
②資本の蓄積と集積について、「そしてここで最後に少数の手中への既存の諸資本の集中と多数の人々からの資本の取上げ(今では収奪はこのように姿を変える)として現れるのである。このような過程は、もしも求心力と並んで対抗的な諸傾向が絶えず繰り返し集中排除的に作用しないならば、やがて資本主義的生産を崩壊させてしまうであろう。」(大月版P309)という文章は「独禁法」の存在理由でもあります。そして、独占資本にとって中小企業は必要な存在であり、社会は中小企業が大企業になる夢を与え続ける必要があり、国の中小企業対策(中小企業への支援策)は「資本主義的生産を崩壊させ」ないための必要な施策なのです。
③「労働の社会的生産力の発展は二重に現れる。」第一に、蓄積されている生産資本の絶対量と生産力の大きさに、第二に、労賃に投ぜられる資本部分が総資本に比べて相対的に小さくなるということに現れる。「充用される労働力に関しても生産力の発展はやはり二重に現れる。」第一に、剰余労働の増大に、第二に、資本を動かす労働力の量(労働者数)の減少に現れる。(大月版P310)
④「資本主義的生産の真の制限は、資本そのものである。」(大月版P313)だから、「産業の空洞化」を資本にやめさせるためには、「資本」の「資本」としての機能を失わせさせなければならない。
⑤「いわゆる資本の過多は、つねに根本的には、利潤率の低下が利潤の量によって償われない資本の過多に関連している。」(大月版P314-315)、「資本が外国に送られるとすれば、それは、資本が国内では絶対に使えないからではない。それは、資本が外国ではより高い利潤率で使えるからである。」(大月版P321)とマルクスは言っているが、日本は「産業の空洞化」によって、資本が国内で使える場が少なくなっている。
「第一五章」を否定することは、科学的社会主義の経済学を否定すること
これから引用する「第一五章」の文章は、⑦で科学的社会主義の経済学の〝核心〟的理論を述べ、⑥で不破さんが二一世紀になって〝発見〟した「恐慌の運動論」から導き出される「架空の需要=恐慌」説と「賃金が上がれば経済は発展する」という資本主義発展論を見事に論破しています。不破さんは、だから、「第一五章」で「展開した理論の主要部分」のエッセンスであるはずのこれらの論点をさけ、「利潤率の傾向的低下の法則」の「内的な諸矛盾の展開」の構成部分をなす「二つの文章」を取りあげて、「どちらも利潤率の傾向的低下とは問題意識を異にする」ものなどといって、お茶を濁そうとしたのでしょう。これでは、『資本論』の解説者として、『資本論』の読者への裏切り行為といってもいいものです。
まず、⑥から、見てみましょう。
⑥「(商品の過剰生産について、──青山補足)もしも、一般的な過剰生産(資本の過剰生産のこと──青山)が生ずるのではなくていろいろな生産部門のなかでの不均衡が生ずるのだと言うならば、その意味は、資本主義的生産のなかでは個々の生産部門の均衡は不均衡からの不断の過程として現れるということ以外のなにものでもない。」(大月版P322)と述べて、「商品の過剰生産」は「資本の過剰生産」ではないとする「経済学者たち」を批判しています。不破さんは、自ら創作した「恐慌の運動論」から導き出される「架空の需要」が「恐慌」であるとして、「恐慌の運動論」なる一つの現象形態にしがみついて、「資本の過剰生産」という本質を忘れ去ります。その結果、不破さんは、リーマン・ショックについても、「架空の需要」が恐慌を生み出したこと、金融資産の規模が167兆ドルにのぼることを述べ、「この経済危機は、文字通り、『過剰生産恐慌と金融危機の結合』だったのです」と「架空の需要」にもとづく「過剰生産恐慌」、つまり、「商品の過剰生産」による〝危機の発現〟とみて、「現在の経済現象」をまったく理解できません。見る現象は違いますが、マルクスが批判した「経済学者たち」並みの理論水準です。※リーマン・ショックについての不破さんの考えについては、ホームページ4-19「☆不破さんは、マルクスが1865年に革命観・資本主義観の大転換をしたという、レーニンも気づかなかった大発見を、21世紀になっておこない、マルクスの経済学をだいなしにしてしまった。」を、参照して下さい。
そしてマルクスは続けて言う、「最後に、もしも、資本家たちはただ自分たちのあいだだけで商品を交換し合って消費してしまえばよいのだ、と言うのならば、それは、資本主義的生産の全性格を忘れているのであり、問題は資本の増殖であって資本の消費ではないのだということを忘れているのである。要するに、過剰生産という明白な現象にたいするいっさいの異論(こんな異論をこの現象は少しも気にかけない)が帰着するところは、資本主義的生産の制限はけっして生産一般の制限ではなく、したがってまたこの独自な生産様式、この資本主義的生産様式の制限でもないということである。とこが、この資本主義的生産様式の矛盾は、まさに、生産力の絶対的な発展へのこの生産様式の傾向にあるのであり、しかもこの発展は、資本がそのもとで運動しておりまたただそのもとでのみ運動できる独自な生産条件と絶えず衝突するのである。」(大月版P322-323)と。
もしも、不破さんが科学的社会主義の思想の正しさを確信しているのなら、不破さんは、「マルクス自身も、さまざまな角度からの探究をくりかえしたものの、納得のゆく解答を得ることができず、決定的な結論を得ないまま、この章を閉じざるを得なかったのでした」などと言うまえに、上記のマルクスの言葉を謙虚に聞き、熟考すべきでした。そうすれば、恥ずかしくて、「賃金が上がれば経済は発展する」という資本主義発展論など言えなくなり、⑦でマルクスが述べている科学的社会主義の経済学の〝核心〟的理論の意味も多少は理解できるようになったことでしょう。
⑦マルクスが述べている科学的社会主義の経済学の〝核心〟的理論。
「資本主義的生産様式の制限は次のような点に表れる。
(1)労働の生産力の発展は利潤率の低下ということのうちに一つの法則を生みだし、この法則は、生産力の発展がある点に達すればその発展に最も敵対的に対抗し、したがって絶えず恐慌によって克服されなければならないということ。
(2)不払労働の取得が、そして対象化された労働一般にたいするこの不払労働の割合が、または、資本主義的に表現すれば、利潤とこの利潤の充用資本にたいする割合とが、つまり利潤率のある高さが、生産の拡張や制限を決定するのであって、社会的欲望にたいする、社会的に発達した人間の欲望にたいする、生産の割合がそれを決定するのではないということ。それだからこそ、資本主義的生産様式にとっては、生産の拡張が他の前提のもとでは逆にまだまだ不十分だと思われるような程度に達しただけでも早くも制限が現われるのである。この生産様式は、欲望の充足が休止を命ずる点でではなく、利潤の生産と実現とが休止を命ずる点で休止してしまうのである。」(大月版P323-324)
これが、科学的社会主義の経済学の〝核心〟的理論である「資本主義的生産様式の制限」に関してマルクスが述べた言葉です。この認識と不破さんの「恐慌の運動論」とには、雲泥の差があります。マルクスは、資本主義的生産様式のもとでの「生産力の発展」が「恐慌」を生むと考えますが、不破さんは、「架空の需要」にもとづく「商品の過剰生産」が「恐慌」を生むと考えます。もしも、不破さんが、「恐慌」が「資本の過剰生産」の現れであることを認めるのであれば、不破さんは「資本の過多」による資本主義的生産様式の矛盾の深まりをも認めなければなりません。不破さんは、『資本論』第三部の第一五章を読めば誰でも目に入るこれらの文章の「解説」をいっさいせず、「第一五章」を「取り消した章」などと言って葬り去ろうとしますが、自分が論破できないからといって「葬り去ろう」とするのは、科学的社会主義の思想から最も離れた人がおこなう考えと行動です。
しかし、19世紀後半に生きたマルクスとエンゲルスが「恐慌が政治的変革の最も強力な槓杆」だというと、「恐慌=革命」説で間違いだといい、19世紀末から20世紀前半に活躍したレーニンの当時の「帝国主義」の捉え方に嘲笑をあびせ、その時々の資本の行動と国家の行動を見てその時々の最も適切な政策を判断することができない不破さんと、その仲間たちは、上記の文章の言葉尻をとらえて、マルクスは、「利潤率の傾向的低下の法則」が「生産力の発展がある点に達すればその発展に最も敵対的に対抗し」、利潤率の低下は、「絶えず恐慌によって克服されなければならない」ということを、述べているではないか、これは、「この法則が、恐慌という破局とその反復」をもたらすといっていることではないか、と鬼の首をでも取ったかのように言うかも知れません。しかし、待って下さい。マルクスは、同じ「第一五章」で「労働者の絶対数を減らすような、……(青山の略)生産力の発展は、革命をひき起こすであろう。」と述べ、生産力の発展による「労働者の過剰時間」が「資本主義的生産の独自な制限」としてあらわれ、資本主義的生産様式が生産力の発展の衝突するようになり、「部分的にはこの衝突は周期的な恐慌に現れるが、このような恐慌が起きるのは、労働者人口のあれこれの部分がこれまでどおりの就業様式では過剰になるということからである。」とも述べています。今度は、不破さんは、マルクスは「労働者の過剰時間が、恐慌という破局」をもたらすといったと言ってマルクスを責めるのでしょうか。
私たちは、不破さんの「恐慌の運動論」、「架空の需要=恐慌」論などに惑わされることなく、資本主義的生産様式における生産力の発展が、「利潤率の低下」をもたらし、「労働者の過剰時間」をもたらし、「資本の過多」をもたらし、資本主義的生産様式が「けっして絶対的な生産様式ではなくただ物質的生産条件のある局限された発展期に対応する一つの歴史的な生産様式でしかない」という科学的社会主義の〝資本主義没落〟論をしかりと学ばなければなりません。現代の日本が「産業の空洞化」を通じて、〝没落〟しつつある姿を示していることをしっかりと認識しなければなりません。
⑧不破さんの謬論に鉄槌を加える「第一五章」の結びの文章
不破さんは『前衛』2014年1月号で、エンゲルスが「生産の社会的性格と取得の資本主義的形態の矛盾」という形で資本主義の矛盾をとらえることは誤りだと、驚くべき発言をしています。この「第一五章」の結びの文章は、「資本主義的生産の三つの主要な事実」を述べた、『資本論』を通じてマルクス経済学を学ぶ上で大変大切な文章ですが、「生産の社会的性格と取得の資本主義的形態の矛盾」をマルクス自身が認めた内容を含むもので、不破さんにとっては「見たくもない」文章です。しかし、そこに書かれていることが自分の矮小な考えに合わないからといって、大切な文章の内容を読者に伝えようとしないのは、これもまた、『資本論』の解説者として、『資本論』の読者への裏切り行為といってもいいでしょう。
「第一五章」の結びの文章でマルクスは何を言っているのか、一緒に、見てみましょう。
「資本主義的生産の三つの主要な事実。
(1)少数の手のなかでの生産手段の集積。これによって、生産手段は直接的労働者の所有としては現われなくなり、反対に生産の社会的な力に転化する。たとえ最初は資本家の私的所有としてではあっても。資本家はブルジョア社会の受託者であるが、彼らはこの受託の全果実を取りこんでしまうのである。
(2)社会的労働としての労働そのものの組織。協業や分業によって、また労働と自然科学との結合によって。
どちらの面から見ても資本主義的生産様式は私的所有と私的労働とを廃棄する。たとえ対立的な諸形態においてではあっても。
(3)世界市場の形成。
資本主義的生産様式のなかで発展する、人口に比べての巨大な生産力、また、それと同じ割合でではないとはいえ、人口よりもずっと急速に増大する資本価値(単にその物質的基体だけではなく)の増大は、増大する富に比べてますます狭くなって行く基礎、つまりそのためにこの巨大な生産力が作用する基礎と矛盾し、また、この膨張する資本の増殖関係と矛盾する。そこで、恐慌が起きる。」
この文章の(1)と(2)は、先に触れた「生産の社会的性格と取得の資本主義的形態の矛盾」を述べたものです。※詳しくはホームページ4-9「☆不破さんは、「生産の社会的性格と取得の資本主義的形態の矛盾」という形で資本主義の矛盾をとらえることは誤りだと、マルクス・エンゲルス・レーニンを否定する。」を、是非、参照して下さい。
「(3)世界市場の形成。」の「世界市場」とは、資本主義的生産様式の基礎をなしその生活環境をなしている「場」です。だから、「世界市場」は、現代の「グローバル資本」の搾取と収奪の行動を基礎づける「場」となり、「グローバル資本」は自らの搾取と収奪に都合のいいルールを定め、それを国際標準として各国の人民に受け入れさせ、「技術」を囲い込むことによって世界全体の技術の進歩を遅らせ、人民と人民の矛盾と人民と資本の矛盾を「形成」する「場」として注視し、自国の変革と結びつけて「世界市場」の変革を追求しなければなりません。「(3)世界市場の形成。」というマルクスの言葉を現代と結びつけて深く考えることに大きな意味があると思います。
そして、「(3)世界市場の形成。」に続く文章は、『共産党宣言』(マルクス=エンゲルス)の中の「社会が自由にすることのできる生産諸力は、もはやブルジョア的文明およびブルジョア的所有関係の促進には役立たないのだ。反対に、生産諸力はこの関係にとってあまりに強大となってしまい、この関係によって阻止されるのだ。……──ブルジョア階級は恐慌を、何によって征服するか?一方では、一定量の生産諸力をむりに破壊することによって、他方では、新しい市場の獲得と古い市場のさらに徹底的な搾取によって。要するにどういうことか?要するに、もっと全面的な、もっと強大な恐慌の準備をするのである。そしてまた恐慌を予防する手段を減少させるのである。」(岩波文庫P46-48)という文章と対にして読むことを推奨したいと思います。※なお、「世界市場」についてのマルクス・エンゲルスの主なコメントについてはホームページ「5温故知新」→「1マルクス・エンゲルスの大事な発見」→「F、世界市場・恐慌」を、是非、参照して下さい。また、「資本主義的生産の三つの主要な事実」はホームページ「5温故知新」→「1マルクス・エンゲルスの大事な発見」→「C、資本主義社会Ⅰ」にPDFファイルとして保存してありますので、ご活用下さい。
以上、大変長くなってしまいましたが、マルクスは「第一五章」で、このように、「恐慌現象を利潤率低下の法則に」ストレートに「結びつけること」などしていませんが、資本主義的生産様式の社会における「利潤率の傾向的低下の法則」のもつ意味を捉えることに「失敗」などしていません。

不破さんは、マルクスの「経済学批判」から「資本論」への構想の発展を利用して、自説を読者に刷り込もうと無駄な努力を重ねる
不破さんは、わざわざ「『資本論』第三部の構想の歴史的な変化」というタイトルの「章」を立てて、「第二部第一草稿での恐慌の運動論の発見」──という不破さんの創作──が「『資本論』全体の構想プランの画期的な変化の出発点となりました」(P40)と言い、「第二部第一草稿での恐慌の運動論の発見以降は、構想全体にあった『資本一般』という枠組みそのものの再検討が必要になりました」(P43)と述べています。これは、あたかもマルクスが「恐慌の運動論」なるものを一八六五年の初めに「発見」し、その結果『資本論』全体の構想の再検討が必要になったかのように述べることによって、不破さんが創作した「恐慌の運動論」──不破さんは、「発見」したのはマルクスで、自分は「恐慌の運動論」と命名しただけだと、虎の威を借りようとしますが──なる産業循環の矮小化された「理論」を、あたかもマルクスが一八六五年の初めに「発見」したかのように読者に思い込ませようとするためです。しかし不破さんは、「第二部第一草稿での恐慌の運動論の発見」なるものが、なぜ、「構想全体にあった『資本一般』という枠組みそのものの再検討が必要にな」り、「『資本論』全体の構想の再検討」を必要とすることになったのかは、残念ながら、まったく語ってくれません。
「『資本論』の成立過程」の概略
私は、ホームページ〈エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説②「『資本論』第二部を読む」を検証する。〉の冒頭の〈不破さんらしい「第二部」の成立過程のスケッチ〉の〈項〉で、マルクスが第一部草案を書き終えたあと、1864年の夏頃から、「第3部」を第2章(この「章」は『資本論』の「篇」に該当する。)→第1章→第3章の順に書き、その後、1865年の前半に「第2部 資本の流通過程」の草案を書きはじめたことにかんして、不破さんがマルクスを誹謗・中傷したので、関連する『資本論』編纂に至る経緯をしめし、不破さんの誤りを指摘しました。
そのなかで、上記のような草稿の執筆過程は、不破さんがマルクスを誹謗しているように、マルクスが「第2部 資本の流通過程」に関する知識が乏しかったからではなく、「構想全体にあった『資本一般』という枠組みそのものの再検討が必要にな」り、「『資本論』全体の構想の再検討」が必要となった結果、必然的に行われたものであることを明らかにしました。
一部重複しますが、ここであらためて、「『資本論』の成立過程」の概略を示し、皆さんと認識を共有したいと思います。
「『資本論』の成立過程」の概略
「『剰余価値学説史』(1)」(大月版、1970年9月30日)の「ドイツ社会主義統一党中央委員会付属マルクス=レーニン主義研究所」の序文と大谷禎之介氏の「『マルクスの利子生み資本論』2」に収録されているMEGA第Ⅱ部門第4巻第2分冊の『資本論』第三部第1稿についての「解題」と「成立と来歴」とに依拠して、『資本論』の成立過程を概略します。
マルクスの『経済学批判』のプランは、「Ⅰ資本について」、「Ⅱ土地所有」、「Ⅲ賃労働」、「Ⅳ国家」、「Ⅴ外国貿易」および「Ⅵ世界市場」という執筆構想に基づき、「Ⅰ資本について」を「1資本一般」、「2競争」、「3信用」および「4株式資本」の四部構成とし、スタートの「1資本一般」は、「a商品」、「b貨幣」および「c資本」の三篇を設けるという設計で、1859年に刊行された「『経済学批判』第一冊」は「1資本一般」の「a商品」と「b貨幣」を扱っています。23冊のノートから成る「1861~1863年草稿」はその続編のための「草稿」です。
〈参考『経済学批判』のプラン(1858-1862年)〉
Ⅰ 資本について
1 資本一般
a 商 品
b 貨 幣
c 資 本
資本の生産過程
1 貨幣の資本への転化
2 絶対的剰余価値
3 相対的剰余価値
4 両者の組合せ
5 剰余価値に関する諸学説
資本の流通過程
両過程の統一 または資本と利潤 利子
2 競 争
3 信 用
4 株式資本
Ⅱ 土地所有
Ⅲ 賃労働
Ⅳ 国家
Ⅴ 外国貿易
Ⅵ 世界市場
「1861~1863年草稿」は「1資本一般」の「c資本」の構成要素である「資本の生産過程」、「資本の流通過程」および「両過程の統一または資本と利潤」というテーマを扱い、「剰余価値に関する諸学説」は「資本の生産過程」の歴史的補論として、1862年1月から1863年7月までの間に執筆されました。だから、マルクスは1863年にはまだ、歴史的-批判的資料である「剰余価値に関する諸学説」を「資本一般」に関する研究の理論的な諸篇に配分しようと思っていました。
しかし、「『剰余価値に関する諸学説』の仕事をしている間に、マルクスが研究した問題の範囲はますます大きく広がって行き、マルクスが最初はただ一つの章だけのために予定していたところの、(1)資本の生産過程、(2)資本の流通過程、(3)両過程の統一または資本と利潤、という区分が理論的な著作全体にたいしてもつ意義がますます明らかになり、この編成が非常に重要であり決定的であることが判明し、最初のプランでは独立の諸篇をなすはずたった諸論題(たとえば「諸資本の競争」、「信用」、「土地所有」)もしだいにこの編成のなかに含められるようになった。こうして、三つの理論的な部分がますます明瞭な輪郭を得てきて、経済学のすべての理論的な問題をそのなかに取り入れてくるにつれて、マルクスは、『剰余価値に関する諸学説』は一つの独立な部分をなし第4部として全著作の結びとなるべきだ、という確信をますます強固にしたのである。」(『剰余価値学説史』(1)」大月版P17-18)
同時にそのことは、「マルクスははじめ、『資本一般』と資本の『実在的な』運動──競争と信用──とを徹底して分離していたが、彼はこの分離をしだいに放棄した。『……要綱』(「経済学批判要綱」のこと──青山)のあと、そして『……諸学説』(「剰余価値学説史」のこと──青山)の執筆にかかる直前には、彼は〔『1861~1863年草稿』すなわち23冊のノートのなかの〕『最後のノート』のなかでまだ、剰余価値と利潤との区別は一つの転換ではなくて、二つの転換で示されるべきだと考えていた」が、「『……諸学説』のなかで、マルクスはこの方法を事実上廃棄した。研究の過程では有効だと認められてきたそのような切断のもつ諸限界が彼にわかってきたのであって、彼は、1862年12月のプラン草案が証明しているように、経済的諸関係の最も重要なもろもろの形態上の区別を資本関係の叙述のなかに取り入れようと考えたのである。それは『資本論』の第1部および第3部のための構成プランだったが、マルクスは、これらの部の執筆を進めるなかで、これらの構成プランにさらにもろもろの変更を加えていった。」(『マルクスの利子生み資本論』2P386-387) ※なお、「剰余価値に関する諸学説」は「草稿」としての完成度が高く、研究の過程とはことなる叙述の仕方が求められていました。
この、研究の過程とはことなる叙述の仕方は、「第1部」の執筆のあと「第2部」ではなく「第3部」を書いた理由にもつながっています。そのことについて、MEGAの「解題」は、次のように述べています。
「第1部から第3部に移ったことは、明らかに、マルクスが、本質と直接的な現象との、問題を孕んだ関連を矛盾なく説明すること、運動法則それ自体を暴くばかりでなく、同じくこの法則の貫徹メカニズムを証明することにも努めていたことに帰せられるべきものであった。彼の考えでは、理論全体の内的な一貫性はこのことにもとづいているのである。彼にとってまずもって肝心であったのは、問題の二律背反を明示的にはっきりさせ、科学的に批判的な解決を与えることであったが、最後には、体系的に論述することに重きが置かれていた。」(P389-390)と。
そして、第3部の執筆を中断し第2部の草案を書いた理由については、MEGAの「成立と来歴」は、「その理由はたぶん、『1861~1863年草稿』のノートⅩⅦでは利潤の平均利潤への転化がまだ包括的には仕上げられていなかったことにあったのであろう。……叙述の論理によって、結局マルクスは、当該の欠落部分を埋めることを、それゆえに第3部の執筆を中断してまず第2部を仕上げることを強制されたのである。」(P403-404)と述べています。
このように、「第1部」の執筆のあと「第2部」ではなく「第3部」の第2章(『資本論』では「章」は「篇」となっている)→第1章→第3章と書いた理由と、今度は第3部の執筆を中断し第2部の草案を書いた理由とは、基本的に同じものです。そして、1862年12月のプラン草案の「8)産業利潤と利子とへの利潤の分裂。商業資本。貨幣資本。」を『資本論』では「第4章」と「第5章」との二つの章に分割したことについて述べている次の文章もそのことをよくあらわしており、マルクスの「叙述の仕方の転換」によるものです。
「第2部の執筆からえられたもろもろの認識がすでにこの変更の根拠となっていたのかもしれない。剰余価値を生産する諸資本のあいだの競争戦のもろもろの基本的な法則性を論じている、草案の最初の三つの章(「章」は『資本論』の「篇」のこと──青山)を書いたのちに、マルクスが直面したのは、特殊的、派生的な資本諸形態の叙述は生産的資本の諸変態の叙述からどのようにして厳密に区切られるべきか、両者のあいだの諸移行は個々的にはどのような姿態をとるのか、という問題であった。この問題の解決は、資本の流通過程の分析を前提していた。最後に第3部で展開されているような諸資本の現実的運動を論じることができるようになる前に、まずもって、諸資本のそのような自立化の可能性が──つまり諸資本の形態的運動が──表現されなければならなかった。そのさいに、商人資本と利子生み資本とは二つの質的に異なる自立的な資本形態だ、という認識が固まったのであって、このことが、この両形態を別個に叙述することを要求したのである。」(P405)
これらの執筆の軌跡は、マルクスが研究した問題の範囲がますます大きく広がって行くにつれ、そして、研究が煮詰まって行くにつれて、マルクスは『剰余価値学説史』執筆前の研究の方法に基づく叙述の仕方から、本質と直接的な現象とのシームレスな貫徹メカニズムを示し、体系的に論述することに叙述の仕方を変えたことの現れでした。
ただし、私は上記の文章の最後のセンテンスには同意できません。マルクスは、当然、「商人資本と利子生み資本とは二つの質的に異なる自立的な資本形態だ」という「認識」は当然もっていたが、研究の段階では同じ「剰余価値」を源泉とする二種類の「資本」と見ることを優先し、研究段階から著作として『資本論』を世に出すにあたって、「質的に異なる自立」性を明確にした「章」立てにすることが、有効であり枝ぶりの良い作品になると考えたのだと思います。
「『資本論』の成立過程と構成」のより詳しい資料は、別添PDF「『資本論』の成立過程と構成」を参照して下さい。
上記の「別添PDF」ファイルは、こちら。
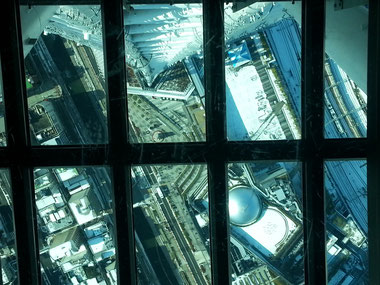
不破さんのつじつま合わせ
上記の〈「『資本論』の成立過程」の概略〉を見ていただければお分かりのとおり、構想全体にあった『資本一般』という枠組みそのものの再検討が必要にな」り、「『資本論』全体の構想の再検討」を必要とすることとなったのは、不破さんが言うような「第二部第一草稿での恐慌の運動論の発見」なるものなどではありません。マルクスは「剰余価値に関する諸学説」の執筆過程で、研究した問題の範囲がますます大きく広がって行くにつれ、そして、研究が煮詰まって行くにつれて、『剰余価値学説史』執筆前の研究の方法に基づく叙述の仕方から、本質と直接的な現象とのシームレスな貫徹メカニズムを示し、体系的に論述するという『資本論』の構想が固まってきたのです。
なお、不破さんは、マルクスが「『経済学批判』第一冊」の続編のなかの利潤に関する篇にその「例解」として「地代」の問題を入れようとしたことについて、「利潤の研究の一部のような顔をして」とか「マルクスが編み出した苦肉の策」とか言って、マルクスを不破さんと同様に次元の低い人間に見せようとしていますが、「利潤の研究」における「例解」として「地代」というアイデアは非常にいい考えで、『資本論』の構想が固まっていなかった1862年の段階では大正解だと思います。「地代」が「利潤の研究の一部のような顔をして」いるものなのか、みなさんは、是非、『資本論』の「第三部」を読んで下さい。
不破さんは、「1865年以後のプラン変更」という「項」で『資本論』の草稿が書かれた時期だけを取って、私が〈「『資本論』の成立過程」の概略〉で指摘した『資本論』の構想に必死でつじつま合わせしようとします。しかし、不破さんは、一向に、「第二部第一草稿での恐慌の運動論の発見」が「『資本論』全体の構想の再検討」を必要とすることとなったとする「主張」の根拠を示すことができません。唯一書かれているのは、1862年12月のプラン草案の「8)産業利潤と利子とへの利潤の分裂。商業資本。貨幣資本。」を『資本論』では二つの「章」に「分割して」「独立させ」たこと──〈「『資本論』の成立過程」の概略〉で、「第4章」と「第5章」の二つの章に分割した理由を詳しく説明していますので、参照して下さい──と、「第4章」が「マルクスが恐慌の運動論を自分の言葉で解説する、現行の『資本論』における唯一の場所となった」(P44)ことだけで、「『資本論』全体の構想の再検討」を必要とする根拠も、どのように「『資本論』全体の構想の再検討」をするのかも、まったく述べられていません。そして、不破さんには失礼ですが、不破さんが二一世紀になって「発見」し、「激しい理論的衝撃」を受け、「ここを理解して『資本論』を読むと、多くの点で、『資本論』の解釈がこれまでのそれとはまったく違って」(『前衛』2015年1月号)きたという、「恐慌の運動論」(「架空の需要=恐慌」論)と不破さんが命名し歪曲し矮小化しているものは「恐慌を資本の現象的な流通形態から説明する」もので、目新しいものではありません。
自分の稚拙な主張に合わないマルクス・エンゲルス・レーニンの論述は歪曲して誹謗中傷しますが、利用できそうな文章は天まで持ち上げます。「マルクスが『恐慌の運動論』を直接解説した唯一の章」(P54-59)という「項」を見てみましょう。
二一世紀になって「恐慌の運動論」を大「発見」した不破さんは、「第一八章 商人資本の回転。価格」の文章を抜粋して、なにか「大発見」でもしたかのように、つぎのように言います。
「この文章と、第二部第一草稿でマルクスが恐慌の運動論を発見した時に書き付けた最初の文章とを読みくらべてみてください。最初の文章は産業資本を主語としての解説、今度は商人資本を主語としての解説ですが、冒頭の『商人資本は、……生産資本のために局面W-Gを短縮する』というのは、第一草稿の『流通過程の短縮』という言葉の再現にほかなりません。それによってつくりだされる『架空の需要』が再生産過程を制限を越えてまでも推進し、ついには恐慌にいたる、という論理も、第二部第一草稿で示された論理とまったく共通のものです。」と。
現代に生きる、多少でも経済学をかじった者ならば、この不破さんの文章の運びに苦笑いをすること請け合いです。
「流通過程の短縮」は資本主義的生産様式の社会での「商人資本」の存在理由であり、見かけ上の価値実現の見返りとして産業資本による搾取の分け前を得ることができるのです。「産業資本」の側から見ても「商人資本」の側から見ても、「流通過程の短縮」は「流通過程の短縮」です。マルクスが、資本主義的生産様式の社会での「商人資本」の役割を明らかにしたからといって、二一世紀になって不破さんが驚くべきことではありません。 「恐慌を資本の現象的な流通形態から説明する」方法として、マルクスが生きた時代に、『架空の需要』が実需を生み、それがまた『架空の需要』を生み、それらがある時点で、「恐慌」によって清算されることをマルクスが述べていることについて、現代に生きる、多少でも経済学をかじった者ならば、目新しいことなどとは思わないでしょう。
そして不破さんは、「恐慌」に至るメカニズムを説明した文章を抜粋して紹介し、「これまでほとんど無視された影の文章となってきたのは、たいへん残念なことでした。」と言います。「無視された影の文章」としてきたのは、これらの文章を二一世紀になって、やっと、「恐慌の運動論」などと称して大「発見」した不破さん自身ではないですか。開いた口がふさがりません。
不破さんが「無視された影の文章」として抜粋した「トリ」の部分を見てみましょう。
「遠隔地に売る(または国内でも在庫の山をかかえてしまっている)商人たちの〔支出の〕還流が緩慢になって、まばらになり、その結果、銀行には支払いを迫られたり、諸商品購入のさいに振り出した手形が諸商品の転売が行われないうちに満期になるということになれば、ただちに恐慌が到来する。そこで強制販売、支払をするための販売が始まる。そうなればそこにあるのは崩落であって、それは外見的な繁栄に一挙に結末をつけるのである」。
この「恐慌」の現象的な説明を「資本の価値」に着目して、恐慌に至る過程について、より詳しく説明した文章が『資本論』の他の箇所にあるので紹介します。
「主要な破壊、しかも最も急激な性質のものは、価値属性をもつかぎりでの資本に関して、資本価値に関して、生ずるであろう。資本価値のうち、単に剰余価値または利潤の将来の分けまえにたいする手形という形で存在するだけの部分、事実上は生産引き当てのいろいろな形の債務証書でしかないものは、それが当てこんでいる収入の減少とともにたちまち減価を受ける。金銀の現金の一部は遊休し、資本として機能しない。市場にある商品の一部分は、ただその価格のひどい収縮によって、したがってそれが表している資本の減価によって、やっとその流通・再生産過程を通ることができる。同様に固定資産の諸要素も多かれ少なかれ減価を受ける。そのうえに、一定の前提された価格関係が再生産過程の条件となっており、したがって再生産過程は一般的な価格低落によって停滞と混乱とにおちいるということが加わる。この攪乱や停滞は、資本の発展と同時に生じてあの前提された価格関係にもとづいている支払手段としての貨幣の機能を麻痺させ、一定の期限の支払義務の連鎖をあちこちで中断し、こうして資本と同時に発展した信用制度の崩壊が生ずることによってさらに激化され、このようにして、激烈な急性的恐慌、突然のむりやりな減価、そして再生産過程の現実の停滞と攪乱、したがってまた再生産の現実の減少をひき起こすのである。」(大月版④P318~319)
この文章は、不破さんによって、ここで「展開した理論の主要部分」が取り消されてしまった、不破さんの言う「理論的大転換の前夜に書かれた」第3篇第一五章の中の、かなり有名な文章で、「商人資本」のもつ「流通過程の短縮」という役割をしっかりと認識しての記述です。
このように、二一世紀になるまで不破さんが「無視」してきた文章と、二一世紀になって不破さんが「取り消し」た文章とは、同じ内容のことを、それぞれの「章」が取り扱うテーマに沿って、それぞれ異なる側面から述べられているのです。このように、「第一五章」と「第一八章」とは内容的に統一されており、少し前に不破さんが、なにか「大発見」でもしたかのように、「第一八章」の抜粋文と「第二部第一草稿で示された論理」とが「まったく共通のもの」と言った、資本主義的生産様式のもとでの「商人資本」のもつ「流通過程の短縮」という役割を、マルクスは『資本論』第三部第三篇第一五章の草案執筆時点で十分認識していたことを示しています。そのことは、マルクスが1865年に「第二部第一草稿での恐慌の運動論の発見」により「理論的大転換」をして『資本論』を書き変えることを決めたという不破さんの妄想が成り立たないことを示しています。
それにもかかわらず、不破さんは、「この時期の、新たに発見した恐慌の運動論へのマルクスの打ち込みぶりが、強く実感されます」とか「適切な機会となりうるところで、早く新しい理論のより具体的な展開をしておきたい、こういう意欲が垣間見える印象をもつからです」などと言って、読者をだまそうとします。しかし、マルクスは、〈「『資本論』の成立過程」の概略〉で指摘したように、「構想全体にあった『資本一般』という枠組みそのものの再検討が必要にな」り、「『資本論』全体の構想の再検討」が必要となって、『経済学批判』の続編から『資本論』として、1863年までの『剰余価値学説史』執筆前の研究の方法に基づく叙述の仕方から、本質と直接的な現象とのシームレスな貫徹メカニズムを示し、体系的に論述することに叙述の仕方を変える新たな著作の出版を決心したときから、このような叙述の仕方を行ってきました。だから、「新しい理論のより具体的な展開」をより詳細に「展開」した文章が、不破さんの言う〝古い地層〟の中の不破さんが「取り消し」た「章」(第一五章)にあるのです。だから、不破さんが「第一五章」で「価値ある遺産──『恐慌の根拠』についての二つの文章」として取り上げざるを得なかった文章が、不破さんの言う〝古い地層〟の中にもあるのです。
不破さんにとって打撃的なことを申し上げて心苦しい限りですが、不破さんは、「恐慌の運動論」の「発見」が「『資本論』全体の構想プランの画期的な変化の出発点となりました」と言って、自らの妄想の「出発点」は言いますが、「『資本論』全体の構想プラン」がどのように「画期的」に「変化」したのか、「新資本論」について、マルクスの遺作から探しだすことができません。少なくとも、「第一五章」について、「そこで展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」と言う以上は、不破さんの言う「第一五章」の「理論の主要部分」とは何で、それが「以後の草稿」の何処でどのように「取り消」されたのか、そのくらい明らかにするのは最低限の義務ではないでしょうか。しかし、それは、不破さんにとって不可能なことです。なぜなら、『資本論』は〈「『資本論』の成立過程」の概略〉で指摘したように、不破さんの妄想の「出発点」より以前からの構想にもとづいて執筆され、全体の整合性は保たれており、同時に、1881年に「第二部」の第8稿をもって『資本論』の執筆を打ち切るまで、不破さんが「古い地層」に属すると言う「第一篇」から「第三篇」までの草稿について、マルクスは一度も「取り消し」などしなかったからです。
なお不破さんには、1859年に刊行された『経済学批判』の次の文章などまったく頭の中に入っていないのでしょう。
「……交換過程における購買と販売との分離は、社会的素材変換の局地的・自然発生的な、先祖伝来のつつましやかな、心地よくてたわいのない諸制限を打ち破るが、それと同時にこの分離は、社会的素材変換の相合して一体を成している諸契機の分裂とそれらの対立的固定化との一般的形態であり、ひとことでいえば、商業恐慌の一般的可能性である。」
この、資本主義的生産様式における「購買」と「販売」との分離による「恐慌の可能性」についての知識は、マルクス経済学を少しでも学んだ人ならば誰でも知っていることです。そして、資本主義的生産様式における「信用」の拡大は、この「購買」と「販売」との分離による「架空の需要」のトレンドを拡大させる「槓杆」の役割をもっています。マルクスはそんなことは百も承知です。「1865年初め」にマルクスが「恐慌の運動論」を「発見」したなどというウソをつくのを、不破さんはやめるべきです。
なお、不破さんは「第五篇」の「解説」──ホームページ「エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説(その4)」参照──で、大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本』全4巻について、「私自身は、この研究の全体に一応目を通したという段階で、研究成果の全体を再現する力はもちませんが、私の理解した範囲での大谷研究の到達点も踏まえながら、エンゲルスの編集の問題点を指摘し、この部分(第二五章~第三五章のこと──青山)でのマルクスの研究と考察のあとを、できる限り追跡してゆきたいと思います」(P86)と大谷氏の知恵を借りて「エンゲルスの編集の問題点を指摘」する──エンゲルスが編集した『資本論』を改竄するためにエンゲルスを誹謗・中傷する──ことを述べています。
しかし、不破さんが知恵を借りようとしている大谷氏は、『マルクスの利子生み資本』③で、第3部第1稿の「第3章 資本主義的生産が進行していくなかで一般的利潤率が傾向的に低下していくという法則」について、「マルクスはここで、利潤率の傾向的低下の法則を明らかにしているが、さらに進んで、『資本主義的生産が進行していくなかで』、すなわち資本の蓄積が進んでいくなかで、この法則がどのように作用し、資本をどのように運動させることになるのか、ということを考察する。そしてこのなかで、資本の諸矛盾の累積が、ある時点でこれらの矛盾を爆発させて、恐慌をもたらすことを明らかにしたのである。」(P259)と言って、不破さんの「利潤率の傾向的低下の法則」の評価とは正反対の評価をしています。そして、大谷氏は、「なお、念のために述べておくが、マルクスは第3部第1稿第3章を書いたのち、第2部第1稿を書き、その後ふたたび第1稿の執筆に戻ったが、第1稿第5章を書きつつあった時点で、第1稿第3章で明らかにしていた一般的利潤率の傾向的低下の法則そのものについての論証を依然として正しいものと考えていたこと、言い換えれば、そこでの論証を不十分なものだったと反省して取り消すべきだと考えてはいなかったことは、第5章のなかの次の四つの記述を見れば明らかである。これはエンゲルス版第15章部分についても妥当することであろう。」(P275)と述べて、不破さんの暴論をきっぱりと退けています。
重ねて言います。不破さんは、自分の変節を合理化するために、「これは、私だけの勝手な結論ではありません。」などとウソをつくのは、もうやめるべきです。
現代のブルジョア経済学者の任務と〝産業循環〟
なお、不破さんは、当時の〝産業循環〟の一般的な現れ方を「恐慌の運動論」なるものに矮小化し、リーマン・ショックについても、「『架空の需要』にもとづく生産の無制限的拡大とその破綻という過程が典型的に現われていた」(『前衛』2015年1月号)と言って、現代の経済危機についての無知・無理解を示し、マルクス経済学をまったく理解していないことを告白します。※詳しくホームページ4-19「☆不破さんは、マルクスが1865年に革命観・資本主義観の大転換をしたという、レーニンも気づかなかった大発見を、21世紀になっておこない、マルクスの経済学をだいなしにしてしまった。」を参照して下さい。
マルクスは、『資本論』の「第二部」、「第三部」を通じて、私たちに、資本は拡大再生産なしには生きて行けないこと、拡大再生産のためには市場の不断の膨張が必要であるが市場の拡大には限界があること、その限界を克服するためには資本主義的生産様式のもとでの〝産業循環〟を通じて、資本の価値の減価が必要なことを教えています。そして、マルクスの時代の資本主義的再生産を円滑に行う唯一の方法は、購買と販売を分離し「架空の需要」をつくり、資本の流通過程を円滑に推進するための「信用制度」を発展させることであり、資本の価値の減価を伴う産業循環のゴールであり、産業循環をリセットさせる方法は恐慌でした。
現代のブルジョア経済学者の任務は、この避けることの出来ない、資本主義的生産様式が生む〝産業循環〟からいかに資本のダメージを少なくし、いかにして需要を創造するかということです。そして、マルクスが描写した当時の〝産業循環〟の一般的な現れ方と現代の〝産業循環〟の現れ方とではだいぶ様相が異なります。
現在は、「産業資本」も「商業資本」も在庫管理を徹底し、機械受注動向を景気の先行指標として注視し、不変資本の需給動向にも注意が払われ、不破さんの言う「架空の需要」が「恐慌」の「原因」となる事態はかなり回避され、資産価値の上昇によるバブルの発生とその崩壊をきっかけとする「危機」の発現へと〝産業循環〟の現れ方も変化しています。しかし、二一世紀になって、やっと、「架空の需要=恐慌」説を発見した不破さんは、リーマン・ショックについて、「『架空の需要』にもとづく生産の無制限的拡大とその破綻という過程が典型的に現われていた」と言うことによって、マルクスとマルクス主義(科学的社会主義)を台無しにしてしまいました。
なお、今日の〝危機〟のきっかけになる主なものとして、「欧米(日本を含む)の緩みすぎた金融」、「中国の債務」、「金融商品のコンピューター取引」等が挙げられています。
不破さんとマルクスの『資本論』の位置づけの違い
ここまで、「第一八章 商人資本の回転。価格」のなかの「資本の現象的な流通形態」から「恐慌」を説明する文章についての不破さんの「特別」な位置づけとその誤りについて見てきましたが、「第一八章」には不破さんとマルクスの『資本論』の「意義」の違いをあらわす文章がありますので、紹介します。
不破さんは、「第三部を読む」の最初の「項」で、「第三部の研究対象は何なのか」と問いかけて、「これから研究するのは、『社会の表面』に現れる世界」だと言い、「これまで第一部、第二部で見てきた世界」と「どこが違ってくる」のか、「それは、これからの研究のお楽しみ」で、「マルクスは、こういう意味で、第三部の内容の核心を示すものとして『諸姿容』の語を押し出したのでした。」(P12-13)と言いました。
そしてマルクスは、不覚にも、第一巻への「序言」で、二一世紀になって不破さんのような馬鹿な人が現れるなどとは夢にも思わず、第三部について、詳しくいえば「資本主義的生産の総過程における資本の諸姿容の科学的研究」を取り扱うというべきところを、第三部で「総過程の諸姿容」を取り扱うと「体言止め」の表現をしてしまいました。その結果、不破さんにおいては、第三部の研究が「科学的研究」から「諸姿容」の「お楽しみ」の「研究」になってしまいました。
しかし、マルクスが第三部において行ったことは、下記の文章にある「科学の仕事」を貫徹することでした。
「再生産の総過程に関するすべての表面的で転倒した見解は、商人資本の考察から取ってきたものであり、また商人資本特有の運動が流通担当者たちの頭のなかに呼び起こす観念から取ってきたものである。
読者が残念に思いながらも認めてきたように、資本主義的生産過程の現実の内的関連の分析が非常に複雑な事柄で非常に手数のかかる仕事だとすれば、また、目に見える単に現象的な運動を内的な現実の運動に還元することが科学の仕事だとすれば、……」(大月版P390-391)
このように、不破さんとマルクスの『資本論』「第三部」の位置づけは、まったく異なります。
続く
『資本論』「第三部」を利用した、不破さんの根拠のない「推測」と「虚構」を用いてのマルクスとエンゲルスへの誹謗・中傷、そして、『資本論』の歪曲に対して、根拠を示しての反論は大変なスペースと労力を要します。
「エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説(その3)」は、すでに、一枚のページとしての限界を超えつつありますが、「第三部」に関する不破さんの妄言への批判はやっと半分をすぎたところです。そして、「第五篇」以降、不破さんのエンゲルスの編集にたいする攻撃は、大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本論』の都合のいいところを利用しながら、ますます激しくなって行きます。そのような事情を踏まえ、続きは「エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説(その4)」として編集することにいたしました。
続きのホームページ「エセ「マルクス主義」者の『資本論』解説(その4)」はこちら。