大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本論』(全4巻)とマルクス・エンゲルスの『資本論』から学ぶこと
──『資本論』を読もう!!『資本論』をベースにグローバル資本主義(新自由主義)を暴露し克服しよう!!──
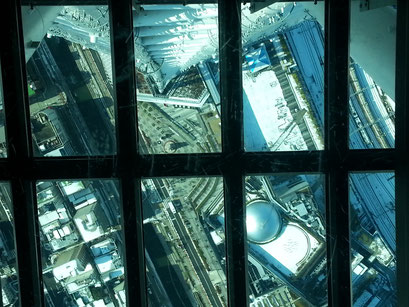
このページのPDFファイルはこちら
このページの続きは下記のPDFファイルをご覧下さい。
要、注目!!!!
このファイルの16ページ(「(7)産業循環」(P251-275)の項)では、
「なお、ここで、大谷氏は、第3部第1稿の「第3章 資本主義的生産が進行していくなかで一般的利潤率が傾向的に低下していくという法則」について、「マルクスはここで、利潤率の傾向的低下の法則を明らかにしているが、さらに進んで、『資本主義的生産が進行していくなかで』、すなわち資本の蓄積が進んでいくなかで、この法則がどのように作用し、資本をどのように運動させることになるのか、ということを考察する。そしてこのなかで、資本の諸矛盾の累積が、ある時点でこれらの矛盾を爆発させて、恐慌をもたらすことを明らかにしたのである。」(P259)と言っていますが、これは不破さんの「利潤率の傾向的低下の法則」の評価とは正反対であり、不破さんの「恐慌の運動論」とも考えを異にします。そして、大谷氏は、「なお、念のために述べておくが、マルクスは第3部第1稿第3章を書いたのち、第2部第1稿を書き、その後ふたたび第1稿の執筆に戻ったが、第1稿第5章を書きつつあった時点で、第1稿第3章で明らかにしていた一般的利潤率の傾向的低下の法則そのものについての論証を依然として正しいものと考えていたこと、言い換えれば、そこでの論証を不十分なものだったと反省して取り消すべきだと考えてはいなかったことは、第5章のなかの次の四つの記述を見れば明らかである。これはエンゲルス版第15章部分についても妥当することであろう。」(P275)と述べて、不破さんの暴論をきっぱりと退けています。」(PDFファイルのP16)
と、大谷氏が不破さんの期待に反して、不破さんの作った「恐慌の運動論」にもとづく資本主義発展論をきっぱりと退け、不破さんの言う『資本論』第三部「第三篇」の最初の「第一三章」は「マルクスの最大の経済学的発見を記録した輝かしい章」、最後の「第一五章」はここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」、中間の「第一四章」は「第一五章の準備のため」の章で「不要になった章」だなどという妄想をキッパリと否定していることを明らかにしています。是非、お読み下さい。
さあ、スタートです。
大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本論』とマルクス・エンゲルスの『資本論』から学ぶこと
はじめに──私がこのページを書いた理由
『資本論』を含むマルクス・エンゲルスの著作は、私たちに、資本主義社会を解明するための基礎的な知識と革命的な思想を与え続けています。
大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本論』は、『資本論』のためのマルクスの草稿を私たち誰もが読めるように日本語で紹介し、マルクスの論究の現場に私たちをタイムスリップさせてくれる貴重な著作です。そしてこの本を読んだ私は、エンゲルスが、「草案」も「筋書きさえもなく」、「ただ仕上げの書きかけがあるだけ」の『資本論』第三部第五篇の草稿を、マルクスが「与えようと意図したすべてのものを少なくともおおよそは提供するようにする」と、「それはマルクスの著書ではない」ものになってしまうので、そのような編集をあきらめ、「現にあるものをできるだけ整理することに限り、ただどうしても必要な補足だけを加えるということ」とした(大月版『資本論』④P9-10)という編集方針に基づきよくぞここまで読みやすい立派な『資本論』に仕上げたものだと、感心致しました。
だからこそ、大谷氏も、『マルクスの利子生み資本論』2の「第3部エンゲルス版の歴史的意義」で「エンゲルス版」の歴史的意義いついて次のように述べています。
「マルクス自身が刊行できなかった第2部および第3部を編集・刊行して、彼の主著の理論的部分を完成させたエンゲルスの功績は、それらがもつ欠陥や不十分さにもかかわらず、不朽のものである。」(P360)といい、「エンゲルスの最晩年の悪戦苦闘によって、人類は、そしてとりわけ労働者階級は『資本論』の第2部および第3部をもつことができた。かりに、エンゲルスによる第2部および第3部の刊行がなかったとして、これまでに経済学者は、そこで分析され展開されている諸問題をそこでなされているような仕方で自ら展開し、さらにそれを資本主義的生産の理論的分析に適用することができていたであろうか。……
エンゲルス編の第2部および第3部の欠陥をあげつらうことは、マルクスの草稿がかなりの程度にまで見ることができるようになったいまでは、むしろ手もない仕事だと言うことさえできる。しかしながら、第2部および第3部の編集・刊行というエンゲルスの不朽の業績は、言い換えればエンゲルス版『資本論』第2部および第3部の刊行の歴史的意義は、それらのもつ欠陥や不十分さによってけっして相殺されることはないであろう」(P363-4)、と。
このような評価にもかかわらず、大谷氏は同時に、「エンゲルス版第5篇は、草稿第5章とは全体の編成も大きく異なっており、エンゲルスの誤読にもとづいてなされた章別編成によって論旨の展開の筋道がほとんどなくなっており」、エンゲルスが編集は「マルクスの構想を覆い隠すという罪つくりな仕事でもあったのである」等々と、「論旨の展開の筋道」がどのようになくなったのかも、「マルクスの構想」がどのように「覆い隠」されたのかも示さずに、非難しています。
そして、大谷氏に『マルクスの利子生み資本論』の執筆を促したと思われる〝日本共産党のカウツキー〟とでもいうべき人物は、執拗にマルクス・エンゲルスの著作の根本思想をねじ曲げたり、彼らを誹謗・中傷したりしていますが、「『資本論』探求」という立派なタイトルをつけた、マルクス・エンゲルスを誹謗し、『資本論』を歪曲・誹謗することを目的とした本において、何とかして大谷氏を利用できないものかと無駄な努力を重ねています。
グローバル資本主義の結果への反発として誤った民族主義と帝国主義的な動きが世界中で強まりつつあるなかで、ダボス会議(2020/01)の討論会で、「我々の知っている資本主義は死んだ」という言葉が〝普通〟に発せられ、「経済は社会を豊かにし、人々の生活を豊かにするためにある」という〝「資本」のための経済から「人間」のための経済へ〟の転換、資本主義社会から社会主義社会への転換の必要性の認識が深まりつつあるとき、マルクス・エンゲルスの著作が複合汚染され、偏見に支配されることによって、若い人たちがマルクス・エンゲルス・レーニンの著作に直接触れる機会を逸し、資本主義社会を解明するための基礎的な知識と新しい生産様式の社会をつくるための革命思想を正しく学ぶ道が閉ざされるとしたら、日本の「科学的社会主義」はマルクスの言う「健全で「単純な」(!)常識の騎士たち」の思想に汚染されたままとなり、日本の未来はお先真っ暗なままで、財界と〝日本共産党のカウツキー〟とでもいうべき人物の思うつぼです。
私がこのページを書いた理由は、『資本論』とマルクス・エンゲルスの価値を低め、『資本論』を歪曲しようとする〝日本共産党のカウツキー〟とでもいうべき人達から『資本論』とマルクス・エンゲルスをまもることによって、世界の未来にとって、日本の未来にとって、少しでも役に立つことができればと思ったからです。そして、このページを読まれた皆さんが、マルクス・エンゲルス・レーニンから学び、『資本論』の思想・マルクス・エンゲルス・レーニンの思想を発展させる素晴らしいアイデアを得て、真の科学的社会主義の思想を拡め、「我々の知っている資本主義」を死なせ、「経済は社会を豊かにし、人々の生活を豊かにするためにある」という〝「資本」のための経済から「人間」のための経済へ〟の転換を実現するうえで、私のこの非力な文章が、ほんの少しでも、役に立つことができれば、それほどうれしいことはありません。
〈目次〉
Ⅰ、大谷氏が『マルクスの利子生み資本論』で述べていることの検証
・大谷氏が『マルクスの利子生み資本論』で批判的に述べていること
・このホームページで大谷先生の『マルクスの利子生み資本論』を通じて検証すべきこと
①「エンゲルス版第5篇」の各章の論旨の概要と提示されたテーマの他の章での展開についての概観
第21章 利子生み資本
第22章 利潤の分割 利子率 利子率の「自然的な」率
第23章 利子と企業者利得
・『資本論』はつぎに「企業者利得」の幻想性の曝露に移ります。
・「企業者利得」について、もっと詳しく見てみよう。
・おまけ、監督・指揮労働に関する不破さんの驚くべき謬論
第24章 利子生み資本の形態での資本関係の外面化
・おまけ、「貨幣資本」について
第21章から第24章までに書かれていたこと
②『資本論』の第25章、第26章および第27章のどこが問題なのか
〈第25章〉について
・第25章の概略
・エンゲルスの編集についての大谷氏の批判について
マルクスの草稿〔317上②〕(P157-158)に関して
マルクスの草稿〔317上③〕(P159-160)に関して
・〈『資本論』の当該部分の転載〉
・〈大谷氏の見解の概要紹介〉
・〈私の意見〉
マルクスの草稿〔317上④および⑤〕(P168-171)に関して
・〈大谷氏の批判に関する部分のマルクスの草稿の抜粋〉
・〈大谷氏の批判と私の考え〉
〈第26章〉について
・第26章の概略
・第26章への大谷氏の批判
・私の意見
・この章でのエンゲルスの挿入文に関する青山のコメント
〈第27章〉について
③『資本論』第5篇は、エンゲルスによって「論旨の展開の筋道がほとんどなくなった」ガラクタに変えられてしまったのか
・『資本論』の価値を不等に低める大谷氏の勇み足
・第3巻の最も困難な篇を立派に編集したエンゲルス
・大谷氏の『資本論』にたいする評価と『資本論』の葬り方
・詐欺師が編集したものを「マルクス『資本論』」などと僭称させてはならない
Ⅱ、『資本論』の位置づけとその読み方
①『資本論』の守備範囲
・資本主義経済を解明するベースとなる〝古典〟
・『資本論』の守備範囲を完璧に書いたものではない
②『資本論』を含む古典の学び方
・私のように原典に近づくことのできないものの古典のよみかた
・古典から何を学ぶのか
Ⅲ、『資本論』の歴史的限界と現代の資本主義
①『資本論』の歴史的限界とマルクス・エンゲルス・レーニン
②現代の資本主義の姿の解明
・おまけ──直接古典からではなく、マルクス・エンゲルス・レーニンの考えに触れるに当たって注意していただきたいこと
・『資本論』第28章以降の大谷氏の主張を検証したPDFファイル(第29章以降は作成中)

大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本論』とマルクス・エンゲルスの『資本論』から学ぶこと
このページは、上記のような趣旨にもとづき、まず第一に、大谷氏の前掲著作に即して『資本論』の当該部分の内容を検証し、次に、私たちにとっての『資本論』の位置づけを明確にし、最後に、『資本論』を学んだ者の責務として『資本論』の歴史的限界を指摘し現代の資本主義の姿を提示したいと思います。
Ⅰ、大谷氏が『マルクスの利子生み資本論』で述べていることの検証
・大谷氏が『マルクスの利子生み資本論』で批判的に述べていること
大谷氏は、『マルクスの利子生み資本論』(全4巻)の第1巻の「はしがき」で次のように述べています。
1980年4月から1982年にかけての幸運に得た在外研究の調査結果にもとづき帰国後「あらためて草稿第5章をエンゲルス版第5篇とつきあわせて精読するなかで、エンゲルス版第5篇は、草稿第5章とは全体の編成も大きく異なっており、エンゲルスの誤読にもとづいてなされた章別編成によって論旨の展開の筋道がほとんどなくなっており、さらに細部でもいたるところにエンゲルスの手入れ(書き換え、削除、書き加え)があって、草稿第5章そのものに拠らなければマルクスの利子生み資本論をそのあるがままにつかむことはできない、と確信するようになった」(P5-6)といいます。
そして大谷氏は、恩師である三宅義夫氏が『資本論』第3部第5篇の全体の編成について、誤った「定説」を主張する論拠のほとんどすべてが、草稿第5章(『資本論』第3部第5篇のための草稿のこと)の編成を正しく読みとれなかったエンゲルスが自分の誤った理解に合うように行なった手入れの箇所だったといい、そのような箇所の多くが『資本論』第3部の第25章および第27章に当たる部分に含まれていると言って、そのことを明らかにするために本書2巻の第5章と第7章を書いたといいます。(P6-10)
これらを踏まえ、大谷氏は、草稿第5章全体を「利子生み資本論」と見て、「第1篇利子生み資本」、「第2篇信用制度概説」、「第3篇信用制度下の利子生み資本」及び「第4篇資本主義以前の利子生み資本」の4篇に編成しています。
そのような問題意識をもっておこなわれた大谷先生の研究は、マルクスの草稿と「エンゲルス版」との相違を丹念に調べられ、草稿第5章に関するマルクスの論考とエンゲルス版との相違を注記した訳文として、20年の歳月を経て2002年に完了・結実されました。その成果は『資本論』を学ぶうえで大変ありがたいもので、その成果をまとめたのが、『マルクスの利子生み資本論』です。
大谷氏は、『資本論』第3部第5篇第25章(以降で第3部について言うときには、「『資本論』第○章」と表記します)のところで(第2巻P41-43)、エンゲルスが「マルクスの草稿を変えた点」として、
①下線、二重下線の箇所の違い
②草稿での角括弧の大部分が取り除かれている
③誤記等不完全文章の改善という純技術的なもの
④文章を加除して読みやすくしたり、不十分な記述の訂正
⑤文章を読み誤って不適切な修正をしたり、草稿と意味がまったく逆なところもある
との指摘をします。
続けて、同じく第25章について、「マルクスの草稿は、エンゲルスが仕上げた現行版とはいろいろな点でかなり違っている」(同P80-81)として、次の4点を指摘しています。
第1。「技術的な編集作業」を行い、「未定稿的な性格の強い草稿はより完成した叙述の装いを与えられ、読者にとっては読みやすいものとなった」が、「原意が変えられたり、力点が置き変わってしまったりしたところが生じている」。エンゲルス版を「厳密に解釈しようとした場合、エンゲルスによる修正箇所の表現に引きずられて無用の推論に誘われることがないとは言えない」。
第2。「本文、注、雑録、という三部分から成る草稿の構成を」、「本文とそれに関連する引用資料という二つの部分から成る構成に変えた」。その結果、文章が整理されたが、注と本文との関連が見えなくなり、注と雑録とがいっしょにされることによって、「両者の微妙な違いもまった隠されてしまった」。この編集の過程で「マルクスの抜き書きの意図が見えにくくなっている」。
第3。「雑録の途中から第26章という新たな章を始めることによって、雑録部分全体の性格と位置とが、ますます不分明になってしまった」。
第4。関連資料の部分の後半でのエンゲルスの手入れは、マルクスの構想を実現したものであるのか、いささか疑問だ。
と言います。
そして、同じく第2巻の「補章5第3部エンゲルス版の歴史的意義」で「エンゲルス版の問題点」として、
Ⅰ、読者はエンゲルス版を通じて、マルクスの第3部があたかもほぼ完成したものであったかのように受け取ってきた。
Ⅱ、エンゲルス版は、現行の全3部が、第1部から第3部へと順次に叙述された完成された著作であるかのような外観を与えている。
Ⅲ、エンゲルスは序文で、内容にかかわる彼の手入れには彼のものであることを明記したとの趣旨を記しているにもかかわらず、実際には、なんの注記もせずに明らかに内容にかかわるような手入れが行われている。
Ⅳ、エンゲルスの手入れには、必ずしも適切ではなかったと思われるものも少なくない。第25章の中半以降に「抜粋ノート」を入れ、第25章及び第26章とし、全体の整合性をとるために第33章をつくった。
と述べています。
なお、「草稿を変えた点」の③と④は「批判的に述べている」点ではありません。
・このホームページで検証すべきこと
大谷先生は、『マルクスの利子生み資本論』の全4巻を通じて上記のような指摘をしていますが、そのうち、「マルクスの草稿を変えた点」の①~④と「エンゲルス版の問題点」のⅠとⅡについては特別の検討を要しないし、「マルクスの草稿を変えた点」の③と④とは山ほどあり、読者の理解を大いに助けています。
大谷氏の論考では、全4巻を通じ、マルクスの草稿とエンゲルス版との表現の違いが数多く指摘されていますが、このホームページはそのすべてについて答える場ではありませんし、エンゲルスが読者の理解をたすけるために行なわれたものなので、大谷氏がエンゲルスの編集は「マルクスの構想を覆い隠すという罪つくりな仕事でもあったのである」と言い、「エンゲルスの誤読にもとづいてなされた章別編成によって論旨の展開の筋道がほとんどなくなっており」と非難し、大谷氏が最も重視していると思われる、『資本論』第25章から第27章について、そのどこが問題なのかということと、草稿第5章全体を「定説」のような編成と見るのか、それとも先ほど見た大谷氏がおこなった「4篇」の編成として見るのがいいのか、という二点にしぼって検証していきたいと思います。
*なお、第28章以降の大谷氏の見解についての私のコメントは、付録としてPDFファイルで順次添付していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
検討の手順として、大谷氏が「エンゲルス版第5篇は、草稿第5章とは全体の編成も大きく異なっており、エンゲルスの誤読にもとづいてなされた章別編成によって論旨の展開の筋道がほとんどなくなっており」と言っておりますので、まずはじめに、①「エンゲルス版第5篇」の各章(第21章~第24章)の論旨の概要と提示されたテーマの他の章での展開について概観し、つぎに、②『資本論』の第25章、第26章および第27章のどこが問題なのか考察し、最後に、③『資本論』第5篇は、エンゲルスによって、本当に、「論旨の展開の筋道がほとんどなくなった」ガラクタに変えられてしまったのか、という順に検討していきたいと思います。
なお、先ほど、「このホームページはそのすべてに答える場ではない」と申しましたが、このホームページでは、「Ⅱ『資本論』の位置づけとその読み方」で詳しく見ますが、①ある表現・ある文章が科学的社会主義の思想に合致しているかどうかという〝真実性〟の問題と②当時の科学的社会主義の思想の〝発展段階〟の問題とのかねあいのなかで、『資本論』第3部第5篇が資本主義社会を解明するためのベースとなる〝古典〟としての価値をもっているかどうかを大谷氏の論究の焦点にあわせて見ることによって、『資本論』の位置づけとその読み方を考える導入の部分としたいと考えています。

①「エンゲルス版第5篇」の各章(第21章~第24章)の論旨の概要と提示されたテーマの他の章での展開についての概観
『資本論』第5篇「第21章 利子生み資本」
ここでは、「利子生み資本」を、資本主義生産を前提とした「貨幣を生む貨幣」として、「可能的資本としての貨幣」として、その流通のし方とその商品としての売られ方とが論究されています。
「利子生み資本」の流通のし方・運動形態は譲渡と返済という貸借の運動であり、生産的資本の循環過程という現実の運動の中では、資本が資本として存在するのは、労働力の搾取過程の中だけのことであるが、資本としての商品である「利子生み資本」は、はじめから、資本として、利潤を創造するという使用価値をもつ価値として貸し出される。(大月版『資本論』④P428、以下ではページのみ表記する)
その利子率には、「自然的」な率というものは存在しないので、競争によって強制されるよりほかに他の法則はない。(P445)
*第21章427ページの「貨幣資本」は生産的資本の循環過程の中の貨幣を言っている。「本来の貨幣資本」を表現していることは、自明なことである。
「第22章 利潤の分割 利子率 利子率の「自然的な」率」
『資本論』は、この章の冒頭で、次のように述べています。
「この章の対象も、およそ後の諸章で取り扱われるすべての信用上の現象も、ここで細目にわたって研究することはできない。……われわれがここでしようとするのは、ただ、利子生み資本の独立な姿と利潤にたいする利子の独立化とを展開するということだけである。」(P447)
このようなスタンスで、まずはじめに、利子の「最高限界」と「相対的最低限」に触れたあと、「総利潤」と「利子」とのあいだに相関関係があると仮定すれば、「利潤率の高さは資本主義的生産の発展に反比例するのだから、したがってまた一国の利子率の高低も産業的発展の高さにたいしてやはり反比例するということになる」(P449)と、利子が一般的利潤率によって規制されることを述べる。つづいて、「利子率と景気循環との関係」(関係あり)や、「利子率が利潤率の変動にはまったくかかわりなしに低落する傾向」の主な二つの原因として、金利生活者の階級の増大と信用制度の発達をあげている。(P452)
そして、利子の自然的な率というものは存在せず(P453)、借り手の提供する担保の種類によって、また貸付期間の長短によっても利子率そのものが変化すること(P457)を述べる。
これらを踏まえ、利子率と利潤率との相違について、利子率は、貸付可能な貨幣資本の供給と需要がその都度の利子の市場水準を決定し、需要供給関係によって直接に規定され、その都度確定されるが、利潤率(一般的利潤率)は、複雑な諸原因の結果として、不断の変動を通じて、利潤の最低限界として現れるだけであることを述べる。
なおここで、「貨幣資本」が、大工業の発展につれて、「社会的資本を代表する銀行業者の統制のもとに置かれ」、一方で「大量にまとまった貸付資本として」供給され、他方で資本の需要の重みにしたがって資本家階級のあいだに分配される、という「信用制度」の課題が呈示されます。これが、第25章、第27章でくりかえし呈示され、深められていきます。あたかも交響曲が進行するように。
同時に、(後の仕上げのための覚え書)として、第25章以降で本格的に論究する「支払手段としての貨幣の機能」をになう「商業信用」の役割が簡単につづられています。これから本格的に論究する「信用制度」というテーマを視野において、どのような文章構成を考えていたのか、興味は尽きません。
そして、こんにちの先進国の〝産業の空洞化と低金利とマネーの狂乱〟を目の当たりにして、「利潤率の高さは資本主義的生産の発展に反比例するのだから、したがってまた一国の利子率の高低も産業的発展の高さにたいしてやはり反比例するということになる」という『資本論』の言葉は、現代のグローバル資本の展開の根拠を示すものです。
*第22章461ページの「貨幣資本」は、生産的資本の循環過程で使われる前提としての、「利子生み資本」のことであることも、文意に即して自明のことである。
「第23章 利子と企業者利得」
第23章は、「利子は、われわれがすぐ前の二つの章で見たように、機能資本家としての産業資本家や商人が、自分の資本ではなく借り入れた資本を充用するかぎり、この資本の所有者であり貸し手である人に支払わなければならないところの、利潤すなわち剰余価値の一部分にほかならないものとして元来は現れる」(P463)と、章の冒頭で、「利子」が「剰余価値の一部分にほかならないもの」であることを確認し、その「利子」とセットの関係にある「企業者利得」の資本主義社会での認識の幻想性とその根拠を明らかにしています。
若干スペースをとるが、大事な論点を含み、「エセ」マルクス主義者のお気に入りのワードも出てくるので、見てみましょう。
『資本論』は、まず、「資本家が貨幣資本家と産業資本家とに分かれるということだけが、利潤の一部分を利子に転化させ、およそ利子という範疇をつくりだすのである。そして、ただこの二つの種類の資本家のあいだの競争だけが利子率をつくりだす」(P463-4)ことを述べます。そして、このように「利子」と「企業者利得」とに分かれることによって、生産過程での労働者の搾取の結果である「利潤」が、「利子は資本自体の果実、生産過程を無視しての資本所有の果実」として、「企業者利得は、過程進行中の、生産過程で働いている資本の果実であり、したがって資本の充用者が再生産過程で演ずる能動的な役割の果実」としての外観をとり、「総利潤の二つの部分がまるでそれぞれ二つの本質的に違った源泉から生じたかのように互いに骨化され独立させられる」ことを明らかにします。
なお、この「利潤」の「利子」と「企業者利得」とへの分割は、第7篇第48章「三位一体的定式」へと繋がっていきます。
同時に『資本論』は、「競争だけが利子率をつくりだす」からといって、「貨幣資本」全体について、「生産資本として機能しなくても、すなわち利子が単にその一部でしかない剰余価値を創造しなくても、利子を生むはずだ」と考えるのは、「もしも資本家のむやみに大きい部分が自分の資本を貨幣資本に転化させようとするならば、その結果は、貨幣資本のひどい減価と利子率のひどい低落」とをもたらすので、大まちがいであることを述べ(P473)るとともに、「貨幣資本」が「利子」を得るのは、「貨幣資本」が「独立な力として、生きている労働力に対立しており、不払労働を取得するための手段になっている」からであるが、「利子生み資本そのものが自分の対立物としているのは、賃労働ではなく、機能資本だから」、「利子という形態では、賃労働にたいするこのような対立は消えている」ことも明らかにしています。(P475)
・『資本論』はつぎに「企業者利得」の幻想性の曝露に移ります。
大月版『資本論』の475ページでマルクスは「企業者利得は、賃労働にたいして対立物をなしているのではなく、ただ利子にたいして対立物をなしているだけである」と言っています。
自らの誤った主張を党内に拡めようとする不破さんは、目の上のたんこぶであるエンゲルスの価値を低めようとして誹謗中傷をふりまいていますが、そのうちの一つに、「プロレタリアートとブルジョアジーの対立というのは、資本主義の生産関係の一番の基本で、資本主義の発生の時点から始まっているものなのに、なぜそれが事態の発展のなかで明るみに出てくる現象形態なのか」(『前衛』No904(2014年1月号))とエンゲルスを攻撃していますが、この文章も、「エセ」マルクス主義者が『資本論』の価値を低め、自らの偉大さを示すのに利用しても不思議ではない文章です。党員の無知を信じてエンゲルスを陥れる。同じように利用されそうな文章なので、つい、わき道にそれてしまいました。
*詳しくはホームページ4-8「不破さんは、「プロレタリアートとブルジョアジーの対立」は「資本主義の発生の時点から」あるのに、事態の発展のなかで明るみに出るのは矛盾だと、自分の理解力のなさを根拠にエンゲルスを誹謗している」を参照して下さい。
「企業者利得は、賃労働にたいして対立物をなしているのではなく、ただ利子にたいして対立物をなしているだけである」ように見えるのはなぜか。「彼(機能資本家)の資本家としての機能は、剰余価値すなわち不払労働をしかも最も経済的な諸条件のもとで生産することにあるということは、完全に忘れられる」のはなぜか。それは、「資本家が資本家としての機能をなにもしないで単なる資本所有者である場合にも利子は資本家のものになり」、機能資本家は資本の被所有者であっても監督労働によって企業者利得をえるという、「二つの種類の資本家のあいだでの利潤の分割理由が、いつのまにか、分割されるべき利潤の存在理由に、あとでどのように分割されるかにかかわりなく資本がそのものとして再生産過程から引き出す剰余価値の存在理由に、転化してしまう」(P476-7)からである、と言います。
こうして、資本主義社会の認識の幻想性と転倒性が完成します。
・「企業者利得」について、もっと詳しく見てみよう。
「企業者利得には資本の経済的機能が属するが、しかしこの機能の特定な、資本主義的な性格(搾取する労働という──青山)は捨象され」(P480)、「監督や指揮の労働」の「どんな結合的生産様式でも行われなければならない生産的労働である」(P481)という側面だけが残り、このことによって、資本主義社会における正当で、社会的に必要な労働ででもあるかのようにみなされることとなる。同じような関係は、「奴隷制度」のもとでもみられることが述べられる。
そして、「信用の発展につれてこの貨幣資本そのものが社会的な性格をもつようになり、銀行に集中されて、もはやその直接の所有者からではなく銀行から貸し出されるようになることによって、また、他方では、借入れによってであろうとその他の方法によってであろうとどんな権原によっても資本の所有者ではない単なる管理者が、機能資本家そのものに属するすべての実質的な機能を行うことによって、残るのはただ権能者だけになり、資本家はよけいな人物として生産過程から消えてしまうのである」(P487)。
しかし、やはり、資本主義は資本主義である。「資本主義的生産の基礎の上では、株式企業において、管理賃金についての新たな欺瞞が発展する。というのは、現実の管理者の横にも上にも何人かの管理・監督役員が現れて、彼らの場合には管理や監督は実際に、株主からまきあげて自分のもうけにするための単なる口実になるからである」(P489)。この事実は、相談役、会長等々として現代に生き、はばをきかせているが、これは資本家(資本主義的生産様式における経済的「価値」の私的所有者)にとても不都合なことではない。現代では、このような「管理者」を資本家と同等の意識状態に置くために、ストックオプションの制度が幅広く用いられて、資本主義は資本主義としての進化をしている。
・おまけ、監督・指揮労働に関する不破さんの驚くべき謬論
以上が第23章のあらましですが、不破哲三氏は、「監督や指揮の労働」は「どんな結合的生産様式でも行われなければならない生産的労働である」(P481)という文章をヒントに、驚くべき「未来社会」像と「科学的社会主義」の理論を展開します。
不破さんは、「従来の社会主義論」について、「たいていが、生産物の分配どまり、経済的土台の変化だけに目を向けて、人間の発達という肝心なことが出てこないのです。だから『未来社会』といってもあまりうらやましくない」といって「搾取」から目を逸らせ、「未来社会」像として、「搾取」を脇に置いた「経済的土台の変化」を無視した「監督や指揮の労働」を取り出して、〝指揮者はいるが支配者はいない〟社会を夢想します。そして、「経済的土台の変化」を無視する不破さんは、マルクス・エンゲルスのいう「自由の国」とは「自由な時間」のことで、余暇時間をマルクスは「自由の国」と呼び、資本主義社会にも〝余暇〟があり「自由の国」があると言います。そして、「未来社会」の社会変革の主体的条件は、自分自身のために使える「自由な時間」を使って人間が発達することであり、「社会主義社会」では「人間の能力の発達が社会発展の最大の推進力になってゆく」と、現代のIT未来論者のような「経済的土台の変化」とその基での生産力の発展を無視した「人間の能力の発達」だけをいう科学的社会主義の思想とはかけ離れた、「独創的」な思想を吹聴しています。
同時に不破さんは、賃金が上がれば経済な発展すると、「経済的土台の変化」には「目を向け」ず、資本家の「生産物の分配」のわずかな譲歩で資本主義の矛盾が解決するかのような幻想をふりまいています。
*残念ながら、このページは、このような不破さんの謬論にかかわりあう場ではありませので、「従来の社会主義論」についての不破さんの謬論の詳しい説明は、ホームページ4-16「☆不破さんは、エンゲルスには「過渡期論」が無いと言い、『国家と革命』と『空想から科学へ』は「マルクスの未来社会像の核心」を欠いていると誹謗・中傷する」及びホームページ4-17「☆「人間の発達」は資本主義を社会主義に変え、生産力を発展させなければ保障されない」を、「自由の国」とは「自由な時間」のことで、資本主義社会にも〝余暇〟があり「自由の国」があるということについては、ホームページ4-26「『資本論』刊行150年にかこつけてマルクスを否定する不破哲三氏」を、科学的社会主義の思想とはかけ離れた独創的な思想全般については、ホームページ4-20「☆「社会変革の主体的条件を探究する」という看板で不破さんが「探究」したものは、唯物史観の否定だった」を、是非、参照して下さい。
「第24章 利子生み資本の形態での資本関係の外面化」
この章は、第21章で示された「利子生み資本」の「貨幣を生む貨幣」としての商品の特質の一層の論究とそこから展開されるとんでもない作り話について書かれています。
『資本論』はまず、「利子生み資本」が「一定の期間に一定の剰余価値を生む資本」となることによって、「利子を生むということが貨幣の属性になり」、その発生の痕跡(利潤の分割とその源泉)を少しも残さないものとなることを述べます(P491)。そして、「利子生み資本」から利潤の源泉(搾取)は、もはや、認識できなくなり、「利子生み資本」が資本主義的生産過程から切り離されて独立な存在となることによって、「生産関係の最高度の転倒と物化」、「資本の神秘化」が行われることを明らかにします(P492)。
このような「生産関係の最高度の転倒と物化」と「資本の神秘化」が、「資本とは、永久に存続し増大する価値としてのその固有の属性によって…(青山略)自分自身を再生産し再生産のなかで自分を増殖する価値であるという観念は、錬金術師たちの空想も遠く及ばない作り話的な」思いつきを生み、「われわれの救世主が生まれた年に」「六%の複利で貸された一シリングは、全太陽系を土星の軌道の直径に等しい直径をもつ一つの球にした場合に包含できるであろうよりも、もっと大きい額の金に、増大しているであろう」などという主張を生むこと、そして、その主張の誤りが「生産関係の最高度の転倒と物化」と「資本の神秘化」にあることを、「過去の労働の生産物の価値の維持」や拡大は「それらの生産物と生きている労働との接触の結果でしかない」こと(したがって、「資本」と違って生産力は六%の複利では伸びないこと──青山)、「資本」が剰余労働を生みだすことができるのは資本主義的生産関係のもとでのことであることをあげて、論駁しています(P495-501)。
なお、この「資本の神秘化」は後の章で「資本の架空性」の問題として再度論じられます。
・おまけ、「貨幣資本」について
また、大谷氏は第25章に関して、マルクスの草稿での「monied Capital」という言葉をエンゲルスが「貨幣資本」と訳したことについて、「エンゲルスは──ドイツ語での印刷用原稿を作るためにはやむをえなかったことではあるが──monied Capital等々も、ドイツ語(Geldkapital)に訳して統一した。そのために、原文のニュアンスが失われている場合もあるように思われる」(P103)と言って批判ていますが、この章(第24章)に興味深い記述がありますので紹介しておきます。
それは、大月版『資本論』④493ページの「こうして、利子生み貨幣資本では(そしてすべて資本はその価値表現から見れば貨幣資本であり、言い換えれば、今では貨幣資本の表現とみなされる)、貨幣蓄蔵者の敬虔な願望が実現されているのである」という文章です。
「利子生み資本」が「利子生み貨幣資本」と表現され、「利子を生むということが貨幣の属性になり」、「すべて資本はその価値表現から見れば貨幣資本である」ところの「貨幣資本」としての意味が、この文章から、『資本論』の読者に強く印象づけられます。資本主義社会での「貨幣」の「利子生み貨幣資本」としての普遍化の意味を、「貨幣資本」という言葉からしっかりとイメージすることが、私たちに求められています。そして、日本語の「貨幣資本」という言葉が、価値実現過程(生産的資本の循環過程)での「貨幣」という意味とともに「利子生み資本」としての「貨幣」という意味をもつことは、『資本論』第3巻を読めば、誰にでも理解できることです。
第21章から第24章までに書かれていたこと
このように、第21章から第24章までに書かれていたことは、「利子生み資本」の資本主義社会での定義づけです。そして、第25章から第27章では、「資本主義のもとで生まれた『信用』制度」によって資本がどのような運動をし、資本主義がどのように発展するのかを考察をすることになります。

②『資本論』の第25章、第26章および第27章のどこが問題なのか
〈第25章 信用と架空資本〉について
・第25章の概略
第25章は、資本の行動を規定する「信用」の機能の説明とともに、第22章の「(後の仕上げのための覚え書)」で簡単にふれられていたことと、第24章の「利子生み貨幣資本」の「資本の神秘化」、あるいは、将来の儲けから現在の「資本」の価値をはかる、「資本」の「架空性と投機性」とが、資本の行動と「信用」の機能を通じて、資本主義的生産の循環過程を支配する様子が展開されています。
簡単に文章のすじを辿ってみます。
①「信用制度」は「生産者や商人どうしのあいだの相互前貸」から発展したことを述べ、その実態を草稿中の資料で紹介し、②同時に、貨幣取引業の発展が利子生み資本の管理という「信用制度」のもう一つの面を発展させ、貸し手の集中と借り手の集中を実現したこと、銀行業者が与える信用はいろいろな形で与えられることを述べ、③②を踏まえて、銀行業者の二重の業務について、信用の貨幣機能について、銀行の利潤の得かたについて、銀行によって取引が容易になり資金に余裕が生まれ、信用により使用される貨幣の何倍もの決済ができることについて、エンゲルスは、草稿中の資料を一部省略し一部要約して引用している。④エンゲルスは、このような信用の機能にもとづいて草稿中の資料が示す実例を説明するために二、三のことだけを簡単に述べるとして、1842年の末から1848年の間のイギリスの経済・信用の動きを説明する自らの文章(パラグラフ)を挿入する。⑤続いてエンゲルスは、Ⅰとして、草稿の他の箇所にあった、1847年の恐慌中に国債と株が非常に減価したという内容の資料を挿入し、続けて、③につづく草稿中の文章をⅡ、Ⅲとして編集します。⑥Ⅱでは、信用によって資金の行き詰まりを一時的にさき延ばす実例が、Ⅲでは、1847年4月のイングランド銀行の手形割引業務の縮小が手形の有効期間を短縮させたこと、その結果ほとんどすべての商社の資金が逼迫し、投機業者から振り出される非常に多くの手形が出回り、生産物の価値実現(商品資本が売れて貨幣資本になること)の前に信用(手形)によって貨幣を手に入れたり信用を使った一時的な錬金術などがおこなわれることが述べられている。⑦エンゲルスは、草稿の他の箇所の文章を使ってⅣ及びⅤとして、第25章の編集を終えます。Ⅳでは、1847年の恐慌の原因に関して、信用の不相応な膨張が現れたこと、十分な担保がなければ手形は引き受けないが外国からの手形が空手形かどうかは見分けることができず、破局の頂点では〔各自自由に逃げよ〕が展開されることを述べ、最後にⅤで、1857年にも同じことが行われていることをのべています。
このように、第25章は、エンゲルスの補足によって「恐慌」にまで踏み込んでいますが、信用制度の確立の経過と役割及び信用制度の抱える資本(貨幣)創出機能、そのもとでの資本の行動について、マルクスの草稿の趣旨が十分に生かされた編集となっています。
・エンゲルスの編集についての大谷氏の批判について
大谷氏は、第25章は、基本的には草稿の317- 320からなっているが、若干の部分はそれ以外のところから取られ、エンゲルスによる文章もある(『マルクスの利子生み資本論』第2巻P63-64、以下括弧内の「『マルクスの利子生み資本論』第2巻」は省略)といい、下記のようにエンゲルスの編集を批判します。
マルクスの草稿に従って、大谷氏の見解を見ていきましょう。
マルクスの草稿〔317上②〕(P157-158)に関して
大谷氏は、第25章に係るマルクスの草稿の最初のパラグラフの「われわれはただ商業信用だけを取り扱う」というフレーズの「商業信用」をエンゲルスが「商業・銀行業者信用」に変えたことが、「従来『商業信用と銀行信用』と訳され」、そのことによて、「信用論ではこの二つの信用を論じることがその根幹をなすという理解を支える重要な典拠となってきた」(P126)と、エンゲルスが「商業・銀行業者信用」に変えたことに咎があるかのように言います。
しかし、エンゲルスが草稿の「商業信用」という言葉を、文脈の中で、わかりやすく「商業・銀行業者信用」と言い換えたことがどうして責められなければならないのでしょうか。「商業・銀行業者信用」というワードを日本の研究者が「商業信用と銀行信用」と訳して、それがたとえ文脈の中で誤っていたとしても──実際には、後で見るように誤ってなどいないが──、それはエンゲルスの責任ではありません。そして、また、「商業信用と銀行信用」とを論じることが信用論の根幹でないならば、それは、信用論の根幹が「商業信用と銀行信用」だと論じた研究者の責任であり、絶対に、エンゲルスの「責任」などではありません。
それぞれのケースで何が真実かを探求するのが科学的社会主義の思想の基礎であり、宗教ならまだしも、誰かが言ったことを「典拠」とするような人たちにマルクス経済学を語る資格などありません。「典拠」(?おかしな表現だ)としている人たちの理論が誤っているならば、大谷氏はその人たちの理論を批判すべきで、「典拠」(?)となった書物を責めるべきではありません。
この文章のなかに出てくる「商業信用」という言葉は、大谷氏も言うように、「私的信用一般」を指していて、「再生産に携わっている資本家が互いに与え合う信用」だけを意味するものではありません。そして、これに続くパラグラフ(マルクスの草稿〔317上③〕)で「生産者や商人どうしのあいだの相互前貸」という表現で、本来の「商業信用」についての叙述があり、その次のパラグラフ(マルクスの草稿〔317上④および⑤〕)で「銀行信用」についての叙述があるので、エンゲルスは草稿の「商業信用」という言葉を「商業・銀行業者信用」と変えたのです。これを受けて、大月版『資本論』ではエンゲルスの「商業・銀行業者信用」という表現を「商業信用と銀行信用」と変えて、読者に一層理解しやすくしたのです。
この、エンゲルスや日本の訳者の補正のどこに問題があるというのでしょうか。
マルクスの草稿〔317上③〕(P159-160)に関して
最初に『資本論』の当該部分を転載し、つぎに大谷氏の見解の概要を紹介し、最後に私の意見を述べさせていただきます。
・〈『資本論』の当該部分の転載〉
「私は前に(第一部第三章第三節b)、どのようにして単純な商品流通から支払手段としての貨幣の機能が形成され、それとともに商品生産者や商品取引業者のあいだに債権者と債務者との関係が形成されるか、を明らかにした。商業が発展し、ただ流通だけを念頭において生産を行う資本主義的生産様式が発展するにつれて、信用制度の自然発生的な基礎は拡大され、一般化され、完成されて行く。だいたいにおいて貨幣はここではただ支払手段としてのみ機能する。すなわち、商品は、貨幣と引き換えにではなく、書面での一定期日の支払約束と引き換えに売られる。この支払約束をわれわれは簡単化のためにすべて手形という一般的な範疇のもとに総括することができる。このような手形はその満期支払日まではそれ自身が再び支払手段として流通する。そして、これが本来の商業貨幣をなしている。このような手形は、最後の債権債務の相殺によって決済されるかぎりでは、絶対的に貨幣として機能する。なぜならば、その場合には貨幣への最終的転化は生じないからである。このような生産者や商人どうしのあいだの相互前貸が信用の本来の基礎をなしているように、その流通用具、手形は本来の信用貨幣すなわち銀行券などの基礎をなしている。この銀行券などは、金属貨幣なり国家紙幣なりの貨幣流通にもとづいているのではなく、手形流通にもとづいているのである。」(大月版④P502-503)
まとまりのある、誰でも理解可能な文章です。
・〈大谷氏の見解の概要紹介〉
㋑エンゲルスが取り入れなかったマルクスの引用でマルクスは、「信用による貨幣の代位、貨幣機能の遂行は、信用制度のもとでは、銀行券流通と預金の振替という新たな形態をもつようになるが、その基礎が手形とその流通とにあるのだということ」を考えていた。(P86-87)
㋺エンゲルスは、マルクスの草稿の「信用制度の本来の基礎」となっているところを「信用の本来の基礎」とし、「信用」、「信用システム」、「信用制度」を「ほとんど彼の語感によって……ほとんど恣意的なもの」にしており、その結果「信用システム」と「信用制度」との区別を見えないものにしてしまっていると言い、同時に「マルクスがどこでも」両語(「信用システム」と「信用制度」)を明確に使い分けているとも言いがたいとも言う。(P88-89)
㋩「信用制度」とは銀行制度を主要内容とし、だから、このパラグラフは「信用=銀行制度」の「さまざまの信用形態を取り扱い、さまざまの信用操作を行うことを一つの本質的な特徴としている」そうした「側面とその基礎について述べている」。(P89-90)
㋥「以上要するに、この本文パラグラフでは信用制度の信用システムとしての側面、『信用取引』という側面、およびそこで用具として用いられる信用貨幣、とその基礎とについて書かれているのである」。(P91)
・〈私の意見〉
㋑で大谷氏が述べていることは、『資本論』の当該部分に含まれており、当該部分を読めば容易に理解できることです。
㋺については、大谷氏がP83で『経済学批判』から引用した文章中の「信用システムが存在するよりも以前に」という文の中の「信用システム」という語が、その直後に出てくる「信用制度」と同一の意味に使われている点からしても、「信用システム」も「信用制度」も資本主義的生産様式のもとでの「信用」を意味しており、エンゲルスが「信用の本来の基礎」と言い換えてもなんら問題は生じない。
㋩と㋥での「本文パラグラフ」の理解のしかたについてですが、書いてあることを正しく理解すればよいことです。
「資本主義的生産様式が発展するにつれて、信用制度の自然発生的な基礎──商品生産者や商品取引業者のあいだに形成された債権者と債務者との関係──は拡大され、一般化され、完成されて行く。ここでの貨幣の機能は支払手段である。だから、手形が、最後の債権債務の相殺によって決済されるかぎりでは、絶対的に貨幣として機能する。
生産者や商人どうしのあいだの相互前貸が信用の本来の(元々の)基礎であり、手形が信用貨幣すなわち銀行券などの本来の(元々の)基礎をなしている。
この流通用具としての銀行券などは、金属貨幣なり国家紙幣なりの貨幣流通の機能にもとづいているのではなく、手形流通の機能、つまり貨幣の支払手段としての機能にもとづいている。」と。
つまり、マルクスとエンゲルスは、ここで「信用制度」の「商業信用と銀行信用」という二つの面のうちの「商業信用」の本質について述べているのです。
エンゲルスの編集の、どこに、大谷氏が目くじらを立てるような問題点があるのでしょうか。
マルクスの草稿〔317上④および⑤〕(P168-171)に関して
・〈大谷氏の批判に関する部分のマルクスの草稿の抜粋〉
信用制度の他方の側面は貨幣取扱業の発展に結びついている。〈……〉貨幣取扱業というこの土台のうえで信用制度の他方の側面が発展し、〔それに〕結びついている、──すなわち、貨幣取扱業者の特殊的機能としての、利子生み資本あるいは貸付可能な貨幣資本の管理である。貨幣の貸借が彼らの特殊的業務になる。彼らは貸付可能な貨幣資本の現実の貸し手と借り手とのあいだに媒介者としてはいってくる。一般的に表現すれば、銀行業者の業務は、一方では、貸付可能な貨幣資本を自分の手中に大規模に集中することにあり、したがって個々の貸し手に代わって銀行業者がすべての貨幣の貸し手の代表者として再生産的資本家に相対するようになる。彼らは貸付可能な貨幣資本の一般的な管理者としてそれを自分の手中に集中する。他方では、彼らは、商業世界全体のために借りるということによって、すべての貸し手に対して借り手を集中する。(彼らの利潤は、一般的に言えば、彼らが貸すときの利子よりも低い利子で借りるということにある。)銀行は、一面では貸付可能な貨幣資本の、貸し手の集中を表し、他面では借り手の集中を表しているのである。(P168-171)
注)青字の「貸付可能な貨幣資本」は青山が「monied Capital」という言葉を正確に表現した。また、〈……〉は青山が行なった略。
・〈大谷氏の批判と私の考え〉
〈大谷氏の批判〉
大谷氏は、「monied Capital」という言葉を「貨幣資本」と訳したことについて、「エンゲルスは──ドイツ語での印刷用原稿を作るためにはやむをえなかったことではあるが──monied Capital等々も、ドイツ語(Geldkapital)に訳して統一した。そのために、原文のニュアンスが失われている場合もあるように思われる」(P103)と言って批判します。
〈私の考え〉
このパラグラフにおける「monied Capital」の意味は「貸付可能な貨幣資本」であるので上記の文章ではあえて「貸付可能な貨幣資本」と表記したが、同じパラグラフの中に「貸付可能な貨幣資本」というフレーズがあるので、正確に表現するとマルクスの草稿は上記のようになり、「monied Capital」と「貸付可能な貨幣資本」とが同一の表現になってしまいます。そこで、エンゲルスは「monied Capital」と「貸付可能な貨幣資本」とのドイツ語文での差を出すためにあえて「貨幣資本」と表現したように思われるが、パラグラフ全体を理解するうえでまったく問題は生じません。そして、その次のパラグラフでは、「monied Capital」を「貨幣資本」と表現することこそが合理的です。
第24章の「・おまけ、『貨幣資本』について」で触れたように、日本語の「貨幣資本」という言葉も、価値実現過程(生産的資本の循環過程)での「貨幣」という意味とともに「利子生み資本」としての「貨幣」という意味をもち、「利子を生むということが貨幣の属性になる」社会(資本主義社会)での信用制度を論じているところで「monied Capital」を「貨幣資本」と訳すことが「原文のニュアンスが失わ」せることはありません。もしも、「原文のニュアンスが失われている場合」があるなら、「原文のニュアンスが失われている場合もあるように思われる」などと言うのではなく、「原文のニュアンスが失われている場合」を具体的に指摘すべきです。
〈大谷氏の批判〉
また、大谷氏は「一方では……、他方では……」の内容を、最後の文で「一面では……、他面では……」として要約していることは一目瞭然である。ところが、エンゲルスはこのうちの「一方では」という語を「この面から見れば」と書き換えた。これは誤りだと言います。
〈私の考え〉
しかし、「貨幣取扱業というこの土台のうえで信用制度の他方の側面が発展し、〔それに〕結びついている、──すなわち、貨幣取扱業者の特殊的機能としての、利子生み資本あるいは貸付可能な貨幣資本の管理である」等の文章を見れば分かるとおり、この草稿は非常に完成度が低いものです。そのことを踏まえて私の意見を申し上げます。
このパラグラフは信用制度の「二つの側面」のうちの前述の「商業信用」の「ほか」の「他方の側面」(貸付可能な貨幣資本の管理の側面)につて述べたものです。そして、「一般的に表現すれば」と言って、「一方では」以下で銀行業者の「貨幣の貸借」という「彼らの特殊的業務」について、「(……)」のまえまでの文章で述べています。だから、エンゲルスはあえて「一方では」という語を「この面から見れば」と書き換えることによって、銀行業者が貸付可能な貨幣資本の一般的な管理者であるというマルクスの考えを明確に伝えようと思ったのではないでしょうか。そして、「他方では」ではじまる文章は、「銀行業者が貸付可能な貨幣資本の一般的な管理者である」ということが、「他方で同時に」「貸し手の集中」と「借り手の集中」をもたらすことを述べています。だから、草稿では、パーレン(丸括弧)の中で、銀行業者が「貸す」ときと「借りる」ときの「利子」のことが書かれており、この「他方では」ではという文章の内容を簡略化していったのが、「一面では」、「他面では」という文章なのです。それを、エンゲルスは読みやすくするために、「一面では」、「他面では」という文章を「他方では」ではじまる文章のすぐ後に置き、パーレンの中の文章をパーレンを取って、その後に置いたのです。
だから、大谷氏の、「一般的に表現すれば、……」以下の二つのセンテンスの要約が「一面では……、他面では……」というセンテンスだという主張は、まったく間違っています。
ここまでの文章を見て、私たちがこれまで見てきた中で、似たような文章を思い出しませんか。
第23章に、「信用の発展につれてこの貨幣資本そのものが社会的な性格をもつようになり、銀行に集中されて、もはやその直接の所有者からではなく銀行から貸し出されるようになることによって、また、他方では、借入れによってであろうとその他の方法によってであろうとどんな権原によっても資本の所有者ではない単なる管理者が、機能資本家そのものに属するすべての実質的な機能を行うことによって、残るのはただ権能者だけになり、資本家はよけいな人物として生産過程から消えてしまうのである」(P487)という文章がありました。
この文章は、「貨幣資本そのものが社会的な性格をもつ」ことによって資本家階級そのものが不要な寄生階級であることを述べた大変重要な文章ですが、この文章も、「他方では」以降でその前の文章の「銀行信用」の機能の別の側面を述べていて、両方合わせて「銀行信用」のことを言っています。今回の文章と同じ言い方です。もう一度、この文章を思い出すのも良い勉強です。
大谷氏の理解は、「銀行業者がすべての貨幣の貸し手の代表者として再生産的資本家に相対する」という資本主義的生産様式の社会における銀行の役割を多面的に論究しようとするマルクスの研究の深さを無視した、あまりにも安易な、そして誤った理解です。エンゲルスは、こんなことで非難されるとは、夢にも思わなかったことでしょう。
このように、このパラグラフは、「信用制度」の「商業信用と銀行信用」という二つの面のうちの「他方の側面」である「銀行信用」の意義を明らかにしており、マルクスの草稿で「公信用」との対比で「商業信用」といっているものをエンゲルスが「商業・銀行業者信用」と変え、これを受けて大月版『資本論』の編集者集団が分かりやすく商業信用と銀行信用とに分解した、エンゲルスの意図と、それを理解した日本の編集者集団の意図とが正しかったことがよく分かる文章です。
〈大谷氏の批判〉
次に大谷氏は、大谷氏の言う(なぜ「大谷氏の言う」というかというと、大谷氏とMEGA版とでは、整理の仕方が違うので、あえてこのような言い方をしています。)「信用制度についての雑録」部分の「エンゲルスによる手入れ」について、「エンゲルスは、この第25章のなかに「架空資本」を見いださなければならなかった」、だから、「他の箇所で見いだされた材料の挿入」(エンゲルスの序文)として、Ⅰ、Ⅳ、Ⅴという三つの草稿を挿入したと言います。
同時に大谷氏は、このホームページのはじめに述べたように、第1巻の「はしがき」で、恩師である三宅義夫氏が『資本論』第3部第5篇の全体の編成について誤った「定説」を主張する論拠のほとんどすべてが、草稿第5章の編成を正しく読みとれなかったエンゲルスが自分の誤った理解に合うように行った手入れの箇所だったと言って、三宅氏の主張の「誤り」(?)まで、エンゲルスの編集のせいにしています。
〈私の考え〉
エンゲルスの編集に対する大谷氏のこのような批判(?)は、残念ながら私には言いがかりとしか思えません。
もう一度、『資本論』第3部のエンゲルスの序文を見て下さい。いまでは、誰でも認めるように、『資本論』第五篇は、「草案」も「筋書きさえもなく」、「ただ仕上げの書きかけがあるだけで」、「この書きかけも一度ならず覚え書きや注意書きや抜き書きの形での材料やの乱雑な堆積に終わっている」ものでした。そこで、何年にもわたる試行錯誤の結果、エンゲルスが下した編集上の決断は、マルクスがこの篇に「与えようと意図したすべてのものを少なくともおおよそは提供するようにする」と、「それはマルクスの著書ではない」ものになるので、そのような編集をあきらめ、「現にあるものをできるだけ整理することに限り、ただどうしても必要な補足だけを加えるということ」でした。(大月版④P9-10)
マルクスがこの篇に「与えようと意図したすべてのものを少なくともおおよそは提供するようにする」ために、エンゲルスが「マルクスの著書ではないもの」を編集するとしたら、『資本論』はどうなったでしょうか。
たとえば、それは、「架空資本」に関していえば、第二九章(銀行資本の諸成分)と第三〇章(貨幣資本と現実資本)等の大幅な再編集が必要になったでしょうし、第二六章(貨幣資本の蓄積 それが利子率に及ぼす影響)もその詳しい論究は第三〇章以降に置き、これまた、大幅な再編集が必要になり、第二八章(流通手段と資本)の配置もその中で大きく変化したことでしょう。その結果、大谷氏の言う「雑録」も「捜論」も、マルクスの『混乱』も、最終稿のための材料の部品になり、『資本論』第五篇は現在の『資本論』とはかなり異なるものになったことでしょう。
このように、「貨幣」と「信用」と「貨幣資本」と「現実資本」との資本主義社会での複雑な絡み合いのなかで、〝マルクスがこの篇に与えようと意図した〟とおりに編集できるのは、マルクスを知りつくした、無二の友であるエンゲルス以外にはいないはずです。たぶん、AIがどんなに進歩してもエンゲルスには及ばないでしょう。しかし、そのエンゲルスが決断し、行った手入れは、必要最小限のものでした。その結果、第25章は、先に示した「第25章の概略」のような編集になったのです。だから、苦労に苦労を重ねたエンゲルスに対して、草稿第5章の編成を正しく読みとれなかったからこのような編集をしたという大谷氏は、エンゲルスの『資本論』編集の意図をエンゲルスの序文の立場で、もう一度熟慮したほうがよさそうです。
なお、大谷氏はこの章に出てくる「架空資本」と第29章相当部分で論じられる「架空資本」とは違うといいます。その通りですが、そう単純に言い切れるものではありません。第29章では銀行資本の諸成分は現金と有価証券からなっていること、その有価証券は貨幣資本という「架空資本」によって得られること、その最大部分である手形による「信用」拡大を中心に有価証券の「架空資本」としての架空性を、「他の箇所で見いだされた材料の挿入」を含めて「実例」で示し、銀行資本の諸成分が第25章で論究した「架空資本」で満ちていることを述べています。
エンゲルスはこのように、第29章へ繋がるものとして、第25章の後半で、資本主義的生産様式のもとでの「信用」の役割とその「架空資本」としての特質を、マルクスの草稿の流れに沿って「現にあるものをできるだけ整理し」、「ただどうしても必要な補足だけを加えるということ」通じて編集したのです。
このエンゲルスの編集のどこに、大谷氏の恩師である三宅義夫氏の誤った「定説」の論拠があるのか、私にはわかりません。しかし、ここでエンゲルスが編集した内容に、科学的社会主義の観点から見て、誤りがないことだけは確かです。

〈第26章 貨幣資本の蓄積 それが利子率に及ぼす影響〉について
・第26章の概略
この章は、第25章の続きで、貨幣資本の蓄積に関する「通貨理論論評」等からの抜粋、それを受けての、『銀行委員会』での問答の引用を通じての、主としてオーヴァストーンの銀行業者の立場からの貨幣資本にたいする見方の矛盾と混乱および貨幣資本の蓄積と利子率の関係についての曖昧な態度の追求からなっています。
最初の貨幣資本の蓄積に関する「通貨理論論評」等からの抜粋は、大谷氏の言う「雑録」の最後の部分で、貨幣資本の蓄積が増えるとその充用先が必要となり金あまりが投機を作ること、イングランド銀行の金融政策のもとでの輸入の大超過の結果遊休資本が減少し信用が厳しくなり、その結果、ユダヤ人や貨幣取引業者が儲かったこと等が述べられています。
次に、大谷氏のいう「挿論」部分(大月版P530の2行目以降)では、上記を受けて、ノーマンとオーヴァストーンの謬論への批判がおこなわれます。ノーマンは銀行券は資本である商品を買うためにあり、貨幣資本に対する需要は貨幣そのものに対する需要ではないといい、このノーマンの主張にマルクスは、異なる商品を扱う者も同じ利子率で貨幣を手に入れることを指摘して論駁します。また、マルクスは、オーヴァストーンが、利子率の上昇は利潤率の上昇の結果であり、資金需要は事業拡大と結びついていると考えたり、自分の都合しだいで「資本の価値」を現実資本に関係させたり貨幣資本に関係させたりしているが、オーヴァストーンにとっての「資本」の意味は「利子を取って貨幣を貸し出すこと」にあるということを『銀行委員会』でのオーヴァストーンの問答を通じて明らかにします。
マルクスは、これらを通じて、ノーマンもオーヴァストーンも、「貨幣資本」についても「貨幣資本」の蓄積と「利子率」との関係についても、正しい認識をもっていないことを曝露します。
・〈第26章への大谷氏の批判〉
大谷氏は、第26章がマルクスの「草稿のテキストとほぼ一致している」ことを認めつつ、「エンゲルスが第26章をつくるときに犯したと考えられる過誤は、大きく言って二つある」(P218-219)と言います。
過誤の第一は、「エンゲルスは小部分への小見出しを第26章部分全体につけられた表題だと勘違いした」と推測され、第26章に付けられた表題がこの章全体の内容を表すものとはなっていないと言い、過誤の第二は、第26章は、第25章に付随する「雑録」と続けて書かれた「捜論」からつくられており、第26章を第25章の本文部分および第27章と対等に置くべきではなかったと言って、「このような第26章の表題と内容(?内容は「草稿のテキストとほぼ一致している」と認めているのになぜ──青山)と位置とが、第5篇の第25章以降の展開の筋道をきわめてわかりにくいものにし」(P221)たといいます。
・〈私の意見〉
まずはじめに、「第26章」の編集の経緯について見てみましょう。
もう一度、「〈第25章〉について」の「マルクスの草稿〔317上④および⑤〕について」の「・〈大谷氏の批判と私の考え〉」の項で見た、『資本論』第五篇に関するマルクスの「草案」の完成度とそれを踏まえてのエンゲルスの『資本論』を編集するにあたっての決断のところを思い出して下さい。
この章こそ、「覚え書きや注意書きや抜き書きの形での材料やの乱雑な堆積」の草稿から、「第26章の概略」で見たように、「貨幣資本の蓄積」と「それが利子率に及ぼす影響」というこれまでのマルクスの草稿では本格的に論究されていない重要なテーマについて、「貨幣資本」についても「貨幣資本」の蓄積と「利子率」との関係についても正しい認識をもっていないノーマンとオーヴァストーンの謬論への批判を行ない、上記のような編集の趣旨にもとづき、マルクスの草稿全体の順序にしたがって編集したものと思われます。
なお、このようにやむを得ず行われた「章」の編集の身近な例として、第28章があります。第27章の〝むすび〟の部分でマルクスとエンゲルスは『資本論』第五篇の編集について、「これまでわれわれは、信用制度の発展──そしてそれに含まれている資本所有の潜在的な廃止──をおもに産業資本に関連させて考察してきた。以下の諸章では、信用を利子生み資本そのものとの関連のなかで考察する」と述べていますが、「信用を利子生み資本そのものとの関連のなかで考察」しているのは第29章「以下の諸章」で、第28章はその橋渡し的な文章の草稿で、第28章も、上記のようなエンゲルスの『資本論』編集にあたっての試行錯誤から生まれたものです。
なお、大谷氏は、第28章について、「トゥクとフラートンとを批判した第28章部分には、さまざまの混同を伴っているトゥクやフラートンの議論から、この重要な区別をつかみだして提示し、それにもとづいて彼らの区別のあいまいさや不十分さや誤謬を批判するという作業が──明示的にではないにしても──含まれていてもよいのではないか、と考えられるのであるが、これまで見てきたように、この部分でのマルクスの記述にはほとんどそのような形跡を見ることができなかった」とマルクスを責めていますが、マルクスとエンゲルスは第28章で、「通貨と資本との区別と流通手段がそのときどきにもつ機能の区別」をしっかりとしていますので、是非、『資本論』で確かめて下さい。そして、私たちが「通貨と資本との区別と流通手段がそのときどきにもつ機能の区別」をしっかりするために、この章は大変勉強になる「章」で、この章を他の章と対等に置くべきではなかったなどと言う前にしっかりと読んで学んでいれば、このようにマルクスを責めることもなかったでしょう。
*なお、「第28章」についてのコメントは、このホームページには掲載しておりませんので、是非、下記のPDFファイルを参照して下さい。
さて、それでは、大谷氏の主張の是非を吟味してみましょう。
大谷氏は、氏の言う「雑録」に続く「捜論」部分について、「貨幣資本の蓄積 それが利子率に及ぼす影響」という表題をつけるのは、「きわめて一面的であって、それらの内容を表してはいないと言わざるをえない」(P220)と言っています。
しかし、私は、「・第26章の概略」で、「 マルクスは、これらを通じて、ノーマンもオーヴァストーンも、『貨幣資本』についても『貨幣資本』の蓄積と『利子率』との関係についても、正しい認識をもっていないことを曝露します」と述べましたが、マルクスは、大谷氏の言う「捜論」部分で、ノーマンやオーヴァストーンが「銀行業者」の立場で「貨幣資本」の需要を「資本」の需要と見て、借り手が必要とするものが「資本」としての貨幣ではなく「貨幣」そのものであることを見ないこと、したがって「利子率」が「貨幣資本」の需要と供給によって決まるということを見ていないことを、『銀行委員会』での問答等を通じて批判しており、オーヴァストーンが貨幣の価値は資本の価値だといい、その資本とは各人がその事業に必要とするものだというが、「貨幣資本」が「資本」であるのは彼ら銀行業者が「利子を取って貸し出す」時であり、そのことによって「貨幣を資本に転化させるのである」(大月版『資本論』P9-10)ことをオーヴァストーンの証言を通じて明らかにしています。
このように、『資本論』を読めば、第26章が「貨幣資本の蓄積」の意味と「それが利子率に及ぼす影響」について述べているのは明らかであり、大谷氏の「貨幣資本の蓄積 それが利子率に及ぼす影響」という表題をつけるのは、「きわめて一面的であって、それらの内容を表してはいないと言わざるをえない」という主張は、まったく当を得ていません。
そして、大谷氏は、「このような第26章の表題と内容と位置とが、第5篇の第25章以降の展開の筋道をきわめてわかりにくいものにし」た(P221)といい、「草稿によって見ると、エンゲルス版で見られるのとはかなり異なった筋道が見えてくるようにも思われるのであるが、ここでは立ち入らないことにする」(P222)とも言います。
もう一度、先ほど見た第27章の〝むすび〟の部分の言葉を思い出して下さい。
マルクスとエンゲルスは、「これまでわれわれは、信用制度の発展──そしてそれに含まれている資本所有の潜在的な廃止──をおもに産業資本に関連させて考察してきた。以下の諸章では、信用を利子生み資本そのものとの関連のなかで考察する」と述べて、「第5篇の第25章以降の展開の筋道」を明確にし、共通の認識をもっています。
大谷氏は、このようなマルクスとエンゲルスの共通認識以外のなにか違った「筋道」があるように「思われる」のであれば、そのことに、「ここで立ち入らなければならない」のではないでしょうか。そうしないと、不破さん並みの人物と見られてしまっても仕方がないでしょう。
この章でのエンゲルスの挿入文に関する青山のコメント
『資本論』(P544~547)に挿入されたエンゲルスのコメントのなかで、貨幣の前貸・資本の前貸等について述べられている部分で同意できない点がありますので、表明させていただきます。
エンゲルスは、①担保なしの貸付は貨幣の前貸であり資本の前貸であるといい②担保ありの貸付は貨幣の前貸ではあるが資本の前貸ではないといい③手形の割引は前貸ではなく売買だといいます。ここでいう「資本の前貸」が、生産的資本・現実資本の増加のための資本の前貸という意味であるとすれば、エンゲルスの①と②の区分は正しくありません。なぜなら、担保の有る無しは「資本の前貸」かどうかには関係ありません。「担保」された〝モノ〟は、ただ「担保」とされているだけで、資本としてその人のもとで生きています。「資本の前貸」であるかの基準は、「貨幣の前貸」が一時的な支払手段としてではなく、商品の購入として、それも消費財の購入ではなく資本財の購入の手段であるかどうかにあります。
なお、エンゲルスは、第28章(P582-583)でも同様な主張を行っていまが、ここでは「有価証券」を担保に入れ、その有価証券は「準備資本として機能するべき任務をもっていた」との前提があるので、この場合は「貨幣の前貸」ではあるが「資本の前貸」ではありません。是非、先ほどのPDFファイルをご覧ください。
〈第27章 資本主義的生産における信用の役割〉について
このホームページの最初に書いたように、大谷氏は、草稿第5章の編成を正しく読みとれなかったエンゲルスが自分の誤った理解に合うように手入れを行い、そのような手入れの箇所の多くが第25章および第27章に当たる部分に含まれているといい、そのことを明らかにするために本書2巻の第5章と第7章を書いたと言っていました。
しかし、第7章での〈第27章〉についてのコメントを見ると、「その内容はほぼマルクスの草稿と一致しており、第5篇のなかでも、エンゲルスによる加工が相対的に少ない部分に属している」(P275)と述べられており、エンゲルスが自分の誤った理解に合うように手入れを行った箇所の指摘はありません。
その代わりに出てくるのが、第25章「本文部分」と第27章との間にある、大谷氏の言うところの「雑録」と「捜論」から第25章と第26章をエンゲルスが編集したが、「第25章本文部分と第27章とを『信用制度概説』としてつかんでみる」ことによって、「第25章本文部分は、信用制度とはどのようなものかを述べ、第27章はその信用制度がどのような役割を果たすのかを述べている」ことが分かるという主張です。
しかし、マルクスとエンゲルスは、「〈第26章〉について」の中で触れたように、この章(第27章)の〝むすび〟の部分で、『資本論』第五篇の編集について、「これまでわれわれは、信用制度の発展──そしてそれに含まれている資本所有の潜在的な廃止──をおもに産業資本に関連させて考察してきた。以下の諸章では、信用を利子生み資本そのものとの関連のなかで考察する」と述べていますが、これまで見てきたように、第21章から第24章が「利子生み貨幣資本」について、そして、第25章から第27章までが「利子生み貨幣資本」の意味・役割の再確認を含む「信用制度の発展」について書かれており、エンゲルスが「序文」で述べているとおりにマルクスの草稿に沿い、マルクスとエンゲルスの共通認識に沿った編集がおこなわれています。
大谷氏は、「論旨の展開の筋道」がどのように変えられたのかも、「マルクスの構想」がどのように「覆い隠」されたのかも示さずに、「エンゲルス版第5篇は、草稿第5章とは全体の編成も大きく異なっており、エンゲルスの誤読にもとづいてなされた章別編成によって論旨の展開の筋道がほとんどなくなって」いて、エンゲルスの編集は「マルクスの構想を覆い隠すという罪つくりな仕事」であったという非難を『資本論』に浴びせ、客観的には、不破さんの、マルクスが「第三部」を資本主義的生産の「総過程の諸姿容」といっているのにエンゲルスが「資本主義的生産の総過程」と変えてしまったのは、「第三部全体の趣旨を誤解させることで、残念な訂正だったと思います」(「『資本論』探求」③「『資本論』第三部を読む」)などと言う、マルクス・エンゲルス批判の片棒を担ぐような役割を演じてきました。
しかし、私たちがこれまで見てきたように、『資本論』第五篇の第21章から第27章までは、マルクスの草稿でのマルクスの論及に沿った編集がおこなわれています。
だから、私たち庶民が、重箱の隅を突っつくことを目的とせず、当時のマルクス・エンゲルスから彼らの考えを学ぼうとするとき、エンゲルスが編集した『資本論』は、マルクスの草稿よりも丁寧でわかりやすく書かれており、科学的社会主義の思想を学ぶうえで、たいへん貴重な古典と言えます。
『資本論』は、ちょっと難しく書かれていますが、現代を考え、未来を展望するうえで、多くの若い人たちに、是非、読んでいただきたい書物です。

③『資本論』第5篇は、エンゲルスによって「論旨の展開の筋道がほとんどなくなった」ガラクタに変えられてしまったのか
・『資本論』の価値を不等に低める大谷氏の勇み足
外国語が堪能でない私たちが、大谷氏の『マルクスの利子生み資本論』(全4巻)を通じて、マルクスの草稿に触れることができるのはたいへん意義のあることです。
しかし、このホームページの冒頭で紹介した、「あらためて草稿第5章をエンゲルス版第5篇とつきあわせて精読するなかで、エンゲルス版第5篇は、草稿第5章とは全体の編成も大きく異なっており、エンゲルスの誤読にもとづいてなされた章別編成によって論旨の展開の筋道がほとんどなくなっており、さらに細部でもいたるところにエンゲルスの手入れ(書き換え、削除、書き加え)があって、草稿第5章そのものに拠らなければマルクスの利子生み資本論をそのあるがままにつかむことはできない、と確信するようになった」との『資本論』についての大谷氏の誤った評価は、エンゲルスが編集した『資本論』についての予断と偏見をうえつけ、『資本論』の価値を不等に低め、『資本論』の購読意欲を低下させるものです。同時に大谷氏のこれらの言動は、このあとで紹介する氏の『資本論』にたいする評価からみても、草稿と「エンゲルス版」との違いを強調するあまり犯した、科学的社会主義の経済学の研究者らしからぬ勇み足のようです。
・第3巻の最も困難な篇を立派に編集したエンゲルス
大谷氏の『マルクスの利子生み資本論』2の第5章「3 エンゲルスの編集作業の経過」には、1885年5月19日付のラファルグあての手紙でエンゲルスが「銀行資本と信用とに関する篇はちょっと雑然として」いることや、1891年7月1日付のシュミットあての手紙で第5篇には、「信用制度と貨幣市場」に関する「たくさんの新しいものと、さらにそれよりもはるかに多くの未解決なものとが、つまりもろもろの新たな解決とならんでもろもろの新たな課題が見いだされるのです」とその内容の濃さについても述べていることなど、エンゲルスがいろいろな人に送った手紙の中で、この銀行や信用に関する篇の編集がいちばん困難であることが述べられています。
大谷氏が草稿と「エンゲルス版」との違いを「マルクスの構想を覆い隠すという罪つくりな仕事でもあったのである」等々と非難するこの第5篇──それは誰もが認めるように、「草案」も「筋書きさえもなく」、「ただ仕上げの書きかけがあるだけ」の草稿──の編集は、エンゲルス自身が第3部への序文で述べているように、マルクスがこの篇に「与えようと意図したすべてのものを少なくともおおよそは提供するようにする」と、「それはマルクスの著書ではない」ものになるので、試行錯誤のすえ、そのような編集をあきらめ、「現にあるものをできるだけ整理することに限り、ただどうしても必要な補足だけを加えるということ」(大月版『資本論』P9-10)とした、第一バイオリンとともに第二バイオリンをも同時に弾かざるを得なくなった、あまりにも忙しすぎるエンゲルスの晩年の、それこそ、努力の結晶でした。
確かに、「細部でもいたるところにエンゲルスの手入れ(書き換え、削除、書き加え)があって」、マルクスの「草稿」を「そのあるがままにつかむこと」ができなくなったかもしれませんが、これまで見てきたように、エンゲルスの編集によってマルクスの考えがねじ曲げられたり、エンゲルスが「マルクスの構想を覆い隠す」ような編集をしたことはありませんでした。ここで取り上げたエンゲルスの編集のほか、エンゲルスは、誤記等不完全な文章の改善や不十分な記述の訂正と文章の加除等を無数に行ない、読みやすく理解しやすくすることを通じて、大谷氏も認めるように、第5篇の「未定稿的な性格の強い草稿はより完成した叙述の装いを与えられ、読者にとっては読みやすいものとなった」のです。
このようにして、エンゲルスは第3巻の最も困難な篇の編集を立派に成し遂げました。
・大谷氏の『資本論』にたいする評価と『資本論』の葬り方
大谷氏は『マルクスの利子生み資本論』2の補章5「1 第3部エンゲルス版の歴史的意義」でエンゲルス版の歴史的意義いついて次のように述べています。
「マルクス自身が刊行できなかった第2部および第3部を編集・刊行して、彼の主著の理論的部分を完成させたエンゲルスの功績は、それらがもつ欠陥や不十分さにもかかわらず、不朽のものである。」(P360)といい、「エンゲルスの最晩年の悪戦苦闘によって、人類は、そしてとりわけ労働者階級は『資本論』の第2部および第3部をもつことができた。かりに、エンゲルスによる第2部および第3部の刊行がなかったとして、これまでに経済学者は、そこで分析され展開されている諸問題をそこでなされているような仕方で自ら展開し、さらにそれを資本主義的生産の理論的分析に適用することができていたであろうか。………
エンゲルス編の第2部および第3部の欠陥をあげつらうことは、マルクスの草稿がかなりの程度にまで見ることができるようになったいまでは、むしろ手もない仕事だと言うことさえできる。しかしながら、第2部および第3部の編集・刊行というエンゲルスの不朽の業績は、言い換えればエンゲルス版『資本論』第2部および第3部の刊行の歴史的意義は、それらのもつ欠陥や不十分さによってけっして相殺されることはないであろう」(P363-4)、と。
これまで、私は、大谷氏の言う「欠陥や不十分さ」の主要なものについて、みなさんといっしょに見てきました。そのなかで、エンゲルスの編集した『資本論』が、大谷氏が言うような「マルクスの構想を覆い隠すという罪つくりな仕事」などではないこと、そして、エンゲルスはマルクスの草稿を最大限生かすよう努力していることを、明らかにしてきました。大谷氏が、エンゲルス版『資本論』を「エンゲルスの不朽の業績」と認めてくれるのは大変ありがたいことですが、率直に申し上げて、これまで見てきた大谷氏のエンゲルスへの悪罵の数々は、「エンゲルス版『資本論』第2部および第3部の刊行の歴史的意義」を否定するような物言いとしか思えず、残念でなりません。
そして、大谷氏はまた、エンゲルス版第3部の今後について、あたかも害毒でもあるかのように、次のように述べて、『資本論』を葬ろうとしています。
「今後は、第3部の版本としては、なによりもMEGA(マルクス・エンゲルス全集─青山)版が使われるべきであるが、MEGA版は草稿をそのまま収録したものであって、読みやすいものではけっしてないから、MEGA版にもとづく新しい普及版が出るまでは、エンゲルス版も利用されることであろう。ただその場合にも、エンゲルス版の性格と限界とがよく理解されたうえで利用されることが臨まれる」(P367)、と。
しかし、「読みやすい」、それなりの完成度をもった「新しい普及版」は誰が編集するのか。誰にも「編集」することは出来ないでしょう。
私は、前に(*)、第25章の編集に関し、「〝マルクスがこの篇に与えようと意図した〟とおりに編集できるのは、マルクスを知りつくした、無二の友であるエンゲルス以外にはいないはずです。たぶん、AIがどんなに進歩してもエンゲルスには及ばないでしょう。しかし、そのエンゲルスが決断し、行った手入れは、必要最小限のものでした」と述べました。『資本論』は、エンゲルスが、『資本論』がマルクスの著作とは別のものにならないよう十分に配慮したうえで、読みやすく理解しやすいように編集したもので、科学的社会主義の思想が貫かれています。だから、エンゲルス以外にマルクスの草稿をいじるとしたら、次の方法以外に「新しい普及版」など作りようがありません。
(*)「②『資本論』の第25章、第26章および第27章のどこが問題なのか」の「〈第25章〉について」の「・エンゲルスの編集についての大谷氏の批判について」の「マルクスの草稿〔317上④および⑤〕(P168-171)に関して」の「・〈大谷氏の批判と私の考え〉」を参照して下さい。
その方法とは、①読みやすさや展開は別にして、「草稿」を知ってもらうために「草稿」を理解しやすくするとすれば、MEGA版にみんなでいっぱい(注)を付けること、②エンゲルスに代わって、「それはマルクスの著書ではない」ものになるが、マルクスが「資本論」に「与えようと意図したすべてのものを少なくともおおよそは提供するようにする」ことを考えて、マルクスの草稿ともエンゲルスの編集とも違う「資本論」を「編集」すること、③現行の『資本論』をもとに、補注を加えること、の三つです。この場合、科学的社会主義の思想を否定する人がマルクスを利用しようとすると、とんでもない「資本論」が生みだされます。
これまで見てきたように、「エンゲルス版『資本論』」は、不破さんのように、マルクスの資本主義の見方や論究の内容を「修正」して私たちをミスリードするような有害な著作などではありません。「エンゲルス版『資本論』」は、マルクスの〝資本論〟を学ぶ上で欠くことのできない著作です。『資本論』に何らかの注釈等が必要であるならば、大谷氏を含むマルクス経済学の研究者が英知を結集して直ちに取り組むべきであり、「エンゲルス版の性格と限界とがよく理解されたうえで利用されることが臨まれる」などと、『資本論』への中傷の言葉をもって、なんの知識も持ち合わせていない『資本論』読者に丸投げされたのでは、これまで大谷氏が主張してきたことは、「エンゲルス版『資本論』」の価値を落とし、労働者が『資本論』に触れるのを妨害するための手段ではなかったのかと思われても、しかたがないのではないでしょうか。
・詐欺師が編集したものを「マルクス『資本論』」などと僭称させてはならない
〝日本共産党のカウツキー〟とでもいうべき、現在の日本共産党を牛耳っている不破さんは、科学的社会主義と称してエセ「科学的社会主義」を「共産党」のなかに蔓延させようとする詐欺師ですが、不破さんはマルクスの威を借りて、『資本論』の内容を改竄してエセ「科学的社会主義」を拡めようとしています。
不破さんは、『資本論』をねじ曲げて、「新しい見地では、可変資本部分の相対的減少は、否定的な現象ではなく、独自の資本主義的生産様式の蓄積過程の当然の、積極的な現象」であり、「恐慌期が過ぎると、資本主義は前回の周期を大きく上回る繁栄を取り戻し、衰退現象を見せない」と資本主義万々歳論の論拠とし、「マルクスは、人間の生活時間のうち、この時間(物質的生産にあてるべき時間──青山補注)部分を『必然性の国』、それ以外の、各人が自由にできる時間部分を『自由の国』と名付けました」とウソを言い、資本主義社会にも〝余暇〟があり「自由の国」があると言うなど、自論にあわせて『資本論』を「解釈」(改竄・捏造)してきました。
その不破さんが、編集責任者(監修者)になって「マルクス『資本論』」と銘打った書籍の刊行をはじめました。エセ「科学的社会主義」者の詐欺師が編集したマルクス・エンゲルス・レーニンの思想(科学的社会主義の思想)の〝まがいもの〟を「マルクス『資本論』」などと僭称させてはなりません。
*資本主義万々歳論については、ホームページ4-19「☆不破さんは、マルクスが1865年に革命観・資本主義観の大転換をしたという、レーニンも気づかなかった大発見を、21世紀になっておこない、マルクスの経済学をだいなしにしてしまった。」及びホームページ4-20「☆「社会変革の主体的条件を探究する」という看板で不破さんが「探究」したものは、唯物史観の否定だった」を、「自由の国=〝余暇〟」論については、ホームページ4-26「『資本論』刊行150年にかこつけてマルクスを否定する不破哲三氏」を、是非、参照して下さい。

Ⅱ、『資本論』の位置づけとその読み方
①『資本論』の守備範囲
・資本主義経済を解明するベースとなる〝古典〟
『資本論』の研究範囲と執筆の目的について、初版の序文でマルクスは次のように述べています。
「この著作で私が研究しなければならないのは、資本主義的生産様式と、これに照応する生産諸関係および交易諸関係である。……一国は他国から学ばなければならないし、また学ぶことができる。たとえある社会がその運動の自然法則の手がかりをえたとしても、──そして近代社会の経済的運動法則を暴露することがこの著作の最終目的である──、その社会は自然的な発展の諸段階を跳び越えることも法令で取り除くこともできない。しかし、その社会は、分娩の苦痛を短くし緩和することはできるのである。」(大月版『資本論』①(初版序文)P8-10)と。
このように、『資本論』は「資本主義的生産様式と、これに照応する生産諸関係および交易諸関係」を研究することを通じて、近代社会の経済的運動法則を暴露し、新しい社会の分娩の苦痛を短くし緩和することを執筆の目的としています。
そして『資本論』は、その研究範囲を次のように限定しています。
「われわれがこの章で研究する諸現象は、その十分な展開のためには、信用制度と世界市場での競争とを前提するのであって、この世界市場こそは一般に資本主義的生産様式の基礎をなしその生活環境をなしているのである。しかし、これらの資本主義的生産のいっそう具体的な諸形態を包括的に叙述するということは、資本の一般的な性質を把握してからはじめてできることである。しかも、このような諸形態の叙述はこの著作の計画外のことであって、もし続巻ができればそれに属することである。」(大月版『資本論』④ P140F2-6)と。
つまり、『資本論』は、その守備範囲が「資本の一般的な性質の把握」であり、「資本主義的生産のいっそう具体的な諸形態を包括的に叙述する」ことは「この著作の計画外のこと」であることを述べています。
*『資本論』の位置づけ等については、ホームページ5「温故知新」→「Aマルクス・エンゲルスと資本論」等を参照して下さい。
・『資本論』の守備範囲を完璧に書いたものではない
このように、『資本論』は、その守備範囲を「資本の一般的な性質の把握」に定めて、必要に応じて「世界市場」での競争や景気循環等を含む資本主義的生産様式のもとでの「生産諸関係および交易諸関係」の発展した具体的な諸形態の叙述をおこなっています。
しかし、同時に、これまで見てきたように、残念ながら『資本論』は、草稿段階のものもあり、その守備範囲を完璧に書いたものではなく、エンゲルスの手を大いに煩わせるものとなりました。
②『資本論』を含む古典の学び方
・私のように原典に近づくことのできないものの古典のよみかた
私はドイツ語もロシア語もまったく出来ません。英語でさえ、大学一年のとき、サミュエルソンの「経済学」第七版の英語版と日本語訳版とをにらめっこしたくらいで、昼夜を分かたぬ学生運動で英語学習の機会を棒に振ってしまいました。だから私には、マルクス・エンゲルス・レーニンの原典に当たって検証することなどまったく出来ません。そんな私がマルクス・エンゲルス・レーニンの著作の日本語訳を読むに当たって心がけていること、私のようにドイツ語も英語も読めず、原典に近づく機会もないものが、外国の書物に接する場合、いつも留意していることは、次のような点です。
日本語訳された著作には、必ず、以下のようなことがあり得るというということ。
①誤植により意味が通じなかったり、反対の意味をあらわすことがありうること
②元の言葉の多様な意味の中から訳者が選んだ日本語が適切でない場合がありうること
③意訳した文章が原典の趣旨に反する場合がありうること
④著者の主張が誤っている場合がありうること
これらを踏まえて、以下のような読み方をしています。
①ワード、フレーズの意味を広めに捉えるようにすること
②一言一句の言葉ではなく文脈全体をつかむということ
③私がマルクス・エンゲルス・レーニンだとしたらどんな意味を込めてこの文章を書いているのかということをつかむ努力をするということ
④書かれていることを「教条」的に捉えるのではなく、自ら判断すること
このような古典の読み方をすることによって、私は、自分の求めている知識を深めるよう心がけてきました。
そして、みなさんも、これから私のホームページを閲覧するに当たって、ぜひ私と同様な態度で臨んでいただければありがたいと思います。なぜなら、このホームページには、たぶん、私の記憶違いや文字の変換まちがい等によるとんでもない誤りや誤解の種が、数多く残されているかもしれません。そのことからくるマルクス・エンゲルス・レーニンの思想に対する誤解を避けるためにも、上記のような態度が必要であるだけでなく、それ以上に、そのような読み方は、あなたのマルクス・エンゲルス・レーニンに対する理解をより深め、科学的社会主義の深耕に必ずや寄与するものと確信するからです。
・古典から何を学ぶのか
私たちは何のためにマルクス・エンゲルス・レーニンの著作を読むのでしょうか。
それには、二つの目的があるのではないかと思います。
一つは、マルクス・エンゲルス・レーニンが発見した理論から〝真理〟をしっかり摑み、自らの思想の中に消化して血肉化し、より豊かな思想をもった個人として、自らの行動に生かすということです。
もう一つは、古典の中にある現代につうじるヒントを摑むとともに、古典の中で欠けているもの不十分なものをしっかり摑んで、現代にいきる理論を発展させるための糧とするということです。
だから、大谷氏を含む研究者に期待することは、どこがマルクスの文章でどこがエンゲルスの文章かを明らかにすることも大切なことですが、それらを踏まえて、現代の経済を解明する視点から、マルクスのいっている大切な点やエンゲルスが補足したことで大切な点をしっかりと明らかにし、古典に欠けているところを補い、彼らの業績を発展させることに全力を尽くしていただきたいということです。
Ⅲ、『資本論』の歴史的限界と現代の資本主義
①『資本論』の歴史的限界とマルクス・エンゲルス・レーニン
マルクスとエンゲルスは人類史の流れを解明し、搾取の仕組みと資本主義の矛盾を明らかにし、資本主義(賃金奴隷制)の改善の意義と限界を明らかにして、科学的社会主義の任務とたたかいの方向を示し、未来社会はどのように実現されるかを明らかにしました。
マルクスとエンゲルスは、資本主義の発展は「生産過程の物質的諸条件および社会的結合を成熟させるとともに、生産過程の資本主義的形態の矛盾と敵対関係とを(成熟させ──青山加筆)、したがってまた同時に新たな社会の形成要素と古い社会の変革契機とを成熟させる」ことを明らかにしました。
*詳しくは、是非、ホームページ5-1「☆マルクス・エンゲルスの大事な発見」を参照して下さい。
そしてマルクスは、「独占資本は、それとともに開花しそれのもとで開花したこの生産様式の桎梏になる。生産手段の集中も労働の社会化も、それがその資本主義的な外皮とは調和できなくなる一点に到達する。そこで外皮は爆破される。資本主義的私有の最後を告げる鐘が鳴る。収奪者が収奪される」(大月『資本論』② P995F6-9)と、取得の資本主義的形態(私的独占)の最も発達した形態として「独占資本」を捉えており、マルクスもエンゲルスも、当時、「恐慌」による矛盾の激化を最も重要な「古い社会の変革契機」と見ていました。
マルクス・エンゲルスが生きた時代は、「独占資本」が国内を支配しつつあり、「恐慌」による矛盾の激化が最も重要な「古い社会の変革契機」である時代でした。
*詳しくは、是非、ホームページ4-19「☆不破さんは、マルクスが1865年に革命観・資本主義観の大転換をしたという、レーニンも気づかなかった大発見を、21世紀になっておこない、マルクスの経済学をだいなしにしてしまった。」及びホームページ4-3「☆「桎梏」についての不破さんの仰天思想」等を参照して下さい。
そしてレーニンは、マルクス・エンゲルスの思想の継承者として、その時代のその時期の資本の動向、社会・経済の動向を注視し、最も大切なことは何かを究明し、その「環」を摑むことに努めました。レーニンは「現代が帝国主義時代であり、いまの戦争が帝国主義戦争である」と、当時の歴史的な状況を把握し、「帝国主義」を当時の資本主義を摑む「環」として把握し、「帝国主義とは、資本主義の特殊な歴史的段階」であり、「死滅しつつある資本主義、社会主義へ移行しつつある資本主義である」という「帝国主義」の定義づけをおこないました。
そしてレーニンは、「独占資本」が「国家」と結びついた「国家独占資本主義」を「帝国主義」の特徴とみて、帝国主義間の戦争を阻止して「資本主義」を「社会主義へ移行」することを呼びかけました。そして、それは、「マルクス主義の全精神、その全体系は、おのおのの命題を、(α)歴史的にのみ、(β)他の諸命題と関連させてのみ、(γ)歴史の具体的経験と結びつけてのみ、考察することを要求しています」(『111イネッサ・アルマンドヘ』レーニン全集第35巻P262~263)という、マルクス主義の精神を体現したものでした。だからこそ、このレーニンの呼びかけが、当時の社会・経済のダイナミズムを正しくつかむものとなったのです。
*詳しくは、是非、ホームページ4-13「☆レーニンの資本主義観、社会主義経済建設の取り組み、革命論への、反共三文文筆家のような歪曲と嘲笑、これでもコミュニストか」等を参照して下さい。
このように資本主義の発展につれて、「資本」はその時期々々にあわせて「最大利潤」の追求に邁進します。その結果、マルクス・エンゲルスの時代の「恐慌」、レーニンの時代の「帝国主義」、現代のグローバル資本の行動に基づく「産業の空洞化」等による矛盾の激化が、それぞれの時代の最も重要な「古い社会の変革契機」となるのです。
「資本の一般的な性質の把握」をその守備範囲とする『資本論』が歴史的限界をもつのは当然で、『資本論』の知見を基礎にして「現代の資本主義」を解明すること、そのことこそが、『資本論』が私たちに与えた『資本論』の歴史的限界を克服する方途なのです。
②現代の資本主義の姿の解明
私たちは、マルクス・エンゲルスの古典から資本主義社会の仕組みとその認識の転倒性・虚構性を学びました。
紙幣は兌換から不換になり、次々と新しい金融商品が開発され、巨大銀行は世界中に支店網を張り巡らせ、金融技術は想像を絶する発展をして「暗号資産」がインターネット上の通貨の位置を獲得するまでになろうとする現代、現実資本の世界ではグローバル資本が安い賃金をもとめて「国家と国民」を捨て、先進資本主義諸国の産業の空洞化が深刻化し政治危機に発展しつつある現代で、日本では相変わらず認識の転倒性・虚構性を利用しての、「企業がもうからなければ国民は豊かにならない」、「人件費の安い海外に生産を移さなければ競争に負ける」というイデオロギーが幅をきかせ、マスコミは自由貿易の騎手を褒め称えています。こうした中で安倍首相は、「賃金が上がれば景気がよくなる」という共産党のお株を奪って、賃上げの伝道師のように振る舞っています。
マルクスは、景気がいいときは賃上げのチャンスだから頑張れとは言っても、「賃金が上がれば景気がよくなる」などと言ったことはありません。「賃金が上がれば景気がよくなる」などという、資本主義社会において「本末転倒」な「珍事」が起こるくらいなら、とっくに世の中は良くなっていることでしょう。
エンゲルスは、自分たちの研究のし方について、「われわれがここで考察するのは、われわれの頭のなかだけに生じる抽象的な思考過程ではなく、いつか実際に起こったか、あるいはいまなお起っている現実の事象であ」り、「この方法においては、論理的展開は純粋な抽象の領域にとどまる必要がまったくな」く、「それは、歴史的例証を、現実との不断の接触を、必要とする」と述べ、「マルクスの見解全体が、一つの教義ではなくて、一つの方法です。……それより進んだ研究のよりどころであり、またこの研究のための方法なのです。」と言っています。
私たちが古典に接する場合にも、そして研究者の方々が古典に接したり自らの研究を前に進める場合にも、エンゲルスの上記のことばは大変重要です。
景気が良くならない原因、賃金が上がらない原因をアメリカやヨーロッパの人民は理解しはじめています。日本のマルクス経済学も、1970年代から現在に至る「歴史的例証、現実との不断の接触」を通じて、「グローバル資本」が支配する日本の実態を明らかにし、その存在意義を示さないならば、エンゲルスの言う「おどろくべきがらくた」をつくりだす、役立たずの「学問」と見られても文句は言えないでしょう。
*なお、「グローバル資本」が支配する日本の実態等に関する詳しい説明は、ホームページ1-1「日用品(コモディティー)が充足されはじめた時から、日本社会の深刻な変化が始まった」、ホームページ1-2「2015年8月からタイムマシンに乗って遡る」、ホームページ1-3「今の日本の経済を動かす力」及びホームページ1-4「70年代始め以降、財界が進めた政策」とホームページ6-2-20「第1回大統領候補テレビ討論中継でCNNが伝えたことと、日本のマスコミが報道したこと」及びホームページ6-2-21「米国の歴史を一歩前に進めたトランプ」を、是非、お読み下さい。
なお、マルクスは『資本論』の執筆にあたり、金融に関する部分で、自分の研究が事実に符合しているかを、実務に詳しいエンゲルスに再三確認しています。このように『資本論』は、まさに、ふたりの二人三脚による「歴史的例証、現実との不断の接触」に依拠した研究の成果であること、「それより進んだ研究のよりどころ」であることを、最後に申し添えておきたいと思います。
おまけ
直接古典からではなく、マルクス・エンゲルス・レーニンの考えに触れるに当たって注意していただきたいこと
エンゲルスは、1890年にヨーゼフ・ブロッホあてに書いた手紙で、「歴史における究極の規定要因」は経済的要因であること、この理論はマルクス・エンゲルスの原典で研究してほしいことを述べ、正しく理解しないと「おどろくべきがらくたをつくりだ」すことになると言っています。
事実、日本にも「おどろくべきがらくたをつくりだ」している人たちがいるように思われます。この人たちは、「歴史における究極の規定要因」が経済的要因であることを忘れ、マルクス・エンゲルス・レーニンの著作の中から言葉の一部を「引用」(〝借用〟というべきか!)し、マルクス・エンゲルス・レーニンの考えを歪曲したり、すて去ったりして、自分の都合のいいように〝利用〟して、「おどろくべきがらくたをつくりだ」しています。その代表格ともいうべき人のさまざまな誤りについては別のページで詳しく述べていますが、私は、その人たちの誤りを指摘するためにマルクス・エンゲルス・レーニンの著作からの引用をする場合、かれらの考えが十分理解できる程度の文章の長さを心がけてきました。みなさんがこれらの人たちの文章を読み、これらの人たちの主張の中にマルクス・エンゲルス・レーニンの著作の一部が散りばめられている場合は、必ず原典に当たって、マルクス・エンゲルス・レーニンの真意を確かめて下さい。
なお、私がこのホームページの他のページでそれらの人たちに厳しい態度で接するのは、マルクス・エンゲルス同様に、「罵倒によって敵を批判する者」には「真の批判」、そして「仮借のない批判」が必要だと思ったからです。
以上を十分留意されて、マルクス・エンゲルス・レーニンの古典の紹介・解説・講義等に接していただければ幸いです。
*これらに関して、ホームページ5-1「☆マルクス・エンゲルスの大事な発見──マルクス・エンゲルスが私たちに教えたことで、私たちにとっていま特に大事なこと」及びホームページ5-3「☆レーニンの大切な考え──レーニンがたたかいの中で学んだことで、科学的社会主義の党にとって大事なこと」も、是非、お読み下さい。
別添参考
『資本論』第5篇の第28章以降に関する大谷禎之介氏の『マルクスの利子生み資本論』(全4巻)への私のコメントは以下のPDFファイルをご覧下さい。
・『資本論』第三部28章とマルクスとエンゲルスと大谷氏
・『資本論』第三部29章とマルクスとエンゲルスと大谷氏
・『資本論』第三部30-32章とマルクスとエンゲルスと大谷氏
なお、このファイルの16ページには、
なお、ここで、大谷氏は、第3部第1稿の「第3章 資本主義的生産が進行していくなかで一般的利潤率が傾向的に低下していくという法則」について、「マルクスはここで、利潤率の傾向的低下の法則を明らかにしているが、さらに進んで、『資本主義的生産が進行していくなかで』、すなわち資本の蓄積が進んでいくなかで、この法則がどのように作用し、資本をどのように運動させることになるのか、ということを考察する。そしてこのなかで、資本の諸矛盾の累積が、ある時点でこれらの矛盾を爆発させて、恐慌をもたらすことを明らかにしたのである。」(P259)と言っていますが、これは不破さんの「利潤率の傾向的低下の法則」の評価とは正反対であり、不破さんの「恐慌の運動論」とも考えを異にします。そして、大谷氏は、「なお、念のために述べておくが、マルクスは第3部第1稿第3章を書いたのち、第2部第1稿を書き、その後ふたたび第1稿の執筆に戻ったが、第1稿第5章を書きつつあった時点で、第1稿第3章で明らかにしていた一般的利潤率の傾向的低下の法則そのものについての論証を依然として正しいものと考えていたこと、言い換えれば、そこでの論証を不十分なものだったと反省して取り消すべきだと考えてはいなかったことは、第5章のなかの次の四つの記述を見れば明らかである。これはエンゲルス版第15章部分についても妥当することであろう。」(P275)と述べて、不破さんの暴論をきっぱりと退けています。(PDFファイルのP16)
と、大谷氏が不破さんの期待に反して、不破さんの作った「恐慌の運動論」にもとづく資本主義発展論をきっぱりと退け、不破さんの言う『資本論』第三部「第三篇」の最初の「第一三章」は「マルクスの最大の経済学的発見を記録した輝かしい章」、最後の「第一五章」はここで「展開した理論の主要部分を以後の草稿で取り消した章」、中間の「第一四章」は「第一五章の準備のため」の章で「不要になった章」だという妄想をキッパリと否定していることも明らかにしていますので、是非、お読み下さい。
・『資本論』第三部33-36章とマルクスとエンゲルスと大谷氏